<今日の要点>
神のゆえに、神が立てた権威を重んじる。ただし、神だけが至高の権威者。
<はじめに:第五戒の意義>
十戒の第五戒に入ります。
第一戒から第四戒までは神と人との関係(対神関係)についてでしたが、第五戒から第十戒までは人と人との間の関係(対人関係)についての神の定めとなります。
第五戒はその後半、対人関係についての最初の戒めになります。
最初に神との関係、その次に人との関係というこの構成にも、意味があります。
宗教が先行し、倫理・道徳はそこから出て来ると言います。
神との関係が一階で、倫理・道徳はその上に建てられる二階部分とも言われます。
倫理・道徳を何に基礎づけるか、と言ったら、この世界をお造りになった神の言葉です。
人間とこの世界をお造りになり、そこに自然法則も道徳の法則もお与えになった創造主であられるお方が、創造主の権威をもって、正しいこと、あるべきあり方を定めておられ、その定めを教えて下さるのです。
また対人関係の戒めの最初に、これが置かれているのも、意味深長です。
ちまたにも、親孝行はすべての倫理・道徳の元と言います。
かなり昔の話ですが、ラジオで野球放送をしていたときに、解説の川上哲治さんが、打席に立っていた淡口という選手について
「いやあ、この子は親孝行な、いい選手なんですよ。」
と言ったそうです。
一見、親孝行と野球は関係なさそうですが、そのココロは?と言うと、親孝行なら稼業に打ち込んでうんと稼いで、親に楽をさせてやりたいと考えるはず。
ならば悪い遊びに走るはずがない。
また今時親孝行な子なら素直な心の持ち主だろうから、コーチや先輩の忠言をよく聞くだろう。伸びないはずがない。
「親に感謝の気持ちを忘れない」これは人間らしさの出発点だ、ということでした。
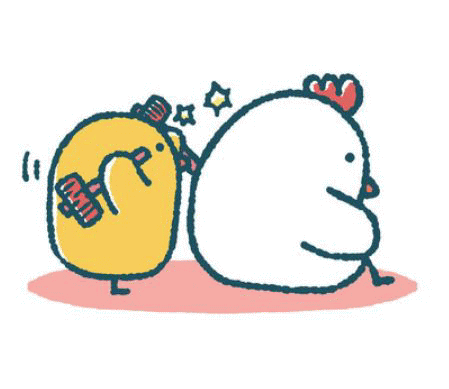
第一テモテ5:4(新約p.410)にも、子どもには、親の恩に報いる習慣をつけさせなさい、とありますが、これは子ども自身を悪から守ることにもなるものでした。
そしてひいては、神に対しても感謝する心を忘れない、大切な信仰教育にもなるものなのでしょう。
なお、ウェストミンスター大教理問答124では、ここの「父と母」は、家庭、教会、国家社会のいづれであれ、神の定めによって、権威上私たちの上にある人を指すと解説されています。
親子関係だけでなく、権威についての教えということです。
<①権威を尊ぶ:神のゆえに>
聖書は原則として、権威は、神が世を秩序をもって治めるために立てたもの、それゆえ重んじるべきものと教えています。
神は混乱の神ではなく、秩序の神です(第一コリント14:33, 40、新約p. 339)。
人が集まれば、みなそれぞれ主義主張が違い、価値観が違い、利害が衝突し、ときには悪を行う者も出て来る中で、秩序と平和を維持するには、その社会における権威が必要で、人々はそれに従わなければいけません。
それが社会のルールです。
ですから、権威が立てられた背後に、神の摂理があることを認めて、それゆえに権威に従うことを、聖書は繰り返し命じています。
もちろん、罪の世ですから、完全ではなく、欠けはあるにしても、です。
というより、だからこそ、彼らのために祈り、とりなす必要があるのでしょう。
第一テモテ2:1-3, 新約p. 407
2:1 そこで、まず初めにこのことを勧めます。
すべての人のために、また王とすべての高い地位にある人たちのために願い、祈り、とりなし、感謝がささげられるようにしなさい。
2:2 それは、私たちが敬虔に、また、威厳をもって、平安で静かな一生を過ごすためです。
2:3 そうすることは、私たちの救い主である神の御前において良いことであり、喜ばれることなのです。
罪の世を治めるというのは、並大抵ではない苦労があると推察します。
複雑な現代社会は難題、難問山積で、一つかじ取りを間違うと、多くの人々の生活が影響を受けてしまいます。
その責任の重さはどれほどでしょう。
それでいて、彼らは良いことをやっても評価されることも少ないように思われます。
使命感をもって、この難しい重責を担って、遂行してくれている人々がいることを、神に感謝し、また彼らのために祈り、とりなすことを、パウロは勧めています。
それが、私たち自身が敬虔に、また威厳をもって、平安で静かな一生を送るのに有益であり、何よりもそれは神の御前に良いことであり、喜ばれることと言っています。
つまり、神への捧げものです。
もう一つ、今度は、当時の奴隷たちに向けたパウロの言葉を見ておきましょう。
彼は奴隷たちに、もし自由の身になれるなら、そうするように、ただそうできなくても、気にするな、と述べています(第一コリント7:21, 新約p. 326)。
そして奴隷の状態に留まらざるを得ない彼らに、パウロは次のように指導しました。
エペソ6:5-8,新約p. 380
6:5 奴隷たちよ。
あなたがたは、キリストに従うように、恐れおののいて真心から地上の主人に従いなさい。
6:6 人のごきげんとりのような、うわべだけの仕え方でなく、キリストのしもべとして、心から神のみこころを行い、
6:7 人にではなく、主に仕えるように、善意をもって仕えなさい。
6:8 良いことを行えば、奴隷であっても自由人であっても、それぞれその報いを主から受けることをあなたがたは知っています。
人に仕えているんだけれども、人に仕えているのではない。
人の奴隷ではなく、主に仕えている。
主が自分をそこにおいておられるから、上に置かれた者を尊び、自発的に善意をもって仕える。
それは「主キリストに仕えている」ことにほかなりません」
(コロサイ3:24, 新約pp. 393-394)。
ですから、そのような心構えで自分の役割を正しく果たすならば、奴隷であれ、自由人であれ、その報いは主から来ると言います。
ときには、自分にとって好ましくない状況もあるでしょう。
自由になれるのなら、遠慮なくそこから自由になればいいのですが、そうできないとき、事柄の背後に神の御手を見て、気持ちの整理をつける。
究極的には、問われているのは、神への信頼、また神の摂理に対する信頼ということなのでしょう。
なお、12節後半には、この戒めに従うとき、長寿の祝福が与えられるという約束が伴っています。
対人関係の戒めで約束が伴っているのは、この五戒だけです。
この戒めが特別であることがうかがわれます。
ウ大教理問答133によると、これは「この戒めを守る全ての人に対する、神の栄光とその人自身の福祉に役立つ限りでの長寿と繁栄の明白な約束」です。
例外もあるけれども、そのような祝福を期待できるということでしょうか。
<②下にある者を尊ぶ:神から与えられた責任として>
第五戒は、文字通りには、父と母を敬えということですが、子の側に一方的に要求するのでなく、本来、親は親としての責任を果たすことが前提とされています。
そして、どちらが先行するべきかと言えば、当然、親の方です。
その、本来神が望んでおられる親子関係の中で、子どもに基本的な信頼感が養われると、その後の人間関係も良好に築けると言います。
それは恵まれた人生を送ることの土台を提供することになるでしょう。
その親の側、また上の立場の人に求められていることについて、ウ大教理問答129から。
「…神から授かった権力と置かれている関係に応じて、下の人を愛し、祈り、祝福すること。彼らに教え、すすめ、戒めること。
良いことをした人には奨励と推奨と褒賞を与え、悪いことをした人には恥と叱責と懲戒を加えること。
彼らを保護し、その心と体に必要なすべてのものを支給すること。…」
続けて、ウ大教理問答130、上の人の罪について。
「…不正なことや、下の人の力ではできないことを命令すること。
悪いことを勧めたり、応援したり、賛成すること。
良いことをするのをやめさせたり、はばんだり、反対すること。
不当に矯正すること。
不注意に不正や誘惑や危難にあわせたり、捨て置くこと。
怒らせること。…」
最後の「怒らせること」とは、正当な怒りのことでしょう。
親や上の者が、不条理な扱いをしたり、果たすべき義務を果たさなかったりなどした場合。
それにしても、読んでて、これはシンドイな、と思います。
そもそも父親とは無理をしなければ勤まらない役目であり、父とはもともとシンドイものと知って、父親をしていくのだと、誰かが言っていましたが。
それは母親もそうでしょう。
そして、ほかの戒めもそうですが、正直、この通りには、できないこともたくさんあるでしょう。
そのためにもキリストが十字架にかかって下さったことをありがたく思い、自分のなし得なかった責任によって、あるいは自分がなしてしまった罪によって、子が被った被害を、神が憐れんで、カバーして下さるようにと、祈らされるのではないかと思います。
そして今、それぞれが与えられている責任も、神の御手によることだから、不信仰によって悲観したり、あきらめるのでなく、神に望みを置いて、神に信頼して、いい意味でお委ねして、精いっぱい、神のみこころを行わせて頂く者でありましょう。

<③例外もある:至高の権威者は神>
以上、神のゆえに権威を尊ぶという大原則を見てきましたが、最後に例外があることをおさえておきましょう。
上に立つ者が、神の律法に背くことを命じた場合です。
三浦綾子さんは、もし、夫が妻に、自分が泥棒する間、そこで見張っていろ、と命令されたら、夫に向かってそれは悪いことです、などと説教せずに、黙って従え、とどこかの牧師が説教したのを聞いたことがあると書いていました。
まあそれは、クリスチャンの奥さんが、夫に向かっていちいち偉そうに説教じみたことを言わないように、ということを、冗談めかして言っただけかもしれませんが。
しかしこれがたとえば、国家が神社参拝や人殺しを命じた場合、どうするのか。
当然、私たちは至高の権威者であられる神に従います。
世に置かれている権威を、神のゆえに尊びますが、それを絶対視したり、盲目的に従うのではないのです。
以前、1章で見たイスラエル人の助産婦たち。
イスラエルに生まれた男の子は、みなナイル川に投げ込め、とパロは命令しましたが、彼女たちはパロよりも神を恐れて、パロの命令に従わず、イスラエル人の子たちを生かしておきました。333333
古代、バビロンのネブカデネザル王は、金の像を作り、すべての人に、角笛や竪琴などもろもろの楽器の音を聞いたら、その像を拝めと命じ、拝まない者は誰でも、燃える火の炉に投げ込むと脅しました。
が、ユダヤ人のシャデラク、メシャク、アベデ・ネゴの三人はその命令に従わず、金の像を拝みませんでした。
彼らは燃える炉に投げ込まれましたが、主は彼らとともに炉の中におられ、彼らは守られました(ダニエル書3:16-18,旧約p.1453)。
第二次世界大戦中、ナチスがユダヤ人狩りをしていたときに、命がけでユダヤ人をかくまったドイツ人もいました。
彼らは時の権威の脅しに屈せず、至高の権威者である神の御心に従いました。
使徒パウロの言葉も聞いておきましょう。
ローマ8:38-39, 新約pp. 302-303
8:38 私はこう確信しています。
死も、いのちも、御使いも、権威ある者も、今あるものも、後に来るものも、力ある者も、
8:39 高さも、深さも、そのほかのどんな被造物も、私たちの主キリスト・イエスにある神の愛から、私たちを引き離すことはできません。
実際にそういう場面に遭遇するかどうかは別として、私たちもこれほどにイエス・キリストにある神の愛と固く結びあわされたいと願わされます。
|