<今日の要点>
主の御名が何よりも麗しく、尊く思われるほどに主を知り、主を愛せるように!
<はじめに:問われているのは心>
第三戒は、ご覧の通り、主の御名を唱えること、口にすることについての戒めです。
名前というのは、言うまでもなく大切なものです。
名前は、その人自身と密接に結びついています。
たとえば、私たちがどこかで自分の名前が人の口にのぼったのが耳に入ったら、そっちの方を向くか、少なくとも、意識はそっちの方に向くでしょう。
誰かと話してても、別な方からチラッとでも自分の名前が耳に入ると、気になるでしょう。
それと同じように、生きておられる神は、私たちが神のお名前を口にするたびに、(人間的な言い方をしますが)そっちのほうに特別に聞き耳を立てられるのかもしれません。
あるいは神は心の中までご存じですから、私たちが心の中で御名を口にしたときも、そちらに耳を澄まされるのかもしれません。
そんなことを思うと、デパートの大安売りのように、やたらとポンポン気安く神の御名を口にすることを慎まされます。
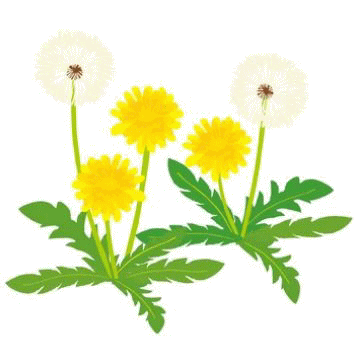
今日の学びに入る前に、一つだけ、心に留めておきたいことは、主の御名をみだりに唱えてはならないと言って、「こういう場合は御名を口にしてよくて、こういう場合はダメ」みたいな理解の仕方だけで終わるのは、避けたいということです。
学校の校則のように、それに引っかからないことだけに気持ちが行くと、窮屈になりますし、へたをすると、神の御名をお呼びすることが、何となくためらわれてしまうことになりかねません。
それはこの戒めの意図することではありません。
十戒を理解するにあたって、常に覚えるべき大原則は、イエス様が最も大切な戒めとしてあげられた二つの戒めです。
「心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。」と
「あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。」。
すべての律法や戒めは、この二つにかかっていると教えられました。
この第三戒も、問われているのは、主の御名をどう口にしたか、しなかったか、という表に現れた行動以前に、私たちの心そのものが、主に対してどうあるのか、ということなのだと思います。
心に満ちていることが口から出るのです、ともイエス様は仰いました(ルカ6:45、新約p. 121)。
私たちが主の御名をどう口にしているかというのは、私たちが主をどう思っているのかが、現れているのでしょう。
この戒めは細則のようなものではなく、律法全体の柱というべき十戒の第三戒として与えられていますから、これもまた私たちにとって大きな意義があるものなのでしょう。
今日も、天地の造り主に対して、すでに、まったくの一方的な、決して揺るぐことのない、永遠の恵みの関係に―愛されている子という関係に―入れられているという、その喜ばしい事実に立って、そのすでに受けている尊い救いを背景として、第三戒を見ていきます。
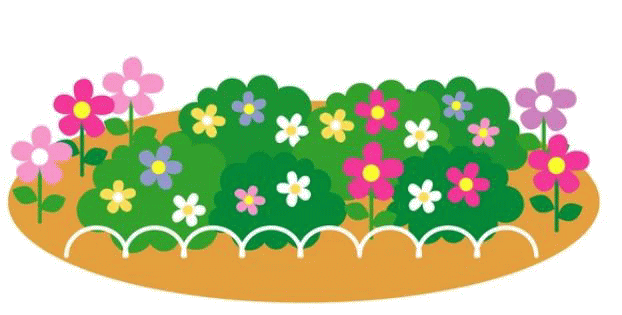
<①禁じられている罪:ふさわしくない思いで御名を口にすること>
「みだりに唱えてはならない」とは、御名をいっさい口にしないことではありません。
禁じられているのは、正しくない、またふさわしくない用い方です。
「みだりに」と訳されている句は、中身が伴わないで、ただ騒々しくとか、あるいは乱用するという意味だそうです。
神に対する敬いもなく、軽々しく御名を口にしたり、ましてや悪い意図をもって使うことです。
たとえば、自分の思い付きに過ぎないことや、自分の願望に過ぎないことを「これは神の御心だ」とか「神がこう言われた、示された」などというようなこと。
また冗談に神の御名を使うことも、はばかられます。
人間同士の間でも、愛する人、尊敬する人の名前を冗談なんかに使ってほしくないでしょう。
ましてや、私たちのために命まで捨てて下さったお方の御名を、です。
また悪い意図をもって使うとは、例えばペテロが、イエス様の十字架前夜、大祭司の庭で「イエスという男など、知らん!」と他人のふりをして、呪いをかけて誓ったことなどです(マルコ14:71、新約p. 100)。
彼は保身のために、うそを真実と偽って誓ってしまいました。
彼はその後、大泣きして己の卑怯さを嘆きました。
そして御名を汚さないということでは、旧約聖書に登場する義人ヨブを挙げなければいけません。
彼は、東の方で第一の富豪で、7人の息子と3人の娘がいましたが、なお奢ることなく、神を恐れる正しい人でした。
ところがある日、そんな彼を、それはひどい災いが襲いました。
彼はすべての財産と、そしてすべての子たちとを一日のうちに失いました。
そのとき、ヨブはよろよろと立ち上がって、言ったのでした。
ヨブ記1:21-22、旧約p. 850
1:21私は裸で母の胎から出て来た。
また、裸で私はかしこに帰ろう。
主は与え、主は取られる。
主の御名はほむべきかな。
1:22ヨブはこのようになっても罪を犯さず、神に愚痴をこぼさなかった。
21節は、ヨブの渾身の信仰告白。
やっと、やっとの思いで口にした賛美でしょう。
とても生身の人間の言葉とは思えない言葉です。
しかし22節を見ると、ヨブはこのとき「罪を犯さなかった」と記されています。
ということは、こんな状況であっても、神を呪ったり、神を非難することは、罪だということです(「愚痴をこぼす」新共同訳は「非難する」多くの英訳も同様)。
とはいえ、さすがにヨブも、心から主をほめたたえたとは思えないのですが、彼は、主の御名はほむべきかな、と主への賛美を絞り出すことによって、主の御名を汚す言葉が口をついて出て来るのを、必死にふさいだのかもしれません。
口は一つしかありませんから。
もちろん、つらい時、苦しい時に、神に訴えるのはよいのです。
ヨブもこの後、切々と神に苦しみを訴えます。
それはいいのです。
神は、私の訴えを聞いて下さる、受け止めて下さるということも、間違いなく神に対する信仰・信頼です。
そのような涙の祈り、嘆きの祈りも、聖書、特に旧約聖書の預言書、特にエレミヤ書には、多く見られます。
ただしヨブは、神の御名を呪うことは、最後までしませんでした。
その一線は守り通しました。
もう神もナントカもあるものか!と叩きつけなかった。
良心を投げ捨てなかったということでしょうか。
それは自分自身を守ることになります(第一テモテ1:19-20、新約p. 407)。
第三戒は、私たち自身の心を守るものでもあるのだと思います。
<②「罰せずには」:威嚇には、へりくだって、恐れる心を失わないように>
7節後半では、この戒めの違反に対して「主は御名をみだりに唱えるものを、罰せずにはおかない。」と威嚇されます。
もし、誰かが主の御名を悪用したときに、神がその都度、その場でその人を打ったとしたら、みんな恐れて、この戒めを守ろうとするかもしれません。
しかし実際は、人が神の御名を不正に悪用しても、神はその場でその人を打つことはないように見えます。
すると今度は、なんだ、大丈夫じゃないか、と神の言葉を侮る心が出てくるのが世の常です。だからこそ、でしょうか。
ウェストミンスター大教理問答114では、この箇所について、たとえ多くの人々が、そのときは非難や刑罰を免れようとも、神の正しい裁きを免れることは許されないと、解説しています。
聖書の威嚇に対しては、正しい心で恐れることが、正しい聖書の読み方です(ウェストミンスター信仰告白 14:2)。
聖書の著者は神ご自身ですから、著者であられる神にふさわしい尊敬を払い、へりくだって、聖書に向かいましょう。
第一サムエル 2:30、旧約p. 469
…わたしは、わたしを尊ぶ者を尊ぶ。
わたしをさげすむ者は軽んじられる。
<③命じられている義務:きよさと愛とが調和した、ふさわしい思いをもって>
前回の第二戒、偶像禁止令は、どんな形をもいっさい造ってはならない、と全面禁止でしたが、こちらはそうではなく、「みだりに」唱えてはならないです。
そのお心をたどっていくと、むしろ、御名をふさわしく用いなさい、というのが趣旨です。
ウェストミンスター大教理問答112には、この第三戒で求められていることは、「神の御名が、思いにおいても、言葉においても、きよい告白と責任のある行動とにより、神の栄光と、私たち自身や他の人々の福祉のために、きよく敬虔に用いられること」と解説されています。
「きよい告白」とは、偽りのない、全き良心をもって告白することでしょう。
「責任のある行動」は、主の御名によって誓約したことを、責任をもって果たすということでしょう。
そのことを、神御自身の栄光のためと、それから自分自身と他の人々の益となるために用いなさい、というのです。
たとえば、福音宣教において、私たちは主の御名を宣べ伝えます。
「世界中で、イエス・キリストの御名のほかには、私たちが救われるべき名としては、どのような名も人間に与えられていません。」
と使徒ぺテロが宣言した通り、主の御名は、私たちを永遠の滅びから救い、永遠の命を与える唯一無二の御名です。
それも、お金ではどれほど積んでも買えない、神の御前での罪の赦し、永遠のいのちを、私たちのために、ご自身が十字架にかかって、いのちを捨てて、買い取って下さったお方の御名です。
そのような尊い上にも尊い御名として、宣べ伝えます。
それから、私達は祈るときにもいつも「主の御名によって」祈ります。
これもただの祈りの終わりの合図ではなくて、私たち罪人の祈りも、主の御名によっていわば包むようにして、きよめて、御前にお捧げします、という意味です。
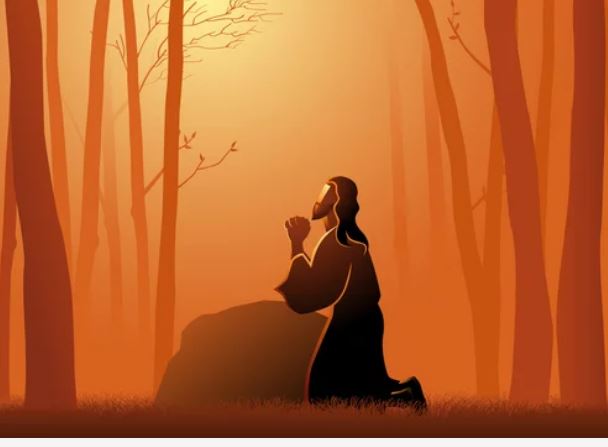
いわば、私たちの祈りをキリストの御名で封印したら、神はその封印の印―キリストの血潮で押されたキリストの御名の印―に目をとめて、そのゆえに、私たちの祈りをお受け下さるということでしょうか。
それから誓約も、主の御名を用いて、厳粛に行なわれます。
これは気まぐれな私たち人間が、神の御前で約束したことですから、責任を持って行動して、お互いの益となるように、ということでしょう。
そのような厳粛さ、聖さとともに、他方で覚えておきたいのは、イエス様は、祈りのときには「天の父よ」と呼びかけなさいと教えられたことです。
私たちに対して、恵み深く、憐れみ深く、慈しみ深く、赦しに富み、私たちを極みまで愛しておられて、心から信頼と愛と崇敬を寄せるべきお方として、お呼びしなさいと。
神の偉大さ、義と聖さと同時に、神の尽きない憐れみ、恵み、ご愛を覚える。
これは、御子イエス・キリストの十字架においてあらわされた、神ご自身のご性質でした。
神の義と愛が、どちらかを犠牲にするのでなく、どちらもが見事に調和して、麗しく輝いているのが、あの十字架です。
その麗しさ、みなさんの心の目にも見えるでしょうか?
「 イエス君の御名に まさる名はなし 」新聖歌 142番
主の祈りの第一の祈願は、「御名があがめられますように」です。
これは、新改訳2017では「御名が聖なるものとされますように」と訳されています。
神の御名を世から取り分けられた、特別な、神聖なものとするということです。
そのように主の御名を心から大切にして、汚すことのなかった一人の姉妹のお証。
戦時中、ある牧師の奥さんが、疎開先の福井で、3人の子供のうち1人をB29の落とした爆弾の破片をおなかに受けて失い、残り2人の子も、流行したチフスにかかって次々と失ったそうです。
そして看病にあたっていた奥さん自身もチフスにかかり、小学校の体育館の、もうダメだという組に置かれました。
まわりの人はみな、気が狂いながら、神を呪い、世を呪って死んでいきます。
しかしそこで名古屋から駆けつけてくれたO牧師婦人に、彼女は言いました。
「もし私が気が狂って、あの御方のお名前を呪うことがあったら、その時は、この防空頭巾を裂いて、私の口に詰めて下さいね。死んでも構いませんからね。
ただ、私があの尊いお名前を汚すことだけは、ないようにして下さい。」と。
まさしく女ヨブです。
同じようにできるか?と言われたら、正直、できないような気がします。
聖霊が臨んで下されば、そう導かれるでしょう、という他にありません。
ただ、主の御名をそのように神聖なものとして、決して汚さない、というその気持ちは、私たちも多少なりとも、持ち合わせていたいと願わされます。
主の御名はそうするに値する御名ですから。
私たちのために、十字架に至る苦しみ、ののしり、あざけりを忍んで下さったお方のご真実、ご愛を思って、何にもまさって心から御名を聖なるものとし、あがめる心を与えられますように、と祈らされます。
それが神の御心でもあります。
ピリピ2:9、新約p. 384
それゆえ神は、この方(キリスト)を高く上げて、すべての名にまさる名をお与えになりました。
|