<今日の要点>
私たちは思っている以上に罪深いが、神はすべてをお見通しの上で私たちを愛しておられる。
<はじめに>
神とイスラエルが契約を結ぶための備えの章、その続きです。前回、この契約がどんな祝福をもたらすかが語られましたが、今回はいよいよ契約を結ぶにあたって、主ご自身がシナイ山に降りてこられるので、民は身をきよめて備えるよう、求められます。
<あらすじ>
「今、もしあなたがたが、わたしの声に確かに聞き従い、わたしの契約を守るなら、そのときには、あなたはすべての国々の中で、わたしの宝となる。…」
モーセの顔は輝いたでしょうか。
エジプトの奴隷だったイスラエルの民が、世界に光を放つ神の宝になる!モーセは、かつて、自分は王室で何不自由なく、キンキラキンの生活をしていながら、同胞イスラエル人が奴隷として虐げられているのを見て、日々心を痛め、ついには見ていられなくなって、行動を起こした人です。
そのときは神の御心ではなく、自分の思いだけで行動したため失敗しましたが。
そんな心をもったモーセですから、この言葉を聞いて、さぞ喜んだことでしょう。
さっそく山を下り、長老たちを集めて主の言葉を伝えました。
それに対する彼らの応答は8節。
「すると民はみな口をそろえて答えた。
『私たちは【主】が仰せられたことを、みな行います。』…」
いいお返事です。
「あなたがたをわたしの宝とする」と神から言われたら、悪い気はしません。
多少誇らしげな気持ちで、優等生の返事をしたのかもしれません。
モーセも、よし!とうなずいて、民の返事を携えて山に登りました。
すると主は、気持ちはわかるが、モーセよ、喜ぶのはまだ早い、とでも仰るかのように、冷静に次なる一手を示されました。
民がちゃんとモーセを信頼できるよう、手を打つのです。
民の目には見えないように、濃い雲の中で、主はモーセに臨まれる。
しかし主が語られる声は民に聞こえるようにするので、それによって民が、確かに主がモーセに語っておられると、わかるようにする。
そうすれば、モーセが勝手に適当なことを言っているのでなく、ちゃんと神が語られたとわかるだろうと。
こういうことが必要だったのです。

モーセは、彼らの耳に心地よいことばかりでなく、耳の痛いことも告げなければならない。
その時、彼らはきっとモーセを疑う。
主はあなたに語られなかったと言い出す。
それに対して主は先手を打たれるのでした。
続けて主は、民に備えをさせるよう指示します。
三日目に主がシナイ山に降りてこられるので、そのときに備えて今日と翌日、彼らを聖別して、着物を洗わせよと。
もちろん実際は、着物だけでなく、からだもゴシゴシ洗っても、罪や汚れは取れません。
ただこうして、感覚的に、神が聖い方ということを教えるのでしょう。
そしてシナイ山の周囲に柵かロープか境を設けて、山に登ることはおろか、その境界に触れることすらないように注意せよ、と戒めます。
ただし、角笛が長く鳴り響くとき、モーセとアロンは(13節の「彼ら」はこの二人と思われます)今度は、境界線の中に入って山に登らなければならない、と言われます。
角笛は、重要な人物の到来、また重大な宣言の前に、それを告知するために吹き鳴らされるものです。
キリストの再臨のときにも、神のラッパが響き渡るとされています(第一テサロニケ4:16、新約p. 400)。
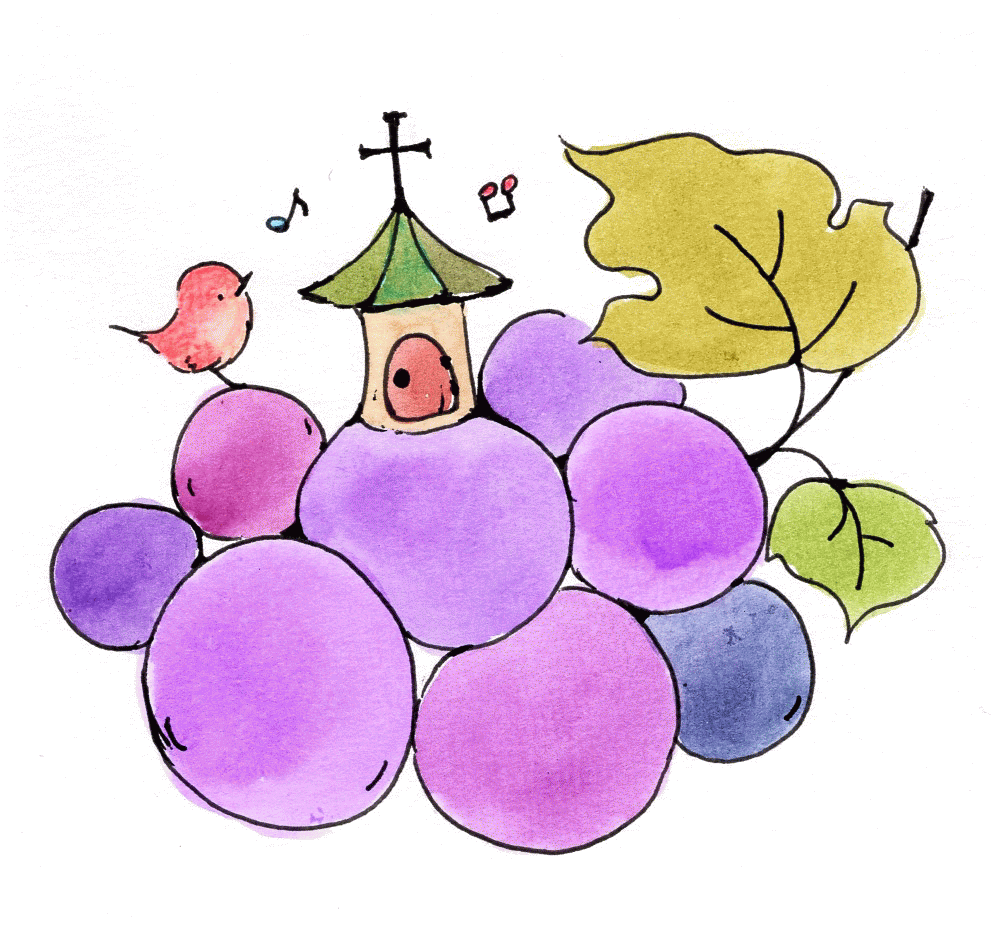
これらの言葉を主から受けて、モーセはまた山から降りて、その通りにしました。
何往復も大変です。
そしていよいよ三日目。
雷鳴がとどろき、稲妻が走り、濃い雲が山頂を覆います。
主の到来を告げる角笛が、高く鳴り響いて、宿営の中の民はみな、震えあがりました。
しかしモーセは、神を迎えるために民を宿営から連れ出し、山のふもとに立たせました。
シナイ山は全山が激しく震え、煙っていたと言います。
主が火の中にあって、山の上に降りてこられたからです。
この火は、さばきを象徴するのでしょうか(へブル書12:29、新約p. 442)。
もちろん、主が現れるときには、必ずこうというのではなく、たとえば創世記では、旅の途中、不安を覚えるヤコブに現れたときは、主は親しく隣に立たれました(創世記28:13)。
このときは、律法を守るという契約を結ぶにあたって、こうして主に対する恐れを抱かせる必要があったのでしょうか。
角笛はますます高くなりました。
主は山の頂に降りると、モーセを山頂に呼び寄せました。
モーセは、ひとり山頂に登って行って密雲の中に入っていきました。
こんな恐ろしい中、よくだな、と思います。
ここでいよいよ十戒の授与かと思ったら、まだその前にもう一度、民を戒める必要がありました。
21節の主の言葉。
「下って行って、民を戒めよ。
【主】を見ようと、彼らが押し破って来て、多くの者が滅びるといけない。」
最初は恐れてブルブル震えていた民も、少し時間が経って慣れたのか、またモーセが境界線の中に入っていったのを見たからか、自分たちも行ってみようと考え出す者がいたようです。
探求心がおおせいなのは、けっこうなことですが、あきらかな主の言葉に背くことは、決してしてはいけません。
大きな代償を払うことになります。
この主の言葉に対して、モーセは、ついさっき、民の良い返事を聞いたばかりですから、まさかと思ったのでしょう。

「大丈夫です。彼らは登ってきません。
あなたが私たちを戒めて、山の回りに境を設けさせ、そこを聖なる地とせよ、と仰いましたから。
そのことは彼らにちゃんと、教えてありますから。」と応じました。
モーセは、境を設け、ここから先に来てはいけない、と主がお命じになったと言えば、民はそのままいい子で言うことを守ると思っていたようです。しかし、それは甘かった。
主はモーセの楽観的な言葉にかまわず「降りていけ。」と命じました。
モーセは主の言葉に従い、山を降りて、彼らにくれぐれも、くれぐれも…と主の言葉を告げたのでした。
それにしても、です。
口をそろえて「はい、従います」と言った民が、三日後には化けの皮が剥がれたと言いますか。
ここから先は来るべからず、という簡単な戒めさえ、守ることができなかったとは…。
いろいろと考えさせられます。
内村鑑三は、これまでの主に対する不信を思えば、彼らの「みな行います」という返答は傲慢な態度であったとし、「私たちはあなたの仰せをみな、行いたく願いますが、私たちには到底、できません。
どうか、憐れんで下さり、助けて下さいますように。」と言うべきだった、とコメントしていました。
さて、今日の場面はご覧の通り、恐ろし気な光景でした。
雷がひらめき、稲光が走り、耳をつんざくような雷鳴がとどろき、シナイ山全山が煙り、鳴動して…。
ところで私たちも毎回、こんなふうに恐れながら、神に近づかなければいけないのでしょうか?礼拝の度に、神と自分たちとの間に境を設けて、死なないように気を付けなければいけないのでしょうか?もちろん、そうではありません。
と言っても、もちろん、神が聖くなくなったわけではありません。
キリストが、私たちの罪のための贖いとなって下さったからです。
キリストが十字架上で流された聖い血潮が、境を取り払い、大胆に神の御前に出ることができるようにしてくれたのです。
キリストによって、光景が一変したのです。
キリストの血潮には、すべてを一変させる力、価値があるのです。
ヘブル(12:18-22、新約pp. 441-442)は、この時のことを引き合いに出して、今私たちがあずかっている恵みの特権を宣言します。
12:18 あなたがたは、手でさわれる山、燃える火、黒雲、暗やみ、あらし、
12:19 ラッパの響き、ことばのとどろきに近づいているのではありません。
このとどろきは、これを聞いた者たちが、それ以上一言も加えてもらいたくないと願ったものです。
…
12:22 しかし、あなたがたは、シオンの山、生ける神の都、天にあるエルサレム、無数の御使いたちの大祝会に近づいているのです。
恐ろしいシナイ山ではなく、祝福に満ちたシオンの山、天のパーティに招かれているのです!ほかにも新約は全体的に、喜び、平安、感謝などの言葉が多くなって、旧約から光景が一変しています。
またヘブル4:16、新約p. 428
ですから、私たちは、あわれみを受け、また恵みをいただいて、おりにかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。
キリストが十字架にかかられたときに、神殿の幕が上から下に真っ二つに裂けました(マタイ27:51、新約p. 61)。
神と人との間を隔てる境を神自ら取り去って下さったのです。
それゆえ、私たちは、ただキリストのゆえに、聖なる神の前に大胆に出ることができるのです。
「 妙にも尊き 神の愛よ 底いも知られぬ 人の罪よ 」新聖歌 230番
この箇所全体を通して、モーセは民をある程度、信用していたというか、そこまで悪いとは思っていなかった節がありますが、神は最初から民の本当の姿を見抜いていたと思われます。
とすれば、です。
神はすべてお見通しの上で、彼らを「わたしの宝とする」と言っておられたのです。
人の罪の深さ―自分でも気づいていない罪の深さーを見通した上で…。
使徒ペテロに対するイエス様もそうでした。
十字架にかかられる前夜、ペテロは、たとえほかのみんながイエス様を知らないと言っても、自分は決してそんなことはしない、イエス様とご一緒に死ぬ覚悟はできています、と言いました。
そのときは、彼も、自分の言葉に嘘偽りはないと思っていたでしょう。
しかし結果は、ご存じのとおり。
一晩のうちに三度も、イエス様を知らないと誓いまでかけたのでした。
イエス様はそのことを前もって、告げておられました。
すべてお見通しでした。
そしてイエス様を裏切ってしまって、ひどく落ち込んでいたペテロを、イエス様は復活して後、責めるのでなく、かえって放っておいたら、自分などもう使徒と呼ばれる資格はない、と自分から身を引いてしまいそうなこともお見通しで、あたかも彼の首根っこをつかまえるかのように、ご自分のもとへ引き寄せて、変わらぬご愛を示されました。
すべてお見通しの上で、彼を弟子としておられたのです。
私たちも、本当は同じなのかもしれません。
私たちも、自分で思っている以上に罪深いものではないでしょうか。
詩篇の作者は祈りました。
詩篇19:12-13、旧約p. 922
19:12 だれが自分の数々のあやまちを悟ることができましょう。
どうか、隠れている私の罪をお赦しください。
19:13 あなたのしもべを傲慢の罪から守って下さい。
それらが私を支配しませんように。

自分には、隠れている罪があるかもしれない、と控えることは、先人の知恵ではないでしょうか。
自信満々で罪の道を突進、まい進して滅びに至ることは、しばしばあるように思われます。
聞く耳を持たず、自分を顧みることなく、相手が、周りが悪いと責めるばかりの傲慢さから守られるよう、祈らされます。
使徒パウロも、詩人と同じ姿勢を示していました。
第一コリント4:3-4、新約p. 321
4:3 …事実、私は自分で自分をさばくことさえしません。
4:4 私にはやましいことは少しもありませんが、だからといって、それで無罪とされるのではありません
。
私をさばく方は主です。
自分をさばくのは、自分ではなく主であられる、とわきまえることによって、傲慢の過ちから多少なりとも守られるのかもしれません。
そして最後に覚えたいのは、天の父なる神は、私たち以上に私たちのことをご存じで、何から何までお見通しで、その上で私たちをご自分のものとして召して下さったということです。
その上で、私たちを愛しておられるということです。
それゆえ、御子を救い主として下さったのです。
洗礼の時に神の御前に誓約します。
その時は心からそう思って誓っても、結果として守ることができないかもしれない。
神はそれもお見通しです。
神は、私たちが完全に誓いを守れるから、クリスチャンとして認めるのではありません。
自分は、自分が思っている以上に罪深いかもしれないけれども、それでも神はすべてをお見通しで、そんな者をもお救い下さるために尊い御子を、救い主として与えて下さった。
クリスチャンは、そう信じるのです。
誓いや戒めを完全に守れるのがクリスチャンなのではなく、神の御子キリストを救い主と信じる者がクリスチャンなのです。
だから私たちは、神の限りなく広く高く深いご愛を信頼して、御前に大胆に出ることができます。
このすべてをお見通しの上での救いの恵み、神の愛を改めて感謝をお捧げしたいと思います。
|