<今日の要点>
命令と教えを与えた方が、どういう方かを思い、信頼して、従う。
<あらすじ>
荒野で200万人以上のイスラエルの民のために、うずら料理とホットケーキをふるまわれた主なる神。
彼らは、主が用意した青空レストランで、舌鼓を打ったことでしょう。
天の父なる神の、彼らに対するご慈愛でした。
その後も、毎朝、神は天からのパンを備えました。
このパンはのちにマナと呼ばれます(31節)。
そのマナの取り扱いについて、神が定めた決まりが三つありました。
第一に、毎朝一人あたり一オメル(約2.2〜2.3リットル)、一日分だけ集めること(16節)。
第二に、集めたパンは翌朝まで取っておいてはならないこと(19節)。
一部の民は言うことを聞かず、翌日まで取っておきましたが、それには虫がわき、悪臭を放ちました。
そして第三は、六日目には七日目の分とあわせて二日分集める、ということでした(5節)。
今日はこの第三のルールについてのエピソードとなります。
人々は、言われた通り、六日目にはいつもの二倍、一人あたり二オメルずつ、集めました。多く集める分には、彼ら文句を言いません。
ただ前回、翌朝まで残しておいたものは、虫がわいたからでしょう。
念のため、民の代表たちはモーセに指示を仰ぎに来ました。
これは、取っておいても大丈夫なのか、腐らないのかと。
するとモーセは言いました。
23節「【主】の語られたことはこうです。
『あすは全き休みの日、【主】の聖なる安息である。
あなたがたは、焼きたいものは焼き、煮たいものは煮よ。
残ったものは、すべて朝まで保存するため、取っておけ。』」
臼で引いて、こねて、成形して、あとは焼いてよし、煮てよし。
六日目にそれを食べて、残ったものは、心配せずに翌朝まで取っておけ、と言います。
なぜそういうことをするかというと、七日目は全き休みの日、主の聖なる安息の日だから、外に出てマナを集めるという労働をしなくていいように、というのです。
主のご配慮の行き届いていること…。
のちに、シナイ山で与えられる十戒の中にも、安息日を覚えて、これを聖なる日とせよ、とありますが、安息日自体は十戒以前からあったようです。
この時から始まったのか、それとももっと前からそういう習慣があったのか(参考 創世記2:3)、わかりませんが。
ともかく、そんなわけで、安息日に食べるためにと、神がこの日には二日分与えられたのだから、心配しないで、翌日の分を取っておくようにということでした。
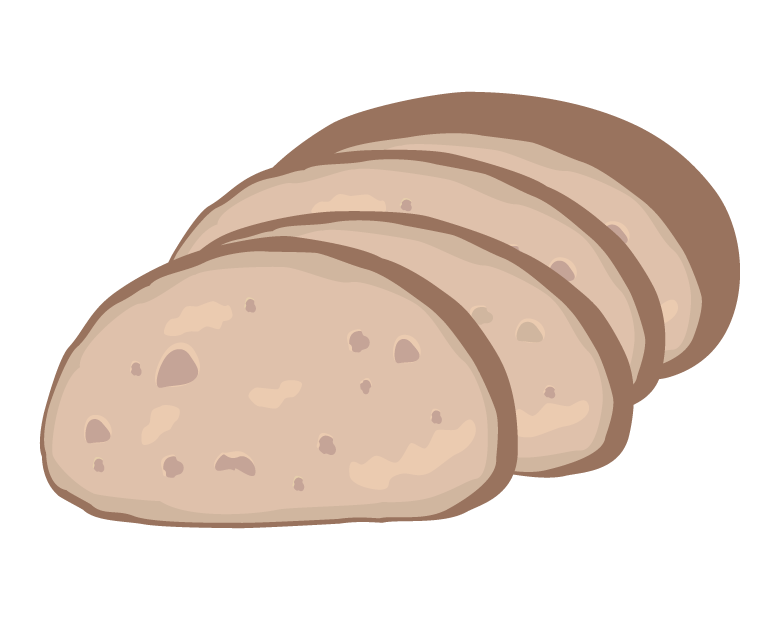
本当に大丈夫かなあ、と少し心配だったかもしれませんが、彼らは従いました。
24節「それで彼らはモーセの命じたとおりに、それを朝まで取っておいたが、それは臭くもならず、うじもわかなかった。」
今度は腐りませんでした。
不思議と言えば不思議、当然と言えば当然と言いますか。
普通は腐るのでしょうが、主の安息を守るために、主の言葉に従って残しておいたものだけは、奇跡的に腐らなかったのです。
目的が主の安息を守るという、主の戒めを守るためには、必要はすべて与えられるということでしょうか。
マタイ6:33、新約p.11。
だから、神の国とその義とをまず第一に求めなさい。
そうすれば、それに加えて、これらのものはすべて与えられます。
さて、七日目の朝、マナが腐らなかったのを見て、民も驚き、ホッとしたでしょう。
そこでモーセは言いました。
25-26節「…今日は、それを食べなさい。
今日は【主】の安息だから。
今日はそれを野で見つけることはできません。
六日の間はそれを集めることができます。
しかし安息の七日目には、それは、ありません。」
モーセは、今日はそれを野で見つけることはできないと言いました。
今日は取りに行くな、でなく、今日は行っても無駄、ないと。
それでも、いやいや、モーセはああ言っているが、もしかしたらあるかもしれない、と欲に駆られた者たちがいました。
27節。
「それなのに、民の中のある者は七日目に集めに出た。
しかし、何も見つからなかった。」
ここまで来ると、笑ってしまいますが…。
七日目に食べるものはあったはずですが、それでも集めに行くというのは、欲か。
それとも、やはり少しでも蓄えておきたいと思ったか。
天からのパンも不作の日が来ないとも限らない、と。
翌朝まで残すなと言われても、翌朝まで取っておく。
七日目は野に行ってもない、と言われても、出て行く。
どこまでも神の言葉に従わない民。
こんな民の姿を見て、神はどう思われたでしょう。
これまで彼らがエジプトにいたときから、彼らのために数々の大いなるみわざを行って見せて、彼らをエジプトの支配から救い出し、パロの軍勢が追撃してきたときにも、彼らを守ってパロの軍勢を海に投げ込んで見せた。
マラでは苦い水を甘く変えて彼らの渇きを癒し、つい数日前には、荒野でうずら料理とホットケーキをさえ、与えたのに。
それでもまだ、わたしのことを信頼しようとしないのか…。
神は悲しく思われたのではないでしょうか。
28節。
「そのとき、【主】はモーセに仰せられた。
『あなたがたは、いつまでわたしの命令とおしえを守ろうとしないのか。』」
主の嘆きです。期待するが故に、じれったくもなるのでしょう。
彼らが主に信頼して、従ってくれるようになることを、主は首を長くして待ち望んでいるかのようです。
新改訳は「守ろうとしないのか」と訳していますが、直訳は「守ることを拒む」で、しかも「拒む」は原語は強調形です。
他の訳は「拒む」という語を入れて訳しています。
守ろうとしているのに守れない、ではなく、そもそも守ることを拒んでいるということで、第三版は「守ろうとしない」と訳したのでしょうか。
はなから守る気がない。
主の命令を守るということが、始めから念頭にない。
それは、神の命令を守ることを拒んでいることです。
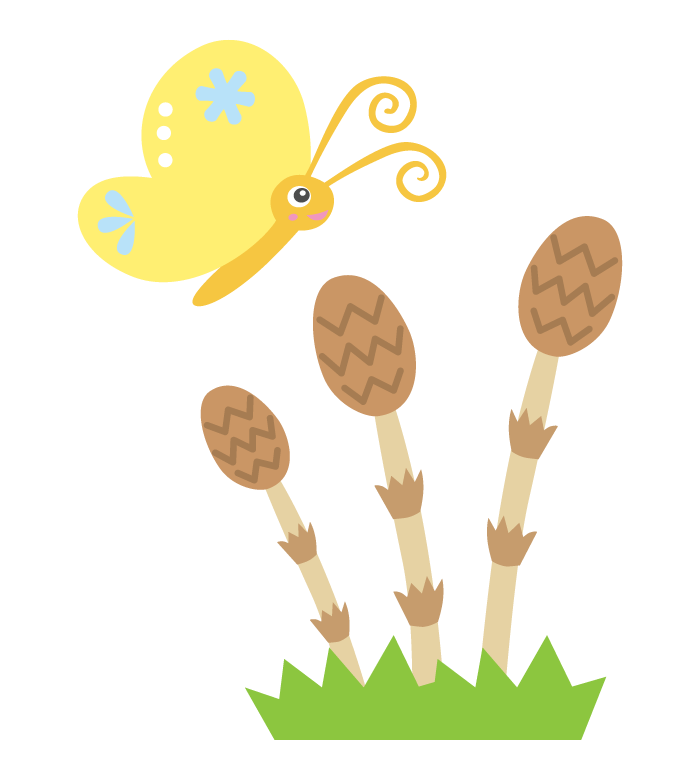
強い意志をもって拒否しているわけではなくても、神の命令を無視することも、実質的には守ることを拒んでいるのです。
神は、私たちが神の言葉を守ろうと意識していても、できないのに対しては、責めるよりもむしろ、励まし、応援して下さるのだと思います。
育てる者の目で、忍耐強く、寛容をもって見て下さっているでしょう。
しかしはなから神の命令を守るつもりがないなら、神は嘆かれ、時に責められもするでしょう。
悔い改めに導くために。
幸い、このときは、主は民をお裁きにならず、モーセを通して注意し、諭しただけでした。
29-30節「【主】があなたがたに安息を与えられたことに、心せよ。
それゆえ、六日目には、二日分のパンをあなたがたに与えている。
七日目には、あなたがたはそれぞれ自分の場所にとどまれ。
その所からだれも出てはならない。』
それで、民はようやく七日目に休んだ。」
私たちもこのような主のご忍耐を、どれほど頂いていることか、と思います。
おかげで、ようやく彼らは七日目ごとに労働を休むことを学びました。
この七日目の安息というライフスタイルが、彼らの霊肉の健康のために神が定めたリズムですし、のちには彼らが神の民であることのしるしともなるものでした(出エジプト31:13)。
「げに主は 依り頼みて 従う者を 恵みたまわん」新聖歌316番
イスラエルが約束の地に入る直前、モーセは彼らに言いました。
申命記8:3、旧約p.319
…主は、あなたを苦しめ、飢えさせて、あなたも知らず、あなたの先祖たちも知らなかったマナを食べさせられた。
それは、人はパンだけで生きるのではない、人は【主】の口から出るすべてのもので生きる、ということを、あなたにわからせるためであった。
この16章では、人間が生きるのに必要な「食べる」ということにおいても、主の言葉に従って食べることを訓練されました。
食欲という、生存本能の最も強く現れる所においてであっても、神の言葉などお構いなしで、ただ目の前にあるパンを本能や欲の赴くままに食べるのでなく。
それでは動物と同じ。
そこには神のかたちに造られた人間の尊厳はありません。
人は、神の言葉を聞き、従うことにおいて、神の栄光を現す存在です。
食べるにも、何をするにも、神の言葉に従って、適切にコントロールすることが、人間本来のあり方です。
イエス様が、荒野で40日の断食をした後に、サタンが近づいてきて、「あなたが神の子なら、その石をパンに変えてみなさい」とそそのかしたとき、イエス様はこの御言葉を引用されました(マタイ4:4、新約p.5)。
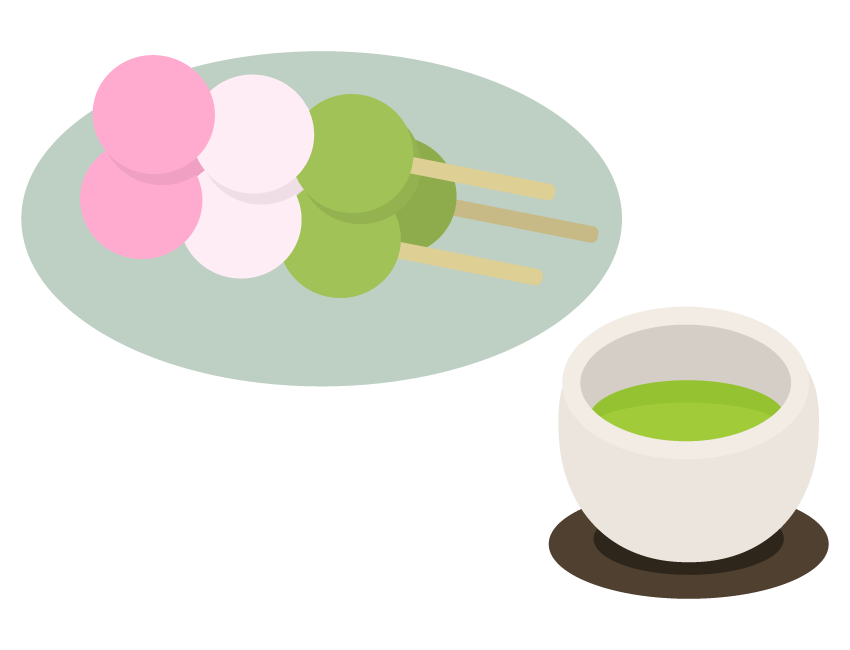
またそのようにすることが、人間自身の幸せにもなるのです。
本能や欲を否定しているのではありません。
ただ神の言葉に従って、適切にコントロールするということです。
食欲は罪ではありませんが、神の戒めに背いて、禁断の木から取って食べたエバは、罪を犯しました。
夫婦は神の定めですが、姦淫は罪です。
人を不幸にします。
神が創造された世界は、神の言葉に従って用いてこそ、祝福となるのです。
神は私たちを、祝福にあずからせたいと願っておられます。
神は、私たちを祝福し、喜ばせるために、世界を造られたのですから。
そのために、神の言葉に従うことを訓練されるのです。
主は、私たちを幸せにするために戒め、教えを与えています。
申命記5:29, 旧約pp.314-315。
イスラエルの指導者たちが、主を恐れて、主の語られることをみな、聞いて行います、とモーセに言ったところで、主は次のように語られました。
どうか、彼らの心がこのようであって、いつまでも、わたしを恐れ、わたしのすべての命令を守るように。
そうして、彼らも、その子孫も、永久にしあわせになるように。
民の幸せを祈るような気持ちで願われる神です。
申命記には同じような表現がたくさんあります。
できれば、開いて確かめて頂ければ。
4:40, 5:16, 5:33, 6:3, 6:18, 6:24, 8:16, 10:13, 12:28, 12:25, 22:7。
これらの個所を読むと、神の命令は重荷ではなくて、私たちを幸せにするために与えられていることがわかって、神の命令に対する印象が変わるかもしれません。
主の戒めが自分にとって良いもの、幸せにするものであって、慕わしいものであることを、ダビデはよく知っていたのでしょう。
彼はそれらが、自分にとって金よりも好ましく、蜜よりも甘いと歌い、それを守ると報いは大きいと言いました。
詩篇19:10-11、旧約p.922
19:10 それらは、金よりも、多くの純金よりも好ましい。
蜜よりも、蜜蜂の巣のしたたりよりも甘い。
19:11 また、それによって、あなたのしもべは戒めを受ける。
それを守れば、報いは大きい。
主の戒めを守らないのは、もったいないことだったのです! たとえば、主は赦しなさい、握りしめているものを手放しなさい、と命じている。
しかし、いやです、私は絶対、手放しません、と握りしめる。
これは、七日目に集めるなと言われても、いやだ、俺は集めに行く、と出て行ったのと同じです。
主の言葉を守りたいと願うなら、簡単には手放せなくても、手放せるようにと祈るべきです。
それは、赦せない苦しみから解放するため、また憎しみや怒りから、道を誤ることのないためです。
この主の命令に思い切って従った人は、主がこう命じて下さったことが、どれほど、ありがたいことだったか、わかると思います。
それが、主の口から出る言葉によって生きるとは、どういうことなのか、体験することです。
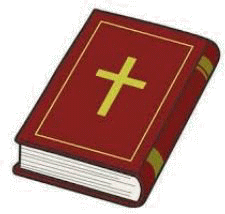
そして最後に覚えたいのは、聖書の命令、教えは、どなたの命令、教えなのか、ということです。
ここを良く考えないといけません。
主は、イスラエルの民に「あなたがたは、いつまでわたしの命令とおしえを守ろうとしないのか。」
と言われました。
そうです。彼らはどなたの命令を拒んでいたのか。パロの命令ではありません。
主なる神の命令です。彼らはこれまで、神の彼らに対する並々ならぬ恵み、特別扱いをたくさん体験してきました。
これまで彼らのために、至れり尽くせりで、大いなるみわざをして下さった方の命令また教えなのです。
この後、与えられる十戒にしろ、そのほかの命令にしろ、教えにしろ、それらはすべて、彼らが体験した神の救いということを背景として、受け取るべきものです。
そこから切り離されると、神の命令や教えの本質を見誤ってしまいます。
キリストを信じる私たちはなおさらです。
聖書の命令、教えは、どなたのものなのか。
ここを良く考えないといけません。
私たちを愛して、私たちのために御子をさえお与え下さった方の言葉。
それは、神が私たちを愛して、私たちの益となるように、私たちが幸せを得るようにーこの世だけでなく、永遠の御国において幸いを得るようにー願って、与えておられるもの。
私たちにとって良いもの、祝福を与えるものです。
今、皆さんに語られている主の命令、あるいは教えは何か、あるでしょうか。
それがなんであれ、主が語っておられることの背後には、御子を与えて下さったほどのご愛があることを心に刻みましょう。
また、ダビデのように主の言葉を慕い求めて、信頼して、行う者でありたいと願わされます。
この一週間が、私たちが御言葉を行うことによって、祝福に満ちたものとなりますように!
|