<今日の要点>
昔も今も、どの民族でも、神はすべての人に、ただご自身を信じることを求めている。
<あらすじ>
ついにイスラエルの民は、エジプトの地を出発しました。
奴隷として苦役に服していたエジプトから、主なる神が力強い御手をもってエジプトをさばき、彼らを解放しました。
誰もが信じられなかった、ありえない奇跡でした。
しかし神に不可能なことは、一つもありませんでした。
神は、どんなに強い闇の支配からでも、ご自身の民を救い出されるのです。
そして、出エジプトが主のみわざであることを、子々孫々に至るまで覚えるために、主は「過越の祭り」を定めたことを以前、見ました。
今日の個所は、その過越の祭りに関する補足になります。
38節に、多くの入り混じってきた外国人とありました。
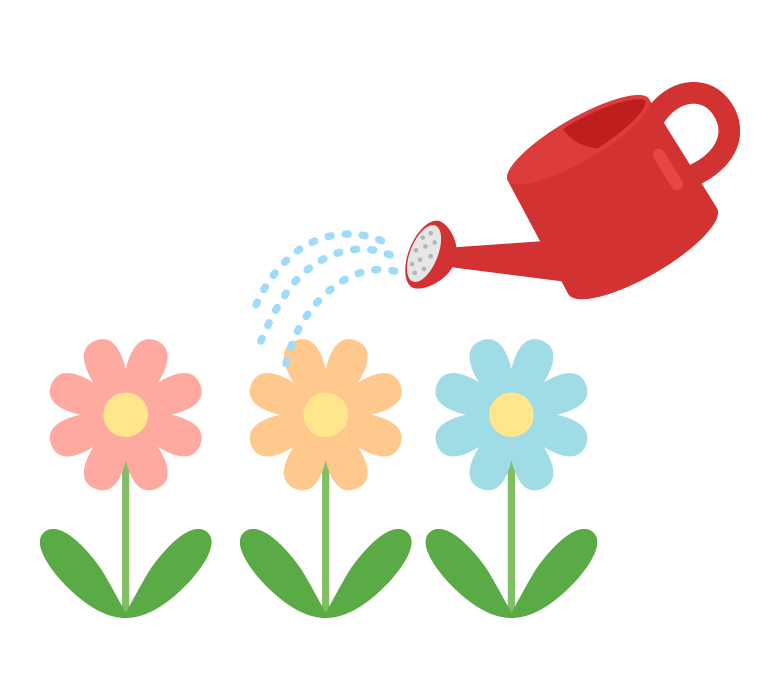
エジプトの地でなされた主の大いなるみわざを体験して、主のもとに身を寄せ、ついて行きたいとエジプトを後にした人たちがいたのでしょう。
その信仰も大したものです。
イスラエル人を解放したら災いも収まるのだから、住み慣れたエジプトにとどまるという選択肢もあったでしょう。
しかし、主についていきたいと、エジプトの地を後にした外国人たち。
そんな彼らが、大切な過越の祭りに参加できるのか、どうか。
主は彼らのためにハッキリと御心を示しました。
ここに一つの大切な原則があります。
神礼拝に関しては、神に聞かなければいけないということです。
ほかのことならいざ知らず、神礼拝に関しては、ただ在留異国人を除外するのは、かわいそうだから、いっしょに…と勝手に決めるわけにはいかないのです。
ウェストミンスター大教理問答109では、「第二戒で禁じられている罪」として、「神ご自身によって定められたのではない、どんな宗教的礼拝でも」考え出すこと、また「すべて、神が定められた礼拝と規定への無視、軽蔑…」が挙げられています。
つまり御言葉の原則を無視して、勝手に自分たちに良いと思うままに決めることではないということです。
それで、毎月行っている聖餐式も、求道者の方々があずかれないのは心苦しいのですが、これは私たちが勝手に、聖餐式にあずかる範囲を広げることはできないことで、聖書全体を調べて、神がそのように定めておられると、長老教会では理解しているので、そのようにしています。
そういうわけで、過越の祭りに関する主からのご指示が43節以下、記されます。
まず大前提としては、外国人は食べることができない。
ただし、お金で買われた奴隷については、割礼(主の民であることのしるし)を施せば、過越の食事を食べることができるとされました(44節)。
当時は、お金で買われた奴隷は、主人の家に属する者とされていたので、息子たちに割礼を施すように、奴隷にも割礼を施したら、その奴隷は過越の祭りにあずかることができる。
割礼を受けた者は、宗教的には主人の家族と同等の権利を認められるのです。
「居留者、(外国人の)雇い人」は、食べてはならないとありますが(45節)、48節には、在留異国人も割礼を受けたら、食べることができるとありますから、彼らも割礼を受けないままでは、食べることができないという意味と思われます。
つまり、ただイスラエル人の間に一緒に住んでいるからと、人間的なつながりだけで、割礼を受けることがないまま、ナアナアで過越の食事をすることを戒めているのでしょう。
また、それは家の中で食べなければなりませんでした(46節)。
外でバーベキューというわけにはいかない。
出エジプトの夜、イスラエル人たちが家の中で息をひそめていたことを思うためでしょうか。
ところでここに「その骨を折ってはならない」とあります。
他のいけにえの場合、足は全部切り取りますが、過越の子羊の骨は、折ってはなりませんでした。
使徒ヨハネはこれを、イエス・キリストにおいて成就したことの一つとしています。
ヨハネ19:32-33,36、新約p.222。
(詩篇34:20、旧約p.936も参照)
19:32 それで、兵士たちが来て、イエスといっしょに十字架につけられた第一の者と、もうひとりの者とのすねを折った。
19:33 しかし、イエスのところに来ると、イエスがすでに死んでおられるのを認めたので、そのすねを折らなかった。
…
19:36 この事が起こったのは、「彼の骨は一つも砕かれない」という聖書のことばが成就するためであった。
こんなところにも、キリストの十字架が示されていたのでした。
47節には、「イスラエルの全会衆はこれを行わなければならない。」
と念を押されます。
ともすると、在留異国人は弱い立場で、不当な扱いを受けがちです。
主は、そんな彼らの宗教的権利、また主を礼拝する心を、断じて妨害してはならないと、彼らのために「イスラエルの全会衆」に命じるのです。
そして48節に在留異国人の過越の祭りに関する原則が記されます。
まず「【主】に過越のいけにえをささげようとするなら、」つまり、強制ではありません。
もし在留異国人で、自分も主を礼拝したい、主の民の恵みにあずかりたいという、自発的な意志をもって、過越のいけにえをささげようとするなら、です。
その場合は、まず信仰の表明として割礼を受けなければならない。
そうすればその在留異国人も、主の御前に近づいてささげることができる。
「彼はこの国に生まれた者と同じになる」というのです!割礼を受けた者は、過越の祭りに関してイスラエル人と同等の権利を持つ。
そこには何の差別も隔てもない。
これが、神の御心です。
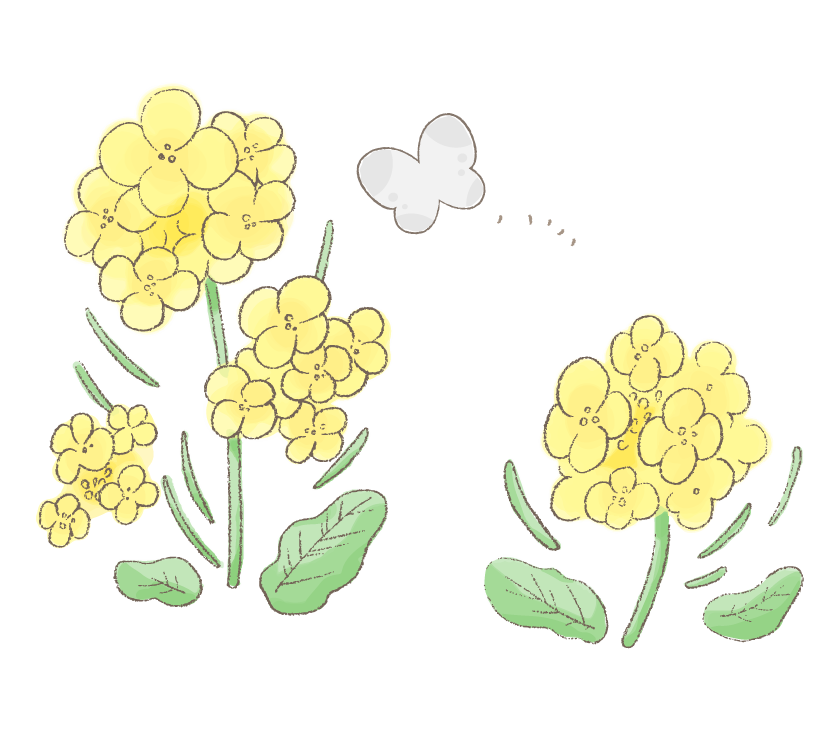
そして、割礼を受けない者はあずかることができない、と明確に一線を引き、この教えは、イスラエル人にも在留異国人にも同じであると宣言されました(49節)。
信仰の表明である割礼を受けているなら、過越の食事ができる。
受けていないなら、できない。
イスラエル人だからと言って、割礼なしに過越の食事はできないし、在留異国人だからと言って、割礼を受けたのに過越の食事を禁じることはできない。
イスラエル人にも在留異国人にも同じ。
そこには差別も特別扱いもありません。
イスラエル人は、主が命じられたとおりに行いました (50節)。
こうしてイスラエルがエジプトに滞在して430年経ったちょうどその日(41節、51節)、目に見えないお方が、男だけで60万人というイスラエルを集団ごとに整然と、エジプトから連れ出されたのでした。
「主と主の言葉に 頼るは楽し」新聖歌 324番
旧約の時代は、イスラエルが選びの民と言われます。
確かにそうなのですが、ただイスラエル人だから救われるのでなく、よく見るとやはり根底にあるのは、信仰による救いの原理です。
信仰によって救われる(=神に受け入れられる)ということは、旧約も新約も変わない、聖書の一貫した教えです。
旧約の時代にも、信仰を持つ異邦人たちは、同じように神の恵みにあずかっています
(ラハブ、ルツ、ナアマン等)。
新約の時代の今は、キリストへの信仰が求められています。
ローマ3:21-25、新約p.293
3:21 しかし、今は、律法とは別に、しかも律法と預言者によってあかしされて、神の義が示されました。
(神の義=神が与えて下さる義。これがないと神に受け入れられない。)
3:22 すなわち、イエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、それはすべての信じる人に与えられ、何の差別もありません。
(神の義は、律法を行うことによってでなく、キリストを信じることによって与えられる)
3:23 すべての人は、罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず、
3:24 ただ、神の恵みにより、キリスト・イエスによる贖いのゆえに、価なしに義と認められるのです。
3:25 神は、キリスト・イエスを、その血による、また信仰による、なだめの供え物として、公にお示しになりました。…
過越の子羊のように、十字架で血を流されたキリストを、私たちの罪のために神が与えて下さった救い主と信じるなら、誰でも神に受け入れられるのです。
滅びから免れ、永遠のいのちを与えられ、永遠の御国を受け継がせて頂けるのです。
本当にありがたいことです。
しかし、ただキリストを信じれば、罪赦されて、救われる、とそれを信じるだけにとどまっているとしたら、自己中心かもしれません。
そこからさらに進んで、キリストを与えて下さった神のお心を思う者でありたいものです。
神がどういう思いで、御子を下さったか。
御子を下さったその神のお心を、私たちが悟ることを、神は喜ばれるのです。やっとわかってくれたか、と。
老ヨハネは、諭すように言いました。
第一ヨハネ4:9、新約p.469
神はそのひとり子を世に遣わし、その方によって私たちに、いのちを得させてくださいました。
ここに、神の愛が私たちに示されたのです。
キリストの十字架において、救いの道が示されただけでなく、神の愛が示されたのです。
御子を下さった神のお心に思いを向けて、神がどれほど、私たちを愛して下さっているかを悟る。
そのときに、はるか昔、サタンの欺きによって、人類の祖アダムが失ってしまった、神を信頼する心が回復するのではないでしょうか。
そして神と人との心と心が、再び結び合うのではないでしょうか。
神が私たちに求めているのは、その神のご愛を悟ること、もう一度、神を信頼し直すことだと思います。
神は、やり直しのチャンスを与えているのです。
私たちが試練に会ったとき、勝利とはなんでしょうか。
それはその試練をうまくやり過ごす、解決する、困難がなくなるということでは、必ずしもないと思います。
もし勝利がそのようなものなら、十字架にかけられたキリストは、大敗北したことになるでしょう。しかし、そうではない。
試練における勝利とは、信仰の勝利のこと。
神の愛、真実を信頼し通すこと。
神を信頼し通すことが、勝利なのだと思います。
その信仰の勝利に対して、神は大いに報いて下さるのでしょう。
キリストを栄光のうちに復活させ、ご自身の右の座に着かせたように。
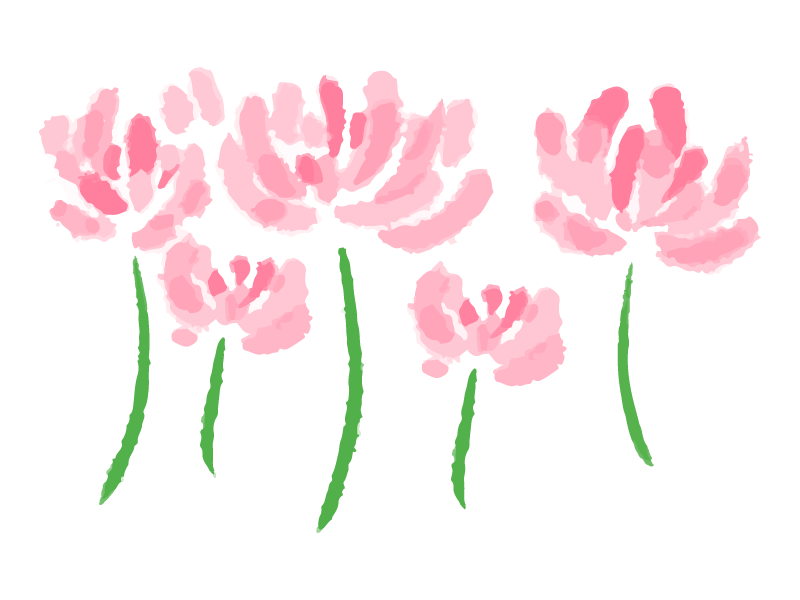
先に信仰の勝利、霊的な勝利があって、後から現実の変化がついてくる、ということは、しばしばあるように思います。
また、気持ちの上で負けてしまったら、勝てるものも勝てない、乗り越えられるものも乗り換えられない、ということもあるでしょう。
世の中には、私たちに理解できないことが、いくらでもあります。
それらを指さして、神がいるならどうして…、とそっちの方向に向かうのは、サタンの思うつぼです。
指さす所が違います。
十字架にかけられたキリストを指さすのです。
そこに神の真実は、ハッキリと証明されたのです。
人生には、わからないことがあります。
しかし、わからないことをもって、ハッキリとわかっていることを否定するのは、論理的ではありません。
ハッキリと証明されたことをもって、わからないことを推論するべきです。
ハッキリわかっていることは、神が真実であり、私たちを愛しておられることです。
最愛の御子をお与え下さったほどに。
その神は、すべてのことを支配しておられます。
だから今は理解できなくても、キリストを下さった神を信じる。
その神への信頼が、試練の中を支える力となるのではないでしょうか。
世に悲惨があるゆえに、キリストの十字架があるにもかかわらず、神を呪うのか。
それとも、世に悲惨があるにもかかわらず、キリストの十字架があるゆえに、神を信頼するのか。
つまるところ、御子の十字架の犠牲をどう見積もるか、です。
安く見積もるなら、キリストの十字架なんか…となるでしょう。
しかし御子は、全宇宙よりも、神にとって尊いお方です。
御子より尊いものは、天にも地にもありません。
その御子を神は下さったのです。
試練に会うとき、私たちの信仰、神への信頼は、揺らぎます。
揺すぶられます。
どうしてこんなことが…と思わず口から出ることもあります。
そんなときは、十字架にかかって下さった御子に目を留めるのです。
私たちを救うために、喜んで十字架にまでかかって下さった御子、またその御子をお遣わし下さった御父の愛と真実は、いかなる疑いも入り込むすきのないほど、ハッキリと表わされています。
へブル書12:2、新約p.440
信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。
イエスは、ご自分の前に置かれた喜びのゆえに、はずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。
聖霊に助けて頂いて、心の目でイエス様をしっかりと見つめて目を離さず、神を信頼して歩みましょう。
神はそれを喜んで下さいます。
その報いは計り知れません。
|