<今日の要点>
主が私たちのためにして下さったことを覚えて、応答する。
<あらすじ>
いよいよ、そのときが来ました。
モーセを通して語られた主のことばどおり、イスラエルの民は傷のない一歳の子羊をほふり、その血を門のまわりに塗って、家の中から一歩も外に出ずに、息をひそめていました。
すると、その日の真夜中です。
突然、エジプト中に叫び声が響き渡りました。
29-30節「真夜中になって、【主】はエジプトの地のすべての初子を、王座に着くパロの初子から、地下牢にいる捕虜の初子に至るまで、また、すべての家畜の初子をも打たれた。
それで、その夜、パロやその家臣および全エジプトが起き上がった。
そして、エジプトには激しい泣き叫びが起こった。
それは死人のない家がなかったからである。」
あらかじめ、モーセがパロに宣告しておいたとおりになりました。
主のことばは、実現するのです。
あらかじめ宣告されていましたから、護衛を最大限にしていたであろうパロの初子も、また看守がついて、地下牢の中にいて、ある意味外敵から守られていた捕虜の初子も、逃れることはできませんでした。
ここには主のさばきは、身分の上下にかかわらず、すべての人に臨むこと、それに、どんなに人間的な守りを固めても、防ぐことはできない、確実に遂行されることが示されています。
どんなに頑丈な核シェルターも、無意味です。
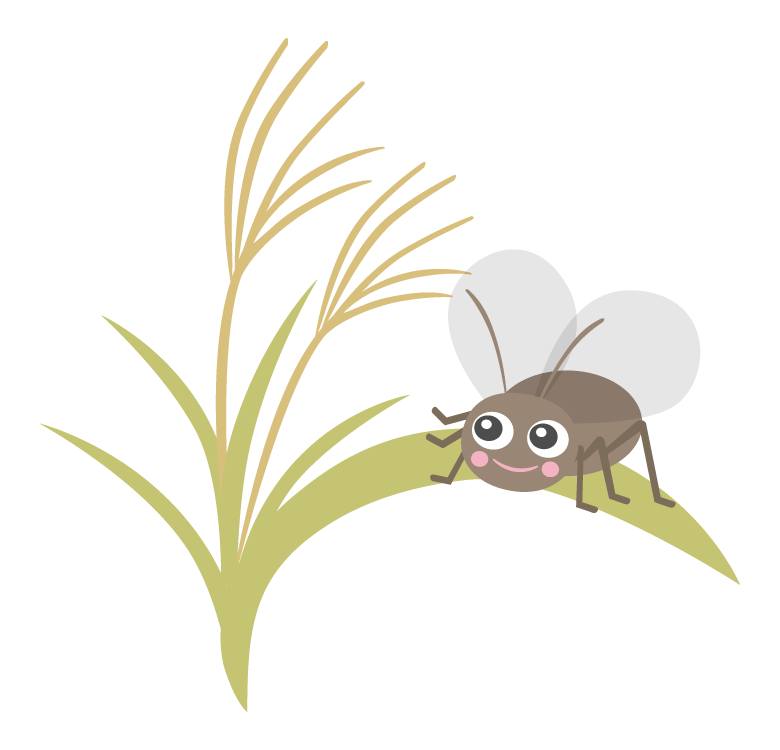
また、弱者を虐げるこの世の権威者も、主の前にはさばかれるべき一個の人間です。主は忖度されません。
また捕虜もです。
虐げられている側だから罪がないわけではありません。
人はみな、それぞれの行いに応じて、ふさわしいさばきを受けるのです。
他方、虐げる側に対するさばきは、それに苦しめられてきた側にとっては救いです。
パロはただちに、夜が明けるのも待たずに、モーセたちを呼び寄せました。
31-32節。
「パロはその夜、モーセとアロンを呼び寄せて言った。
『おまえたちもイスラエル人も立ち上がって、私の民の中から出て行け。
おまえたちが言うとおりに、行って、【主】に仕えよ。
おまえたちの言うとおりに、羊の群れも牛の群れも連れて出て行け。
そして私のためにも祝福を祈れ。』」
これまでパロは、災いに会うたびに少しずつ譲歩しながらも、モーセの要求を全面的に受け入れることを拒否してきました。
例えば、イスラエル人が犠牲を捧げることは許すが、国内で行えとか(8:21)、次は、男しか行ってはいけないとか(10:11)、その次は、行ってもいいが家畜は置いていけとか(10:24)言っていました。
全面的にモーセの言いなりになるというのは、パロとしてのメンツ、意地があって、許せなかったのでしょうか。
しかし、ここに至って、ようやく全面降伏しました。
させられました。
「前たちの言うとおりに」と繰り返しています。
悔しさと嘆きと痛みとともに、叫ぶように言ったのでしょうか。
かくして、あれほどイスラエルを行かせることを、頑強に拒んでいたパロが、ついに100%モーセの言い分とおり、出ていかせることになりました。
主のことばは、実現するのです。
さらには、かつて「主とは何者か。
私が言うことを聞かなければならないとは。」
と言っていたパロは、今や「私のために祝福を祈れ」と主の祝福を乞うことになりました。
完全なる主の勝利です。
さてさて、私たちの心にも、いろいろ条件を付けて、主に全面降伏するのを渋っている、内なるパロはいないでしょうか。
内なるパロが、むだな抵抗をやめて、条件を付けずに、100%主に明け渡すときに、私たちの内なるイスラエルが解放されるのでしょう。
こうして、以下、次々とあらかじめ主が語っておられたとおりに事が運びます。
エジプトは強制的にイスラエルを追い出しました。
これも主のことばのとおりです(6:1)。
イスラエルの民は、翌日のためにこねてあったのでしょうか、パン種を入れないままの練り粉を取り、こね鉢を着物に包んで肩にかつぎました。
当時のこね鉢は、木、金属、または陶器でできていたようです。
また、彼らは、主が語っておられたとおりに、エジプト人から銀の飾り、金の飾り、それに着物を求めました。

これは、長い間の苦役に対する報酬であると同時に、のちに、幕屋建設の材料となることは、前にも言ったとおりです。
そして求められたエジプト人の側も、不思議なことにと言いますか、神がそのようにされたのですが、イスラエル人の求めに嫌がる様子もなく、好意的に差し出してくれたのでした。
36節に「はぎとった」とありますが、力づくでむりやり奪い取ったのではありません。
こうしてイスラエルは、ついにエジプトの地を後にします。
37-38節「イスラエル人はラメセスから、スコテに向かって旅立った。
幼子を除いて、徒歩の壮年の男子は約六十万人。
さらに、多くの入り混じって来た外国人と、羊や牛などの非常に多くの家畜も、彼らとともに上った。」
最初は緊張した面持ちで家を出たイスラエル人も、離れるにつれて、次第に緊張も解け、解放された喜びが湧いてきたでしょうか。
東の空も白んできます。
彼らは、エジプトの奴隷生活と決別して、主に仕える生活へと踏み出しました。
イスラエル人居住区だったラメセスから、彼らはまず、スコテへ向かいました。
このスコテは、以前、創世記で出てきたカナンの地にあったスコテとは別で、彼らがいたラメセスから東南の方向にあるエジプトの町のようです。
60万という数字については、諸説ありますが、とりあえずこのまま読み進めます。
彼らの先祖ヤコブ一族がエジプトに下ったときは70人でしたから(創世記46:27、旧約p.87)、ものすごい数に増えたことになります。
40節には、イスラエルがエジプトに滞在した期間は430年だったとあります。
かつてアブラハムには400年と言われていましたが(創世記15:13-14、旧約p.21)、概数だったのでしょう。
430年が終わった、ちょうどその日に、主の全集団はエジプトの国を出ました。
その夜、主が夜通し、彼らのために番をされたと言います。
42節。「この夜、【主】は彼らをエジプトの国から連れ出すために、寝ずの番をされた。この夜こそ、イスラエル人はすべて、代々にわたり、【主】のために寝ずの番をするのである。」
主のために寝ずの番をするとは、徹夜で主を礼拝するという意味でしょうか。
主がイスラエルのために寝ずの番をするとは、主が彼らを守っておられたということでしょう。一人の人が救われる時にも、様々な妨げが入るものです。
サタンの妨害というものは、あります。
430年もの間、滞在したエジプトの地から、いよいよイスラエルの民が出発するという、この歴史的な転換点となるとき、主は特別なご臨在をもって、目に見えない敵からイスラエルの民を守っておられたのでしょう。
もっとも、この時は、特別な意味でこう記されているのでしょうが、主は常にまどろむことなく、私たちを守って下さっています。
有名な詩篇121:3-4、旧約p.1036
121:3 主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方は、まどろむこともない。
121:4 見よ。
イスラエルを守る方は、まどろむこともなく、眠ることもない。
私たちが、いびきをかいて寝ている間も、主はまどろむことなく見守っていて下さいます。
主が守って下さっていることを覚えて、主にゆだねて、安心して眠りにつきたいものです。
「主は命を与えませり。…われ何をなして 主に報いし」新聖歌 102番
今日は42節に注目したいと思います。
ある人はこの箇所で次のようにコメントしています。
「ここに聖書の宗教の基本形がある。
聖書の宗教は、神のみわざが最初に存在する。
神がなされた御業の上に、私たちの生活が築きあげられなければならない。
神が私達の為にしてくださった恵みのみわざの故に、私たちは、それへの応答として信仰生活を築き上げる。
主の恵みのみわざを我が物として初めて、主のために生きる生活が出来る。」
この順番が大切です。
こっちが寝ずの番をして礼拝したから、神も寝ずの番をして下さる、ではない。
まず神が恵みを与えて下さる。
それに私たちが応答する。
これが信仰生活の基本です。
最初に神が、天と地を創造しました。
そして人を創造し、すべてが整った環境に置きました。
太陽と地球の距離は、ここしかないという絶妙のポイントで、1%でも近いか遠いかずれていたら、全面氷の世界か灼熱地獄の世界。
さらにこの地球に、紫外線などの有害物質を防ぐ大気の衣をまとわせ、地球の温度を一定に保ち、また空気が宇宙に逃げないように守っています。
おまけに大気中の乱反射によって、気持ちのいい青空を見ることができます。
ポンプなしに、海の水を空に上げて雲とし、雲は気流に乗って陸地に移動し、高くそびえる山々に雨を降らせて多くの動物たちの渇きを癒し、川となって流れて海に帰る。
また雨は大地を潤して草花や作物を生じさせる。
しかも一回きりでなく、それこそ永久機関のように何千年も繰り返している、無公害の循環システム。

動物も昆虫も人間も、その恩恵を当たり前のように受けていますが、これは主の恵み、慈しみを表す主のみわざです。
使徒の働き14:17、新約p.257。
パウロが異邦人に語ったことばです。…(神は)ご自身のことをあかししないでおられたのではありません。
すなわち、恵みをもって、天から雨を降らせ、実りの季節を与え、食物と喜びとで、あなたがたの心を満たしてくださったのです。」
当たり前のように恵みを受けていて、日頃、あまり感謝することがなかったかな、と反省させられます。
しかも、こうして日々の命を養って下さっているばかりか、神は私たちに最愛の御子をさえ、お与え下さって、永遠のいのちをお与えになりました。
ことばに尽くすことのできない犠牲を払って、私たちに罪の赦しを与え、神とともに住む永遠の御国を受け継がせて下さった。
その神の御愛に対して、私たちは、どう応答したらいいのでしょう。
まず、神が、私たちを愛して下さったので、私たちも互いに愛し合うようにと言われています。
第一ヨハネ4:10-11、新約p.470
4:10私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために、なだめの供え物としての御子を遣わされました。
ここに愛があるのです。
4:11 愛する者たち。
神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。
また、神が自分を赦して下さったから、他の人をも赦すようにとも。
エペソ 4:32、新約p.378
お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなたがたを赦してくださったように、互いに赦し合いなさい。
また、貧しい人々のための献金を勧めるところで、パウロは次のように言っています。
第二コリント8:9、新約p.354
あなたがたは、私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。
すなわち、主は富んでおられたのに、あなたがたのために貧しくなられました。
それは、あなたがたが、キリストの貧しさによって富む者となるためです。
これらのことはみな、まず自分が神から、キリストから受けた恵みを知るということがあって、そのゆえにこうしなさい、と言われていることです。
このところ、何度か言っていますが、行いだけに焦点を合わせるのでなく、心が大事です。
自分が神から受けた恵みを味わい、思って、それゆえ自分もそのように行う。
そうするときにますます、キリストとの一体感が味わえるでしょう。
先週と同じ結びになりますが、ローマ12:1、新約p.308。
このみことばは、キリスト教倫理の立脚点と呼ばれます。
クリスチャンは、このみことばに立って、他のすべてのことを行うということです。
そういうわけですから、兄弟たち。
私は、神のあわれみのゆえに、あなたがたにお願いします。
あなたがたのからだを、神に受け入れられる、聖い、生きた供え物としてささげなさい。
それこそ、あなたがたの霊的な礼拝です。
「そういうわけですから」は、神から計り知れないご愛を受けているのですから、ということです。
それは「神のあわれみのゆえに」と重ねて、強調されます。
クリスチャンの生活は、神のあわれみに対する応答であり、神のあわれみを原動力とするものです。
神のあわれみにあずかるためのものではありません。
「お願いします」は、勧めることであって、命じることではありません。
命じられて初めて動き出すのではなく、自分から進んで動き出すのです。
それでこそ、神に喜ばれる捧げものとなります。
人は、神に自発的に応答する存在として造られました。
この一週間、主に応答して喜んでみことばを行うことができますよう。
|