<今日の要点>
礼拝は信仰生活の心臓部。
公的にも個人的にも礼拝を大切に守って、健やかな信仰生活を。
<あらすじ>
前回まで、主からモーセに、これからエジプトに対して行うさばきのこと、そしてイスラエル人が代々にわたって守るべき過越の祭り、種を入れないパンの祭りについて、語られました(12:1-20)。
それを受けて、今度はモーセが民の長老たちに語ります。
ここでは過越の祭りの方だけ記されています。
21節「そこで、モーセはイスラエルの長老たちをみな呼び寄せて言った。
『あなたがたの家族のために羊を、ためらうことなく、取り、過越のいけにえとしてほふりなさい。』
前に学びましたが、これは一歳の、傷のない子羊でなければいけませんでした。
いい子羊だからと惜しまずに、「ためらうことなく」ほふるように、モーセは言いました。
そして22節「ヒソプの一束を取って、鉢の中の血に浸し、その鉢の中の血をかもいと二本の門柱につけなさい。
朝まで、だれも家の戸口から外に出てはならない。」
ヒソプという植物が何を指すかは、正確にはわかっていないようです。
ヘブル語ではエゾブ、これのギリシャ語訳聖書(70人訳)でヒュソポスと訳されたことから、ヒソプと呼ばれています。

英語名でヒソプと呼ばれるのは、和名がヤナギハッカですが、これはイスラエル周辺には自生しないことから聖書のヒソプではないと考えられています。
新聖書辞典(いのちのことば社)には、「学名をOriganum maru L.というものであると考えられる。
このしそ科の雑草は、イスラエルの山野の至る所に自生し、また栽培される植物で、夏から秋にかけて小さな淡紫色のくちびる状の花をつける」そうです。
過越の祭りの頃は、まだ花をつける前ということになります。
このヒソプに、きよい子羊の血を浸して門に塗ると、さばきが過ぎ越されるのです。
聖書では、ほかにもヒソプは、きよめのためにしばしば用いられたようです
(参照ヘブル9:19,21-22、新約p435)。
それを踏まえてでしょうか。
ダビデは罪を犯した後、次の詩篇を記しました。
詩51:7、旧約p955。
ヒソプをもって私の罪を除いてきよめてください。
そうすれば、私はきよくなりましょう。
私を洗ってください。
そうすれば、私は雪よりも白くなりましょう。
私たちの罪をきよめるのは、キリストの血です。
悔いる心や罪責感は、必要な時もありますが、深く悔いたからと言って、罪がきよめられるのではありません。
罪そのもの、またこびりついて離れない罪責感も、ただキリストの血によってのみ、きよくされ、雪よりも白くされるのです。
また、朝まで子羊の血の塗られた門から、外に出てはならないと命じられます。
一晩中、息をひそめて、家の中にとどまります。
それは、23節「【主】がエジプトを打つために行き巡られ、かもいと二本の門柱にある血をご覧になれば、【主】はその戸口を過ぎ越され、滅ぼす者があなたがたの家に入って、打つことがないようにされる。」
からでした。
さばきを行う主が、その血を見て、その家を過ぎ越される。
その家の中の人を見て、でなく。
どれだけ功績を積んだか、とか、どれだけ罪を犯したか、とか、家の中の面々を見て、この家は通り過ごそう、この家は見過ごすわけにはいかない、と決めるのでなく、家の中は見ることなく、ただ家の門に塗られた、傷のない子羊の血を見て、通り過ぎるのです。
この原理は、今日の私たちも変わりません。
子羊の血は、罪なき神の御子イエス・キリストの血を表していました。
キリストが、私の罪のために身代わりに十字架にかかって下さったと信じるなら、私たちの心の門にキリストの血が塗られているのです。
さばきのときに、主はそのキリストの血をご覧になって、私たちの罪には目を留めず、私たちはさばきをまぬかれるのです。
神の子羊たるキリストの血が、その心の門に塗られているか、どうか。
その一点に永遠の運命はかかっていると、ありがたいことに聖書は教えてくれています。
そしてこの過越の祭りを、約束の地カナンに入って、定住してからも、代々にわたって守るよう命じます。
もう約束の地に入ったから、主とか、そういうのはいいから、ではなく、子々孫々に至るまで守るようにと。
そしてただ儀式を守るのでなく、ちゃんとその意味も教えるようにと言います。
26-27節「『あなたがたの子どもたちが「この儀式はどういう意味ですか」と言ったとき、あなたがたはこう答えなさい。
「それは【主】への過越のいけにえだ。
主がエジプトを打ったとき、主はエジプトにいたイスラエル人の家を過ぎ越され、私たちの家々を救ってくださったのだ。」』
すると民はひざまずいて、礼拝した。」
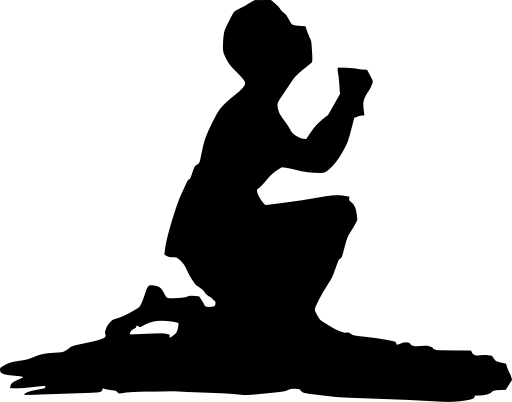
この時点では、まだ事が行われていないにもかかわらず、あたかもすでに、そのようになったかのように、イスラエルの長老たちはモーセの言葉を信じたのでしょう。
今まで、数々の主の大いなるみわざを体験してきたので、さすがに彼らも、まだ見ていないことだけれども、主がモーセに語られた言葉を信じて、そして、ひざまずいて、礼拝しました。
最後の「礼拝した」と訳された言葉は「ひれふす」というのが元々の意味です。
ひざまずき、ひれふす。
これが本来の礼拝の姿だったのでしょうか。
黙示録には、そのような究極の礼拝の光景が多く記されています。
一つだけ引用します。
黙示録4:9-11、新約p481。
4:9 また、これらの生き物が、永遠に生きておられる、御座に着いている方に、栄光、誉れ、感謝をささげるとき、
4:10 二十四人の長老は御座に着いている方の御前にひれ伏して、永遠に生きておられる方を拝み、自分の冠を御座の前に投げ出して言った。
4:11 「主よ。われらの神よ。
あなたは、栄光と誉れと力とを受けるにふさわしい方です。
あなたは万物を創造し、あなたのみこころゆえに、万物は存在し、また創造されたのですから。」
こうしてひざまずいて、主を礼拝して後、彼らは力を得て、立ち上がり、恐れることなく、主の命じた通りに行いました。
28節「こうしてイスラエル人は行って、行った。
【主】がモーセとアロンに命じられたとおりに行った。」
この1節のうちに「行(おこな)った」が二回、繰り返されて強調されています。
いよいよエジプトの地にさばきが臨むに際して、イスラエルは主のことばどおりに備えをしました。
一歳の、傷のない子羊をほふり、その血をヒソプで門のまわりに塗って、家の中に息をひそめてとどまって、そのときを待つのでした。
「祭壇に行き 身も心も ささぐると 同時に」新聖歌 316番
今日は27節の最後と28節に注目したいと思います。
イスラエルの民は、主のことばを聞いて、ひざまずき、礼拝し、そして立ち上がって、主のことばどおりに行いました。
主を礼拝する心があって、主のことばへの従順という実がなる。
これは、今年の年間主題聖句とも、似ているところがあるのではないでしょうか。
主を愛するという根があって、主のことばを守るという実を結ぶ。
根の部分なしに、行いだけに気を取られると、律法主義というものの罠にはまります。
苦しくなり、窮屈になり、あるいは高慢になります。
そういう意味で、神を礼拝することは、信仰生活の心臓部です。
信仰生活にいのちを吹き込むものです。
もう天に召されましたが、マザーテレサという方は、多くの人がご存知だと思います。
インドで、誰からも顧みられずに、道ばたで死んでいくばかりの多くの人たちを、最後までお世話をされた方でした。
小柄な方だったそうですが、小さな体のどこから、そんなエネルギーが湧いてくるのか。
その秘訣を彼女は、祈りであるといいます。
毎朝、まだ暗いうちからお祈りし、黙想し、ミサ(カトリックの礼拝)をして、神から毎朝、力を頂くというのです。
では、どのような祈りをしていたのか?どういう祈りが、神から力を受ける祈りになるのか、というと、彼女の祈りとは、キリストに自分のすべてを差し出し、自身を完全にゆだねること、またキリストと完全に一つになることというのです。
自分中心でなく、神中心、キリスト中心になるように、という祈りです。
これはイエス様が、このように祈りなさい、と教えて下さった主の祈りの原則に一致します。
もちろん、自分の必要、自分の願いを祈っても良いのです。
すべての願いを用いて、神に祈るようにとも、聖書は勧めています
(エペソ6:18、新約p381、ピリピ4:6、新約p387)。
それもよいこと。
ただ、祈りの本筋は、神の御心に私たちの心が一致するように導くことにあると思います。
不思議なことに、そのような祈りを捧げることによって、力が与えられ、勇気が与えられ、自由が与えられ、喜びが与えられることがしばしばです。
自分中心に自分の必要だけを求めていた時には、経験できない恵みです。
また、ひざまずいて、礼拝したとありました。
神の偉大さ、きよさに触れると、さきの黙示録にあったように、だれしも圧倒されて、ひれふして礼拝すると思います。
神は全宇宙を造られた方。
現在、132億光年先の天体に、砂粒が大量にあることが発見されているそうです。

1秒で地球を7周り半する光で132億年かかるところにある天体。
神は、今もそこの砂粒一つに至るまで、支配している方です。
全宇宙とその中に存在しているすべてのものを、今この瞬間も存在せしめているのは、神ご自身の御力です。
私たちの想像を絶するスケールの大きさの前に、人は神の前にひれ伏して、礼拝させられます。
しかしそれだけではありません。
それほどに偉大な方が、私たちを愛して、私たちを滅びから救うために、最愛の御子をお遣わしになり、私たちの身代わりとして十字架にさえ、渡されたのです。
御子キリストは、私たちを愛して、自ら進んで、その苦しみを受けられたのです。
その神と御子キリストのご愛、御真実を知るときに、私たちは完全に圧倒されるのではないでしょうか。
自発的に、「ひざまずいて、礼拝」する心が生まれるのではないでしょうか。
このお方を、「私たちの父よ」とお呼びして、主の祈りに入るというのも、良いようです。
主の祈りの一つ一つの祈願を、心を込めて祈る。
これを日々、続けるなら、この祈りは御霊の働きによって、私たちの心を整え、神に結び付けてくれるでしょう。
また私たちは御言葉によって、神を礼拝します。
私たちの神は、御言葉によって語って下さる神です。
私たちは、聖書を開いて御言葉を読み、それに応答することを通して、神を礼拝するのです。
つまり、生活全体が、神への捧げものであり、礼拝です。
福音にあらわされた神の絶対のご愛、ご真実、義、聖さに触れ、聖書に記されている神の主権、神の救い、永遠の御国、永遠のいのちを確かめ、また聖書に記されている具体的な生活の指針を得る。
ときには、心を刺される御言葉もあります。
それは私たちの魂から毒を取り除く御言葉です。
罪を示し、悔い改めとキリストにある赦しの確信、そして希望へと導く御言葉です。
また赦しを促す御言葉もあります。
それも私たちの心を解放し、健康にするためにも有益です。
これら神の御言葉に応答することを通して、神を礼拝するのです。
今月の聖句は詩篇1:2ですが、3節とともに引用します。
旧約p907。
1:2 まことに、その人は【主】のおしえを喜びとし、昼も夜もそのおしえを口ずさむ。
1:3 その人は、水路のそばに植わった木のようだ。
時が来ると実がなり、その葉は枯れない。
その人は、何をしても栄える。
水路から離れた木は枯れるばかりですが、水路のそばに植わった木は、水を吸い上げて、やがて時が来ると、実を結びます。
私たちも神のことばを取り入れて、素直に応答していくなら、すぐにではなくても時が来て、実を結ぶに至るでしょう。
その人は何をしても栄えるというのは、この世的に栄えるというのでなく、神の御目に栄えるということでしょう。
神の創造のみわざと救いのみわざを思って、神の御前にひれ伏し、そのお方をわが父と呼んで主の祈りを心を込めて祈る。
そして聖書を開いて御言葉に応答する。
そんなふうに神を礼拝する歩みを、と願わされます。
ローマ12:1、新約p308。
そういうわけですから、兄弟たち。
私は、神のあわれみのゆえに、あなたがたにお願いします。
あなたがたのからだを、神に受け入れられる、聖い、生きた供え物としてささげなさい
それこそ、あなたがたの霊的な礼拝です。
|