<今日の要点>
神がして下さったことを土台として、神を第一として礼拝するライフスタイルを。
<あらすじ>
今日の個所は、1-2節がメインの主題で、すべての初子は主に聖別せよ、という主の言葉です。
その後はモーセが民に語った言葉で、3-10節は、以前学んだ「種を入れないパンの祭り」について、11-16節が初子を主に聖別せよ、ということについてとなっています。
どちらも、神の民のライフスタイルについての教えという視点で読みたいと思います。
主がイスラエルをエジプトの奴隷状態から救い出されたのは、彼らを豊かな約束の地に住まわせて、彼らを主の民として生かし、彼らに真の幸いを得させるためでした。
奴隷状態から解放されて、自由で、豊かな地に住めれば、それで人は幸せというわけではない。
自由で、モノがあふれていても、幸せでない人々はたくさんいるでしょう。
どう生きるか、何のために生きるのか。
ある意味、ぜいたくな悩みなどとも言われますが、しかし大切なことです。
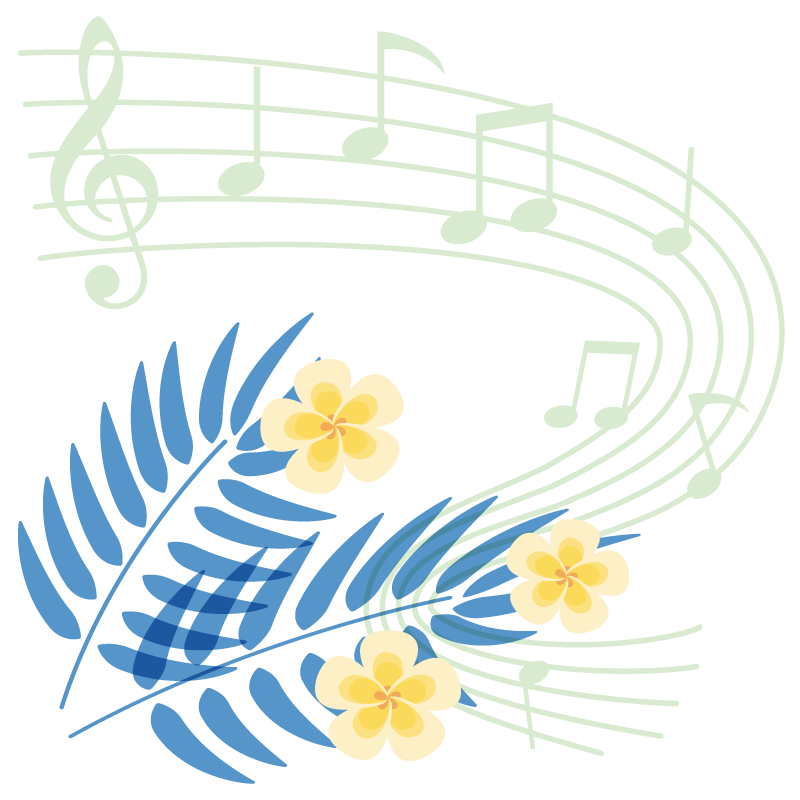
1-2節「【主】はモーセに告げて仰せられた。
『イスラエル人の間で、最初に生まれる初子はすべて、人であれ家畜であれ、わたしのために聖別せよ。
それはわたしのものである。』」
「聖別」とは、主のために取り分けること、またささげることです。
ほかの用には使わず、ただ神の用にのみ使うのです。
それは神聖不可侵なものです。
そういう部分を持つことが、人間には必要ではないかと思います。
自分がお山の大将、世界の中心になってしまわないためにも。
主は、人でも家畜でも、初子はすべて主のものである、だから主に聖別しなさい、とご自身の所有権を主張します。
詳しくは11節以下、モーセが語ります。
そしてモーセは民に語るのですが、なぜか、種を入れないパンの祭りについて、最初に語ります。
神の民のライフスタイルという視点で見れば、共通点があるからでしょうか。
モーセは、まず主が、奴隷の家エジプトから、大いなるみわざを行って解放して下さったことから始めます。
3節「モーセは民に言った。
『奴隷の家であるエジプトから出て来たこの日を覚えていなさい。
【主】が力強い御手で、あなたがたをそこから連れ出されたからである。
種を入れたパンを食べてはならない。』」
彼らが出て来たのは、「奴隷の家」でした。
毎日追い立てられ、責め立てられて、鞭打たれて、精神的にも肉体的にもきつかったエジプトでの奴隷生活。
その日その日をどうにかこうにか、生き延びるので精いっぱい。
苦しみにあえぐ日々。
しかし、どんなに苦しくても、自分たちの力でそこから出ることは不可能だった。
エジプトの強力な軍隊の前に、丸腰で全く無力なイスラエルの民。
しかし神は、彼らが苦しむ姿をご覧になり、そのうめき、叫びを聞かれて、御心を留められた。
そして大いなる御手を伸ばして、驚くばかりの奇跡をもって、次々とエジプトを打ち、ついに彼らを救い出された。
主なる神の奇跡がなければ、ありえないことでした。
これからの彼らの生活の土台となるのは、この事実でした。
繰り返し繰り返し、この歴史的な事実に立って、自分たちの生活、人生を建て上げていくことでした。
これは、強大なエジプトさえ打たれた、大いなる、力ある神が、自分たちを愛して、特別に顧みて目を留めて下さっている。
そのことを覚えて、生きなさいということでしょうか。
大いなる力ある方が、自分を愛して、特別に目を留めて下さっているということを、心から確信して生きることを、主は私たちに願っておられるのだと思います。
どうでしょう。
このとき、イスラエルのために、天から大きな雹を降らせたり、闇で地を覆わせたりなさった神が、今も私たちの神であり、私たちについておられるとは、にわかには信じがたいですが、実際はそういうことです。

そして、この神とともに生きるというときに、私たちが心すべきは、なるべく罪から離れることです。
それで、種(イースト菌)を入れたパンを食べてはならない、と続くのでしょう。
この種は罪を象徴していました。
ですから、主に救い出して頂いたあなた方は、聖い神に愛されている民なのだから、罪から離れて生活しなさい、というのでしょう。
神は罪を嫌悪されます。
また、罪は不幸の種です。
罪から離れることは、私たちの幸いのためでもあります。
なので、モーセは続けて、エジプトを出て約束の地に現に向かっている今、改めて、種を入れないパンの祭りを念押しします。
4節で、アビブの月(太陽暦3〜4月頃)のこの日にあなたがたは「出発する」と訳されているところ、ヘブル語原文は分詞(英語のing形に相当)で、英訳聖書では現在進行形に訳しているものが多いようです。
すでにエジプトを出ているので、その方があっているように思われます。
そしてエジプトを出たはいいが、行き先がなくてあっちこっち放浪するのでなく、主はちゃんと、たくさんの家畜を抱えた彼らを、十分に養うことのできる土地を用意しておられる。
主がはるか昔に、彼らの先祖アブラハム、イサク、ヤコブに約束しておられた、あの「乳と蜜の流れる地」と言われる、豊かなカナンの地。
そこを自分たちのものとするべく、今、あなた方は向かっているのだ。
こう言われて、彼らは希望を新たにしたことでしょう。
さあ、だから、その豊かな地に入り、安定した生活を送るようになったときに、くれぐれも罪の道、滅びの道にそれないように、次の儀式をこの月に守り行いなさい、と6-7節の言葉を語るのです。
が、これがご覧の通り、かなりくどい。
パン種を目のかたきにしているかのように、徹底的にパン種を取り除くよう命じます。
パン種は、罪を象徴しているからでしょう。
罪の力はしぶとく、強いものです。
最初は心の片隅に小さく宿っても、放っておくと大きくなり、心を支配するようになります。
そして人は往々にして豊かになると、堕落することがあるようです。
ある女性が、昔はご主人といっしょに苦労して自営業をやってき、幸か不幸か、それが当たって大金が入るようになった。
ところがそれで、ご主人が悪い遊びをするようになって、息子も悪い連中とつるむようになり、家庭が滅茶苦茶になってしまった。
あの、貧乏でも一緒に苦労していた日々の方が幸せだった、というあかしを読んだことがあります。
罪の力、あなどるべからず、です。
そしてこの種を入れないパンの祭りについて、ただ儀式を守るのでなく、その意味も子どもたちに教えます(8節)。
パサパサした、あまりおいしくないパンを苦菜と一緒に食べるという、正直、あまりうれしくない祭りです。
子どもたちも不満に思うでしょうから、これは、エジプトから出た時、主がして下さったことを覚えるための、大切なお祭りなのだよ、と歴史教育、信仰教育をして、主への信仰を受け継ぐのです。
そして最後に、くれぐれもこのことを忘れず、行うよう念を押します(9-10節)。
「手の上のしるし」は、「手」は「手のわざ」という表現があるように、この祭りを「行う」こと、「額の上の記念」とは、その意味をしっかりと「理解し、覚える」ことを表すのでしょう。
そして最後に「主が力強い御手で、あなたをエジプトから連れ出されたからである。」
と、ここでも主がして下さったことを覚えて、そのゆえに、このおきてを年々、定められたときに守るよう、命じました。
次です。
11節から「初子を聖別すること」について、モーセが民に語ります。
当時、最初に生まれる子は特に尊ばれ、イスラエルでは、長子が他の兄弟たちの二倍の分け前を継ぐことになっていました。
その一番尊いもの、価値のあるものを、主のものだから聖別しなさい、と言うのです。
ただし例外がありました(13節)。
ろばの初子はみな、代わりに羊を捧げます。
ろばは、汚れた動物とされたので、主に捧げることができなかったようです
(民数18:15、旧約p264)。
人間の男の初子は、もちろん贖います。
その代価が羊なのか、銀なのか、わかりませんが、代わりのものを捧げます。
ちなみに、イスラエルが住むことになるカナンの地の先住民たちは、実際に自分の子を火で焼いて、偶像に捧げることをしていました。
そのような忌むべき罪のゆえに、彼らは裁かれることになったのでした。

そしてモーセはここでも、子どもたちにその意味を教えるようにと言います(14-15節)。
どうして、そんなもったいないことをするの?と疑問に思うのも自然なことです。
ここでも最初に、主が力強い御手によって、自分たちを奴隷の家エジプトから連れ出されたことを教えます。
そして、パロがなかなか行かせなかったときに、主がエジプトの初子を人から家畜からみな、打って、いわば力づくでパロを降参させて、イスラエルを解放したことを語ります。
私たちはただ、文字で読んでいるだけなので、手に汗一つ握ることなく読み過ごしてしまうのですが、実際に体験した人にとっては、実に生々しかったでしょうし、その子孫にとっても自分たちの先祖のことですから、心に響いたことでしょう。
それで、それほどのことを、主が自分たちのために、して下さったのだから、自分たちも最も価値あるものを主にお捧げするのだ、というつながりなのだと思います。
2節で主が、初子はすべて、わたしのものだから聖別せよ、と言われていましたが、命令だから仕方なくそうする、ではなく、主がこれほどのことをして下さったのだから、私たちも自発的に、最高のものを主にささげるのだ、というつながりなのでしょう。
この心こそ、礼拝する心です。
そしてこのことを子々孫々、行い、意味を伝えるようにと繰り返します(16節)。
モーセは種を入れないパンの祭りの最初(3節)と最後(9節)、初子の聖別の由来を語る最初(14節)と最後(16節)で、「主が力強い御手によって、あなたがたをエジプトから連れ出された」と言いました。
主の戒め・定めは、主のみわざを背景として、覚えるべきものだということが、読み取れます。
主がして下さったことを覚えて、そのゆえにこれらのことを感謝をもって行うという因果関係を忘れるとき、心の伴わない、いのちのない形式だけの儀式、ただの決まりごとに成り下がってしまうのです。
「全き愛と 低き心 御座に供え ひれ伏す」新聖歌 7番
主は初子はすべて、聖別せよと言われました。
どうしてでしょう。
全地は主のものですから、何か足りないものがあるわけではありません
(使徒17:25、新約p2264)。
もちろん、肉が食べたいわけでもありません。
と考えると、主の関心事は私たちの心だということに思い至ります。
一番尊いものを惜しまずに主にささげる。
愛する相手には、言われなくても自然と良いものをあげたいと思うものでしょう。
それが、神と私たちの理想の関係です。
本来あるべき姿です。
神はそれを望んでおられるのだと思います。
しかし、初子を聖別せよというのは、酷な要求でしょうか。
横暴な専制君主のような命令でしょうか。そうではありません。
神の方こそ、最も尊い、喜びであるひとり子を、私たちのためにお与え下さっていたのです。
ヨハネ3:16、新約p177
神は、実に、そのひとり子をお与えになったほどに、世を愛された。
それは御子を信じる者が、ひとりとして滅びることなく、永遠のいのちを持つためである。
神が、ひとり子をお与えになったほどの愛とは、どういう愛なのでしょうか。
神にとって、天にも地にも御子より尊い存在はありません。
その最愛の御子を、神は私たちのために、十字架の苦しみに渡された…。
この神の救いのみわざを土台とし、そこにあらわれている神のご愛、ご真実を原動力として、罪から離れる生活、そして神を礼拝する生活を送る。これがクリスチャンのライフスタイルです。
贖いを土台として、聖化と礼拝の生活を建て上げるのです。
私たちが救われたのは、神を礼拝し、神に仕えるためです。
そういえば、これまでも主は、「彼らをわたしに仕えさせよ」と何度も繰り返し言っていました。
単に彼らを解放せよ、でなく。
人は神を礼拝するために造られました。
が、罪ゆえに神を正しく礼拝できなくなってしまいました。
しかし、神はキリストによって、その人間の本来の目的、存在意義を回復して下さったのです。
天国は永遠に神を礼拝する場所です。
言葉に尽くすことのできない、すばらしい神を礼拝することが、人にとって最高の幸いなのでしょう。
地上の礼拝はその前味に過ぎませんが、私たちが、神の素晴らしさを知るにしたがって、神を礼拝することがますます喜ばしくなっていくのでしょう。
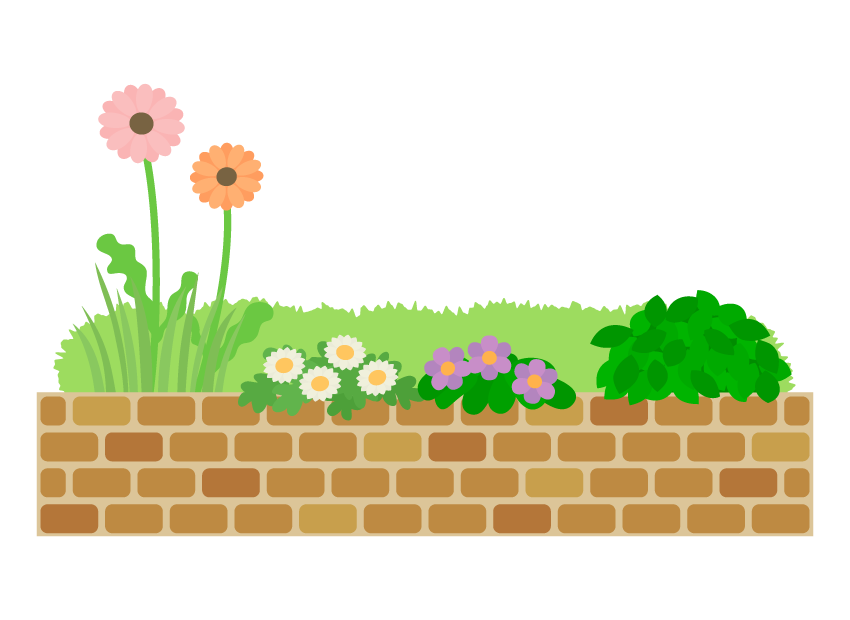
主は第四戒で、安息日を定めておられます。
初子ならぬ週の初めの日を、まず神に聖別せよと。
一週間の初めに、まず神に礼拝をささげる。
また、収入のある人は、最初に主のために、自分で決めた分を取り分ける。
捧げる額が同じなら後回しでも同じ、ではなく、まず主におささげするために、取り分けるという、その心を主は喜ばれると思います。
そんなふうに神を第一にする、神を礼拝するライフスタイルを喜んでさせて頂きたいと思います。
|