<今日の要点>
キリストは、私たちを救うために、過越の子羊として自分がほふられることさえ願われた。
<あらすじ>
前回、モーセは、どこまでも主の前に高ぶることをやめないパロに対して、最後通牒を言い渡しました。
それは主ご自身がエジプト中を生き巡り、初子という初子を打つ、というものでした。
行くところまで行かないとわからないパロ。
これでついに全面降伏、イスラエル人はエジプトの支配から解放されることになります。
そしてこれまでは、イスラエル人は何もすることがありませんでしたが、この第十番目、最後のわざわいでは、やるべきことが命じられます。
と言っても、彼ら自身が棒や槍をもって戦うのではありません。
ただ、主が自分たちを救って下さったことを、子々孫々に至るまで記念し、覚えることを命じられるのです。
主の救いを覚えること。
これがイスラエル人にとってー神の民にとってー最も大切なことなのです。そのために定められたのが、今日の「過越の祭り」と呼ばれるものです。
まず主は、イスラエル人たちがエジプトを出た月を、一年のはじまりとせよ、と言われました(2節)。
この月は「アビブ」(「青穂」の意。

大麦の穂が出始める頃のこと)と呼ばれます(13:4)。
これは太陽暦の3〜4月頃にあたります。
新しい暦のはじまり。新しい歴史のはじまりです。
これまでのエジプトで奴隷として過ごしてきた年月は終わり、これからは神に救われた民として、独立した、自由の民としての歴史が始まります。
私たちも、神を信じ、キリストによって罪と死の支配から救われたときから、新しい人生、新しい歴史が始まっています。
Ⅱコリント5:17、新約p351
だれでもキリストのうちにあるなら、その人は新しく造られた者です。
古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。
そして3節以下、11節まで過越の祭りの行い方です。
まずこの月の10日に、基本的に家族ごとに、1歳の傷のない雄羊または雄やぎを一頭用意します(以下、単に子羊と書く)。
これを食べるわけですが、一家族で多すぎるなら、二家族、あるいはそれ以上で一頭と、その辺は柔軟に行います。
後代になると、一頭の子羊を食べる人の数は、十人と定められるようになったそうです。
ここで大切なのは、「傷のない」子羊でなければならないということです(5節)。
「傷のない」と訳されたヘブル語は、体に欠陥のないことを表しますが、道徳的、信仰的な意味でも用いられ、「全き人(者)」と訳されます(創世記6:9、17:1)。
これは「神の御心に全く合致している」という意味です。

この子羊を14日まで、5日間、念入りに調べます。
そして14日の夕方にそれをほふります。
具体的に何時ころか、ユダヤ人の間にも諸説あるようですが、1世紀のユダヤ人歴史家ヨセフスによると、彼の時代には午後3時頃にほふるのが一般的と記録しています。
そして、羊をほふったら、その血を取って家の門の両側にある二本の柱と、その二本の柱の上に渡してある、かもいにその血をつけるのです。
そしてその夜、その肉を火で焼いて食べます。
その際、「種を入れないパン」すなわちイースト菌の入らないパンと「苦菜」を添えて食べます。
普段、私たちが食べるパンは、イースト菌が入って、発酵しているおかげで、触感もふんわりで、かおりも香ばしく、おいしく頂けるわけですが、それが入ってないわけですから、味もそっけもない。
ほかのところでは「悩みのパン」と呼ばれています(申命記16:3、旧約p333)。
この種を入れないパンは、急な来客の際、発酵させる暇がない時に供されたそうです。
出エジプトのときも、パンを発酵させる暇がなく、パン種の入っていない、こねただけのものを、鉢に入れて背中にかついで出ました。
そのことを思うためです。
「苦菜」は、ユダヤ教では、レタス、チコリー(和名:菊苦菜)、コショウソウ(アブラナ科)、ヘビノネ、タンポポの五種類と指定されているそうです。
苦菜はエジプトにおける苦難を表しました。

調理法は焼きの一択。
鮮度のいいラムだから刺身で、とか、トロトロになるまで煮込んでスープに、もこの時はダメ。
必ずその頭も足も内蔵もすべて、火で焼くことと決められました。
焼くときに煙が空に立ち上るので、天の神への捧げものという意味あいでしょうか。
また、朝まで残してはならず、もし食べきれずに残ったら、全部火で焼かなければいけません。
ほかのときはいいのでしょうが、これに関しては、もったいないからと言って、翌日食べたりしてはいけませんでした。
これは、神を覚えるために聖別されたものと、世俗に用いるものとを厳格に区別するためでしょうか。
ここの区別をあいまいにすると、聖なるものに対して、いい加減な気持ちになってしまいやすいでしょう。
合理的思考に慣れた現代人は、合理性だけでなく、敬虔な感情をもっと大切にする必要があるかもしれません。
食べるときの作法も、指定されました。
腰の帯を引き締め、足にくつをはき、手に杖を持ち、急いで食べる。
ゆっくり味わって食べるのでなく、旅姿でそそくさとすませる。
まるでビジネス街の立ち食いそば屋でかきこむビジネスマンのよう。
「これは【主】への過越のいけにえである。」
とある通り、エジプトを出るときの、緊迫した様子を思うためでしょう。
こうして過越の祭りの指示を与えてのち、12節、イスラエル人がこれらのことを行う夜に、主ご自身が、エジプトの地を巡り、人をはじめ家畜に至るまで、エジプトの地のすべての初子を打つ、と仰いました。
また、エジプトのすべての神々にさばきを下すとも仰いました。
エジプトではたくさんの神々が拝まれていましたが、それらは、エジプト人を救い出すことができない。
いくら拝んでも救いを与えることのできない、偽りの神々であることが、明らかにされるということでしょうか。
また、どれほどの富も、権威・権力も、軍事力も、人間的な知恵も、それらの偶像も、神のさばきから救い出すことはできない、ということも表すのかもしれません。
救いは、ただ主にのみ、ある。
そのことを銘記させるかのように「わたしは【主】である。」
とここで宣言されます。
他方、イスラエル人は、あらかじめ主が教えた通りに行っている限り、みな、滅びを免れます。
13節「あなたがたのいる家々の血は、あなたがたのためにしるしとなる。
わたしはその血を見て、あなたがたの所を通り越そう。
わたしがエジプトの地を打つとき、あなたがたには滅びのわざわいは起こらない。」
ここの「通り過ぎる」から、「過越」と言われます。
ここで大切なのは、主が、さばくためにエジプトの地に臨むとき、門に塗られた子羊の血がしるしとなって、それを主がご覧になって、その家にはさばきを行わずに、通り過ぎるということです。
その血の塗られた門の中にいる者は、みな安全。
富も権力も力も人間的な知恵も、何も関係ありません。
またきよさとか、能力、功績は一切関係なく、ただその血が塗られた門の中にいることだけが、決定的なのです。
イスラエル人がきよいから、救われるのではないのです。
彼らも、私たちと同じ生身の人間です。
神のさばきに耐えられる人はいません。
ただ、彼らには、さばきを免れる方法が教えられたのです。
その主のことばを信じて、従ったら、滅びから免れたのです。
逆に、たとえイスラエル人であっても、主が教えて下さった救いの方法を、なんだそんなもの、と拒否して、俺はこのままでいい!と子羊の血を門に塗らなかったら、さばかれるのです。
子羊の血が塗られた門の中にいるか、どうか。
そこだけが、分かれ道です。
その一点にかかっているのです。
過越の祭りの中心は、そこにあるのではないか、と思います。
なぜ、神はその血を見て、通り過ぎて下さるのか。
傷のない子羊の血の価値。
そこに注目させることです。
「赦し与え きよくするは ただ主の血あるのみ」新聖歌 108番
イエス・キリストが十字架にかかられたのは、この過越の祭りの日でした。
それは偶然ではありません。
この日でなければなりませんでした。
なぜなら、キリストこそ、真の過越の子羊だからです。
キリストが流された血によって、信じるすべての人は、全地に臨む神のさばきを免れると聖書は教えています。
過越の祭りはキリストを表すものなのです。
アビブの月の10日に群れの中から羊を取って、過越の準備が始まったように、その日にイエス様はエルサレムに入りました。
そして5日間、子羊に傷がないか調べたように、イエス様も、何とか難癖をつけようと隙を窺うパリサイ人たちから論争を仕掛けられました。
最後には、ユダヤ人指導者たちによる裁判で調べられ、人々は偽証してでもイエス様を有罪にしようとしましたが、できませんでした。
最後は、イエス様がご自分を神と等しいとしたということで、死に値する冒とく罪だ、と判決を下しました。
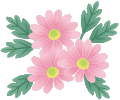
当時、ユダヤ人には勝手に死刑を執行する権限はなく、ローマの許可が必要だったので、彼らはローマ総督ピラトに訴え出ました。
ピラトは裁判においてイエス様を調べましたが、彼も「この人にはなんの罪も見つからない。」
と言いました(ルカ23:4、新約p166)。
さらにイエス様は、実に裏切り者イスカリオテのユダをしても、この方には罪がないと言わしめました(マタイ27:4、新約p59)。
そしてイエス様は、人から潔白と認められただけでなく、父なる神の御目にも一点のシミも汚れもないお方です。
イエス様だけは、いくら叩いててもほこりひとつ出てこない、心の底まで完全なきよいお方、父なる神の心と完全に合致しているお方です。
イエス様は、神の御目にも完全な、傷一つない子羊でした。
そして過越の子羊は、午後三時ころ、ほふられました。
キリストが十字架上で死なれたのは、実にその時間でした。
マタイ27:45−46、新約p61。
27:45 さて、十二時から、全地が暗くなって、三時まで続いた。
27:46 三時ごろ、イエスは大声で、「エリ、エリ、レマ、サバクタニ」と叫ばれた。
これは、「わが神、わが神。
どうしてわたしをお見捨てになったのですか」という意味である。
そして、さばきを行う主は、家の門に塗られた子羊の血を見て、その家にさばきを下さず、通り過ぎると言われました。
ただの目印ならペンキでもいいはずですが、これはペンキではダメです。
まったき子羊の血でなければいけない。
これはただの目印ではないのです。
主はその傷のない子羊の血を見て、通り過ごすのです。

これは、さばきの時に神が、私たちの罪に目を留める代わりに、キリストのきよい血に目を留めて、私たちをさばきから免れさせて下さることを表しています。
あの家の中にいる者は、誰であれ救われたように、キリストの十字架が自分のためだと信じるなら、誰であれ、キリストの血のゆえに、救われるのです。
キリストの十字架が、自分のためと受け入れたとき、いわば、心にキリストの血が塗られるのです。
この時、子羊の血が塗られた門の家の中にいるか、外にいるか、その一点に救いがかかっていたように、永遠のさばきにおいても、いわば、キリストの血が塗られているかどうか、その一点にかかっています。
聖餐式は、イエス様が十字架にかかられる前夜、弟子たちと取られた食事、いわゆる「最後の晩餐」が元になっています。
その最後の晩餐は、この過越の食事でした。
アビブの月の14日、傷のない子羊をほふり、その日の夜、この食事をしながら、古の昔、神がエジプトの苦しみからイスラエルを救い出されたことを覚えたことでしょう。
その際に、傷のない子羊がほふられ、その血が門に塗られたことによって、その家の中のものが滅びから免れたことを思いながらでしょうか、その席上、イエス様は仰いました。
ルカ22:15、新約p162。
イエスは言われた。
「わたしは、苦しみを受ける前に、あなたがたといっしょに、この過越の食事をすることをどんなに望んでいたことか。…
このあと、ご自身が、ご自分の民を滅びから救うために、罪と死の支配から解放するために、ご自身が傷のない真の子羊としてほふられることをご存じであられながら、こう仰ったイエス様。
ご自分が犠牲になってでも、ご自身の愛する者たちが救われることを願って、この時をどれほど望んでいたことか、と仰る主。
この過越の食事をすることを、どれほど恐れていたか、の間違いではないですか?とお聞きしたくなります。
このあと、十字架にかけられるんですよね?それなのに、それなのに、どれほど望んでいたことか、と仰るのですか…。
私たちの救い主、贖い主は、こういうお方なのです。
この後の聖餐式で、「これはわたしのからだです」「これはあなたがたのために流される、契約の血です」と語りかけて、聖餐に招いておられる主を、親しく覚えさせて頂きたいと願います。
|