<今日の要点>
世にさばきが臨むときにも、主はご自身の民とともにおられ、平安を与えることできる。
<あらすじ>
11章は、場面としては10章の続き。
モーセを呼び出したものの、自分の思い通りにならず、ついにブチギレたパロが、今度、会ったときは、命はないものと思え、と言えば、モーセは、結構です、もう二度とあなたの顔を見ません、と応じたところで、10章は終わっていました。
売り言葉に買い言葉というわけでもないのでしょうが、このあたり、モーセはパロに対して怒りを感じていましたから(8節)、つい言ってしまったのかもしれません。
しかし、モーセはパロの前を去る前に、言っておかなければならないことがありました。
そのことを主はここでモーセに示されます。
1節「【主】はモーセに仰せられた。
『わたしはパロとエジプトの上になお一つのわざわいを下す。
(ここで終わりではない。まだ最後のがある。)そのあとで彼は、あなたがたをここから行かせる。
彼があなたがたを行かせるときは、ほんとうにひとり残らずあなたがたをここから追い出してしまおう。』」
モーセよ、気持ちはわかるが、その前に、わたしはなお、もう一つのわざわいを彼に下すのだから、そのことをあなたはパロに告げなければならないと。
さばきの内容は4節以下にありますが、このさばき自体は、すでに語られていました(4:21-23)。
それをより具体的に示されたのでしょう。
そして、そのあとは、パロは本当に一人残らず、イスラエル人を追い出すが、そのときに、あたかもパロを恐れて逃げる者のように、何も取らずに出て行ってはならない、ということも思い出させます。
2節「さあ、民に語って聞かせよ。
男は隣の男から、女は隣の女から銀の飾りや金の飾りを求めるように。」
これも以前にも語られていたことですが(3:21-22)、リマインドしたのでしょう。
イスラエル人は奴隷として、エジプトの荘厳な建築物を建てるために、長年、酷使されてきましたから、その労働に対する正当な報酬として、これをちゃんと持って出るようにと。
この金銀はのちに、幕屋礼拝に使われる器具を作るための材料となりました。
もちろん、それ以外はイスラエル人の財産となりました。
しかしそんなことを言っても、エジプト人が、はい、どうぞ、とスンナリ与えるだろうか、と思うところです。
が、ここにも主が働かれて奇跡が起こります。
3節「【主】はエジプトが民に好意を持つようにされた。
モーセその人も、エジプトの国でパロの家臣と民とに非常に尊敬されていた。」
実際にイスラエル人が、エジプト人から金銀を求めるのは、第十のわざわいが下ってのち、エジプトを出るときです(12:35-36)。
それにしても、エジプト人たちが、イスラエル人に好意を持つというのは、奇跡です。
好意と言っても、大好き!ということではなく、抵抗せずに与えるということでしょう。
嫌がるのをひったくるようにして、争って取るのではないと。
それにしても奇跡です。
悪いのはエジプトながら、イスラエル人のせいで自分たちがこんなわざわいにあっている!と逆恨みするのが人間というものでしょう。
モーセその人にしても、たとえ彼自身は立派な人格者だったにしても、モーセを通して次々とわざわいが臨んだとなれば、こいつのせいでこんな目に…となるのが人の情というものでしょう。
それが尊敬される。
口語訳は「はなはだ大いなるものと見えた」と訳しています。
次々と奇跡を行うモーセを、むしろ恐れたというニュアンスでしょうか。
それで抵抗せず与えたと。
神がみわざをなさるときには、こういう不思議が起こるのでしょう。
このとき、モーセが立ち去ろうとしたところに、主がこれらのことを語って下さいました。
たまに、必要な時に、ある考えなどが、フッと思い浮かぶというか、心に降ってくるような感じがするときがあります。
それは御霊が与えておられる可能性があります。
自分の勝手な思い付きの場合もあるので、すぐに決めつけない方がいいですが、そういうときは、いったん心に留めて、さらなる導きを求めても良いと思います。
以上、主から語りかけを頂いて、モーセはパロに最後の通告をします。
4節「モーセは(パロに)言った。
『主はこう仰せられます。
「真夜中ごろ、わたしはエジプトの中に出て行く。
エジプトの国の初子は、王座に着くパロの初子から、ひき臼のうしろにいる女奴隷の初子、それに家畜の初子に至るまで、みな死ぬ。
そしてエジプト全土にわたって、大きな叫びが起こる。
このようなことはかつてなく、また二度とないであろう。…」
真夜中ごろとは、この日ではなくて、何日か経った後の真夜中と思われます。
その間、パロたちはできる限りの対策を講じたでしょう。
呪法師を呼び、護衛を増強し、初子を外に出さないなど。
しかし、人がどれほど知恵と力を振り絞っても、神のなさることを防ぐことはできません。
「わたしはエジプトの中に出ていく」これまでは、モーセとアロンの杖によって、事が行われましたが、今度は主ご自身が出ていきます。
「ひき臼の後ろにいる女奴隷」とは、最も貧しい者のこと。
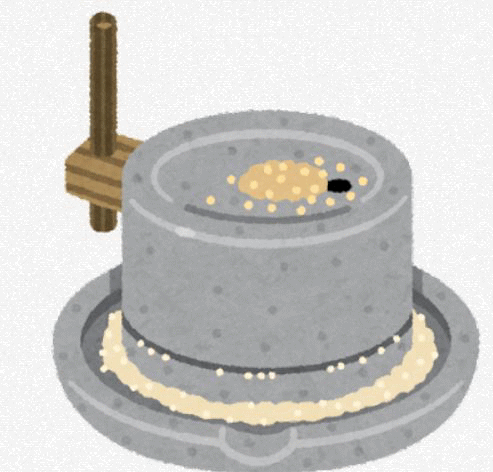
ですから、身分の高い者も低い者も、すべてのエジプト人の初子ということです。
また人ばかりでなく、家畜の初子に至るまで。
初子という初子が、取り去られるというのです。
エジプト中に激しい叫び声が起こります。
後にも先にも、二度と起こらない出来事でした。
かつてパロは、「イスラエル人に生まれた男の赤ちゃんは、みな、ナイル川に投げ込まなければならない」と命令を下しました(1:22)。
それに対する裁きでもあるのでしょうか。
ところが、ここでもイスラエル人は区別され、特別な守りが与えられます。
7節「しかしイスラエル人に対しては、人から家畜に至るまで、犬も、うなりはしないでしょう。
これは、【主】がエジプト人とイスラエル人を区別されるのを、あなたがたが知るためです。」
ここでもエジプトとイスラエルは対照的です。
全エジプトに大きな叫びがあったのに対して、イスラエルでは犬もうなりはしない…。まったく平和。
主は、ご自身の民を区別されます。
そして主は区別することを、知らせたいと思っておられます。
最後にモーセは、事の結末がどうなるか、パロに告げます。
8節「『あなたのこの家臣たちは、みな、私のところに来て伏し拝み、「あなたとあなたに従う民はみな出て行って下さい」と言うでしょう。私はそのあとで出て行きます。』
こうしてモーセは怒りに燃えてパロのところから出て行った。」
パロよ、あなたはそうやって意地を張っても、あなたの家臣たちはもう、あなたを見限って、直接、私の所に来て、どうか、出て行って下さい、と願うでしょう、と。
そう言って、モーセは怒りに燃えてパロの前から出て行きました。
そんなモーセの後姿を、パロは、歯ぎしりしながら、にらみつけて見送ったでしょうか。
ここのモーセの怒りは、何の怒りでしょう? パロのかたくなさが、どれほど多くの悲劇を引き起こすか。
エジプトの民衆のことを思うと、モーセの心も張り裂けんばかりだったのかもしれません。
それゆえのパロに対する怒りだったのかもしれません。
そんなモーセに主は、これまで何度か語られたことを繰り返されます。
9-10節。
「【主】はモーセに仰せられた。
『パロはあなたがたの言うことを聞き入れないであろう。
それはわたしの不思議がエジプトの地で多くなるためである。』
モーセとアロンは、パロの前でこれらの不思議をみな行った。
しかし【主】はパロの心をかたくなにされ、パロはイスラエル人を自分の国から出て行かせなかった。」
これだけ言っても、パロは聞き入れない。
それは、最初から言っていたように、神の大いなるみわざがエジプトの地で多くなるため…。
モーセも、後から振り返って、このように思うことができたのではないでしょうか。
モーセならずとも、この世で義憤にかられることあります。
そういうとき、最後の最後は天地万物をまったくの無から造られた神の主権、絶対主権に立ち返る。ここが最後の砦と言いますか。
ここがないと、おさまりがつかないように思います。
今はわからなくても、最善以下のことはなさらない、神の絶対主権のもとにある。
それでも、心から納得はできないでしょうけれども、私たちの心を守る最後の砦となるのではないでしょうか。
「主 宣(の)たまえり『われなどて なれを捨てて 去るべき』」新聖歌254番
今日の個所は「犬も、うなりはしないでしょう」という言葉が印象的です。
犬は敏感で、ちょっと物音がしたり、おかしな気配がすると、ワンワン吠える習性があります。
そんな性質を持つ犬も、うなりもしないというのです。
まったくの平安な、長閑なと言ってもいいような状態。
エジプト中に激しい叫び声があがったのですから、ただならぬ気配を感じてもよさそうなものですが。
これは超自然的な、まったき平安を強調する表現なのでしょう。

このイスラエルの平安は、主がともにおられることから来る平安です。
普通じゃない。主が与える不思議な平安です。
ヨハネ14:27、新約p211。
わたしは、あなたがたに平安を残します。
わたしは、あなたがたにわたしの平安を与えます。
わたしがあなたがたに与えるのは、世が与えるのとは違います。
あなたがたは心を騒がしてはなりません。
恐れてはなりません。
これはイエス様が十字架にかかられる前夜、弟子たちに語られた言葉です。
このあと、弟子たちは迫害を受ける。
心を騒がすこと、恐れることに直面する。
しかし「わたしはあなたがたに平安を残します。
わたしは、あなたがたにわたしの平安を与えます」と仰いました。
「わたしの平安」イエス様の平安。
それは世が与えるのとは、違うといいます。
世が与える安心とはー神が与える平安と区別して安心と呼びますがー目に見える状況や条件が整って得られるものです。
しかしこの世は、うつろいやすく、状況は時々刻々、変わっていくもの。
昨日は思ってもみなかったことが、今日、起こることもあります。
そういうものに心の拠り所をおいていては、本当に心の安まることはないのではないでしょうか。
それに対して、イエス様が与える平安とは、神がともにおられるという平安です。
手の付けられないほど、泣いていた赤ちゃんが、お母さんに抱っこされたとたん、ピタリと泣き止むように、神がともにおられるー神の懐に抱かれるーことは、理屈を超えた平安を与えるものです。
昔、ある姉妹が、まだ幼いお子さんを天に送られました。
その姉妹のお母さんは、娘は大丈夫だろうか、葬儀にも出れないんじゃないだろうか、と心配したそうです。
ところが、その時が来ると、その姉妹は落ち着いて、平安な様子が、お母さんにも伝わるほどだったと言います。
お母さんは、「あれは、私の知っている娘ではない。
どうしてあんなに落ち着いていられるのか」と仰ったそうです。
後で聞いたところでは、葬儀の間中、その姉妹の心にはずっと讃美歌が流れていて、隣にイエス様がいてずっと私を支えていてくれていたように感じて、不思議な平安に包まれていた、ということでした。
また、以前、ある場所で「平安」というテーマで展覧会が行われたそうです。
のどかな田園風景、木漏れ日の下で戯れている子犬の絵、波一つない美しい水辺の絵、いかにも平安を思わせる様々な絵が出品されました。
しかし、その中で最も多くの人の心をひきつけた作品は、嵐の海の様子を描いた絵でした。
不気味などす黒い雲の下、荒れすさぶ風と高巻く波。
そこにそそり立つ断崖絶壁の岩。
波は勢いよく岩にぶつかり、しぶきをあげています。
これのどこが平安なのか、と思ってよく見ると、その岩の割れ目に親鳥が翼で雛を覆って休んでいます。
イエス様の与える平安というのは、こういうものではないでしょうか。
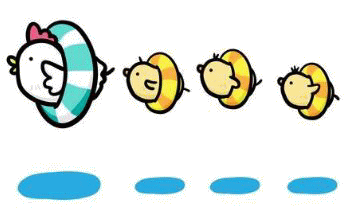
神を信じたからといって、悩みや問題がまったくなくなるわけではありません。
試練は他の人と同じように襲ってくるでしょう。
しかし、イエス様が約束された「平安」は、そんな嵐の中にあっても、神がともにいて下さるという平安。
キリストが岩となって私たちを嵐から守って下さる平安。
また親鳥となって守って下さる平安です。
しぶきくらいはかかるかもしれません。
おびえさせる音は聞こえてくるでしょう。
そういうときには、私たちは揺れ動き、恐れます。
しかしそのまっただ中にあって、神がともにおられるという、理屈を越えた平安、絶対的な存在がいつもそばにいて、守っておられるという平安を、イエス様は与えることができます。
天地万物を造り、今もすべてを支配なされている方が、私たちとともにおられ、私たちをその御翼の陰にかくまい、覆って下さる。
それは、気休めではなくて、目には見えないけれども確かな現実です。
主の言葉を聞きましょう。
ヘブル13:5、新約p442
…主ご自身がこう言われるのです。
「わたしは決してあなたを離れず、また、あなたを捨てない。」
|