「恵みによる救い」シリーズを終了し、思いを新たにみ言葉に耳を傾けようと、前回は「伝道者の書」12章1節以下を心に刻んだ。
ボンヤリと「神」を信じるのではなく、「私たちは天と地を造られた神、『創造者』であられる神を信じます」と、明確な信仰を言い表したいと願うからであった。
その時、次の機会は12月第二週となり、どのみ言葉から学ぶのか思い巡らした。
クリスマスの季節に、主は、何をどのように導いて下さるのか・・・と。
行き着いたのが今朝の聖書個所である。
神の御子がお生まれになった出来事を、私たちが倣うべき生き方として、しっかり捉えているかどうか、そのことを見つめ直したいと。
クリスマスの季節は確かに喜びの時である。
けれども、ただ単なる喜びではない。
深い意味のある喜びであることを覚えたい。
巷のクリスマスとは違う!と覚えたいのである。
1、使徒パウロは、ローマ帝国が支配する世界の各地に福音を宣べ伝えていた。
各地にキリスト教会が起こされ、福音の広がりは目覚ましかった。
ところが同時に、各地の教会には様々な課題があって、パウロは心を痛めながら、その課題を乗り越えられるように、諸教会に手紙を書き送っていた。
ピリピ人への手紙はその一つである。
彼にとってのピリピの教会は、思い出すたびに先ずは「感謝」が溢れる、喜ばしい教会であった。
初穂であったルデヤを中心に、貧しさの中にあっても、喜んでささげる教会として、パウロの働きをよく支えた。
そのような群れであったからか、
「ただ一つ。キリストの福音にふさわしく生活しなさい」
と勧め、福音のために「ともに奮闘しており」と、励ましの言葉を贈っている。
その上で2章1節以下の勧めを語る。
キリストにあって歩んでいるなら、一層「私の喜びが満たされるように」と言う。
「一致を保ち」、「同じ愛の心を持ち」、「心を合わせ」、「志を一つにしてください。」
それを言い換え、
「何事でも自分中心や虚栄からすることなく、へりくだって、互いに人を自分よりすぐれた者と思いなさい。
自分のことだけではなく、他の人のことを顧みなさい。」
パウロは心を込めて語っている。
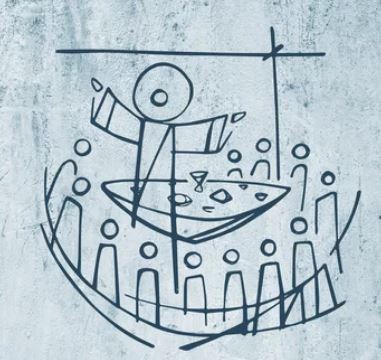
2、パウロにとって、喜ばしい群れ、感謝が溢れる教会であっても、なお残る課題、一層の高嶺を目ざすべきは、「キリストにあっての一致」であり、そのために必要なのは「へりくだり」である。
それは「互いに愛し合う」ことであって、主イエスご自身が、大切な戒めとして、はっきりと語っておられることである。
(マルコ12:28-31) 主は、最後の晩餐の席でも語られた。
(ヨハネ13:34)互いに愛し合うことを難しくするのは、私たち人間の罪のゆえの、心の頑なさである。
御子イエス・キリストの十字架の血潮によって、罪の赦しをいただいた者でも、この地上にある限り、罪との戦いがあることを認めなければならない。
恵みにより、信仰によって、罪の赦しを与えられた者は、もはや罪によって縛られてはいない。
それゆえに、自己中心や虚栄からは解き放たれている。
だからこそ、「へりくだって、互いに人を自分よりもすぐれた者と思いなさい。」
この「へりくだり」は、主イエスご自身のお姿に見られることであると、人々の心を、神の御子に向けるよう語る。
「あなたがたの間では、そのような心構えでいなさい。
それはキリスト・イエスのうちにも見られるものです。」
(5節 ※新改訳2017「キリスト・イエスのうちにあるこの思いを、あなたがたの間でも抱きなさい。」 ※文語訳「汝らキリスト・イエスの心を心とせよ。」 )
3、「キリストは神の御姿である方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして、仕える者の姿をとり、人間と同じようになられました。
人としての性質をもって現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。」(6〜8節)
神の御子が人となって世に来られたのは、至高の神が神の御姿を捨てることがなければ、起こり得ないことであった。
それほどに「ご自分を無に」され、「仕える者の姿」をとられたのである。
「人間と同じようになられた」ことには、「自分を卑しく」することが含まれていた。
私たちは、クリスマスの出来事を喜びをもって思い描きながら、神ご自身が人となられたことを、自分自身を「無にする」ことや、「仕える者となる」こと、また「自分を卑しくする」ことに当てはめ、自分の生き方に関わることとして考えているだろうか。
というのは、この生き方は、この世の常識、またこの世の価値観とは全くかけ離れているからである。
私たちは普段、全く反対の生き方や考え方を追い求めているのではなだろうか。
この世は、自分がどれだけ優れているかを競い、自分が認められることこそが尊いと、ひたすら人と自分を比べ、自分の存在を確かめようとしている。
その弊害は、キリストの教会の中にも忍び込んでいることを、パウロは知っていた。
だから、十字架のキリストを仰ぐこと、また、いと低くなられ、人としてこの世に来られた神の御子を、しっかり覚えることを説いたのである。
私たちは、何としてでも、人となられた方、十字架の死にまで従い通された神の御子、キリストを仰ぎ見て、この方に従い通すことを学ばねばならない。

<結び> 人となって世に来られた神の御子は、十字架で死なれ、私たちの罪の代価を支払って下さった。
十字架の死にまで従い通された御子は、死で終わることなく、死からよみがえって、御子を信じる者も、よみがえりの命に生きる希望のあることを明らかにされた。
この方を信じる者が、いよいよ増し加えられることこそが、父なる神のご計画である。
「すべての口が、『イエス・キリストは主である』と告白して、父なる神がほめたたえられるためです。」(9〜11節)
私たちが、クリスマスを救い主のお生まれと喜び迎えられるのは、何と幸いなことであろうか。
と同時に、ただ単なる喜びとして、この世の人々と同じように過ごしてしまわないよう心したい。
私たちは、神の御子が、神としてのご自分の在り方を捨てて、人となって世に来られた意味を知ること、そのお方のお姿に倣うことを、真剣に祈り求めたい。
「へりくだる」ことを学ばせていただきたい。
それができないなら、私たちの信仰は見せかけのものでしかなくなってしまう。
パウロは、それほどの覚悟をピリピの教会の人々に迫っていたのである。
私たちも、そのパウロの思いに触れて、私たち自身の生き方を、主ご自身によって探られ、導かれ、整えられたい!!!
|