<今日の要点>
神ご自身が、ご自身の民の生きる指針を与えて下さった。
<はじめに>
出エジプト記第20章となります。
出エジプト記は全部で40章ですから、ちょうど半分、折り返し地点となります。
ここでいよいよ十戒授与の場面となります。
十戒は、神が、「このように生きなさい」とただポンと与えたものではなく、契約の一部として与えられたものだということを、19章で見ました。
そこでは、この契約が彼らにどんな祝福をもたらすかが、語られました。
すなわち、もし、彼らが神の言葉を守り、行うなら、彼らは神にとって宝となるという祝福。
神にとって宝・尊いものといえば、御子キリストの似姿。
元々神に似せて、神のかたちに造られていた人間が、罪を洗い落とされて、本来の姿を回復し、その光を輝かせるようになる、ということでした。
異教の神々の影響が生活の隅々にまで及んでいたエジプトの地から、またそこで虐げられていた奴隷状態から、救い出されたイスラエルの民に、あとは好きにしなさい、などと荒野にほっぽりだすのでなく、ちゃんと神の民としてどのように生きるか、道筋を教え、そうすればどのような祝福が待っているか、祝福をもって励まして下さる神の親心の現れと見ることもできるでしょうか。
その契約のことばがいよいよ語られます。
今回は、十戒全体に関することを取り上げ、次回以降、一つ一つの戒めについて見ていきたいと思います。
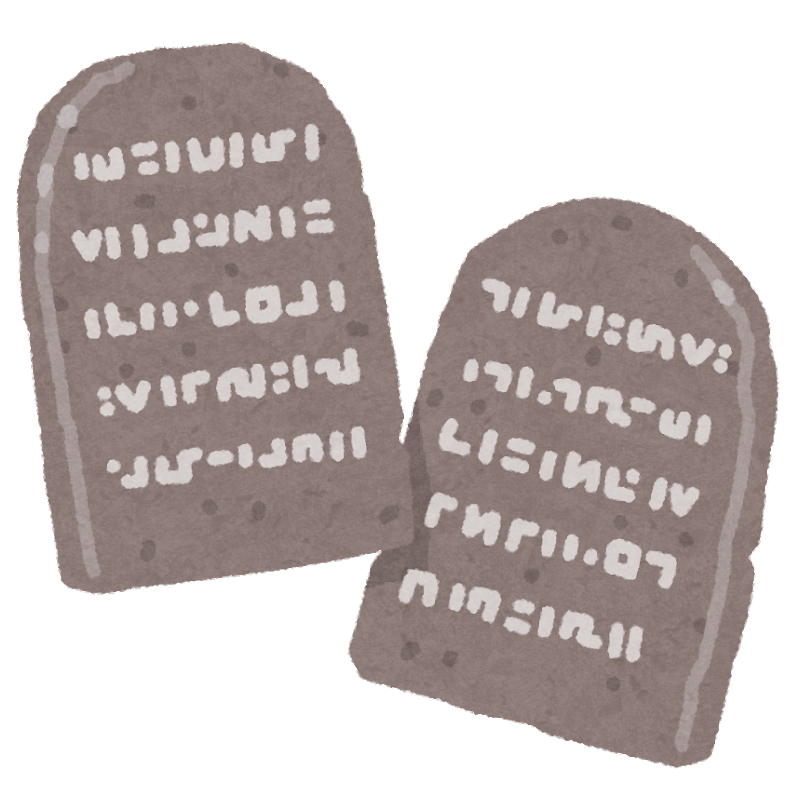
<十戒は、神が直接、民に語られた:十戒の神的起源>
1節「それから神はこれらのことばを、ことごとく告げて仰せられた。」
十戒について、まず覚えたいのは、これから告げられる言葉は、天地の造り主なる神が、直接、語られた言葉だということです。
モーセ個人の言葉ではない。
齢80の人生経験も豊富、知恵もある、学問もあるモーセという指導者が、あれこれ考えて、これをイスラエルの憲法にしようと定めたものではない。
人類の英知を傾けて作った法というのでもない。
十戒の起源・出所は人ではなく、実に神なのです。
神から、直接、語られたものなのです。
私たちはまず、そのことを心に刻むべきでしょう。
単なる人間同士の取り決め、ルールなら、自由に話し合って変えることもできるでしょう。
都合が悪くなったら手を入れても、承認されればそれでよいわけでしょう。
しかしこれは人間の勝手な都合でねじ曲げたり、削除したりすることは許されない、神聖不可侵な神の言葉です。
十戒は、イスラエルの民に対してだけ、語られたのではなく、私たちに向けても語られた言葉です。
世界観においても倫理道徳においてもますます混乱を極めてきた昨今、こういう永遠に変わらない神ご自身から与えられた確かな生活規範を持っていることは、ありがたいこと、幸いなことではないでしょうか。
自分はこれで行く、これによって生きる、と言えるもの、心から信頼できる基準、言葉を持っている。
これがキリストを信じる者の生きる道だと、世間の雑音に惑わされずに行きたいものです。
特に、人のものを盗む、人を平気で殺す、姦淫の罪を犯す、嘘をつく、だますなんていう事件が、毎日のように起こっている現代の世相を見ると、この十戒の、当たり前のようなことをみなが守っていたら、どれほど静かで、平和で、安心して暮らせる世の中になっていることか、と思ってしまいます。
十戒は、天地の造り主なる神が、私たちがどう生きるべきか、という道筋をギュッと凝縮して、わずか十のことばとして結晶させたもの。
起源は人ではなく、神ご自身。
幾千万の金銀にも勝る貴重な御言葉です。
もう一度、そのことを心したいと思います。
<十戒の構成について:神を愛し、人を愛すること>
2節から、その神の語られた御言葉になりますが、普通、十戒はこの2節から17節までを指します。
大きく分けて前半は、神に対する人の関係、対神関係についてであり、後半が人と人との関係、対人関係についてです。
十の戒めの分け方については、教派によって違いがありますが、長老教会で採用している区分は、まず2節を十戒全体の序文とします。
そして3節「わたしのほかに、他の神々があってはならない」を第一戒とします。
4-6節を「偶像禁止」の第二戒。
7節「主の御名をみだりに唱えてはならない」を第三戒、8-11節の安息日規定を第四戒として、ここまでが対神関係について定めた前半部とします。
それから
12節「あなたの父母を敬え」が対人関係の最初に来る戒めで第五戒、
13節「殺してはならない」が第六戒、
14節「姦淫してはならない」が第七戒、
15節「盗んではならない」が第八戒、
16節「偽りを言ってはならない。」が第九戒と来まして、
最後17節「むさぼってはならない」が第十戒となります。
ルター派やローマ・カトリック、また古くからあるユダヤ教の伝統では、違う分け方をしているようです。
いづれにせよ、十戒の構成は前半で対神関係、後半で対人関係について定めているのですが、この十戒の構成そのものにも、ありがたい神のお心があらわれているようです。
神が与えた戒めは、よくみると、半分以上は実は、私たち人間同士の益となるためのものです。
神が要求しておられるのは、ご自分を礼拝するように、ということだけではない。
むしろご自分に関することは4つしか求めずに、あとの6つは人間のために割いておられて、お互いに尊重しあい、愛しあい、お互いに大切にしあって、平和に、みんなが幸せに暮らすように、と命じているのです。
神は、いかに人を大切にしておられるか。
いかに、人間のことに心を用いておられるか。
神が十戒という律法を命じておられるのは、暴君のようにただ自分を拝め、従え、自分に仕えろ、ではない。
私たちの自由を奪って、窮屈にさせるのでもなく、私たち人間自身の幸いを願っての命令なのです。
神は、私たちの生活に関心があるようです。
私たちがどう生きているか、どういうふうに共同体として歩んでいるか。
そこにキリストに似姿が形作られているか…。
私たちの間に、神の教えと戒めが行き渡ることが大切と、以前、学びましたが、まさに御言葉が私たち相互の間に行われていることを、神は喜ばれるのだと思います。
もっとも大切な戒めは何かと問われて、イエス様は、神を精一杯愛することを第一の戒めとしてあげてのち、「あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ」という第二の戒めも、それと同じように大切です、と言われました(マタイ22:39、新約p. 46)。
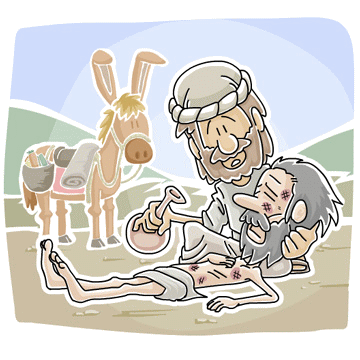
<序文が大切:救われたから、愛されているから、御言葉を慕い、従う>
次に2節、十戒全体の序言を見ておきたいと思います。
「わたしは、あなたをエジプトの国、奴隷の家から連れ出した、あなたの神、【主】である。」
実際の戒めに入る前に、この序言があることに、大きな意味があります。
彼らがこれから戒めを守る前に、まず神の一方的な救いの恵みがあるということです。
彼らに対して、主が示した恵み、ご真実、彼らに対する主の御愛を、まず覚えるということです。
イスラエルの民は、すでに神とそのような関係にあるのだからーすでに恵みを受け、愛されている関係にあるのだからーこのお方を信頼し、このお方の御言葉に従うのです。
何度も言っていますが、学校の規則か何かのように、とにかく規則だから守らなければならない、と言うのでなく、私たちを愛し、恵みをもって救って下さった全知全能の神からの言葉だから、信頼して、従う。
幼子が親を信頼しているように、神に信頼を寄せるがゆえに、その言われることに素直に従う。
神が私たちに語られる言葉はみな、神がすでに与えておられる救いということを背景として、受け取られるべきものです。
そこを見失うと、神の命令や戒めの本質を見誤ってしまいます。
これを今日のクリスチャンに適用すると、神は、私たちが何かしたから、立派な行いをしたから、ではなくて、ただ恵みによって、キリストを救い主と信じるすべての者を、ご自身の子として受け入れて下さった。
恵み先行。救い先行。一方的なご愛先行です。
その恵み、救い、ご愛を感謝し、喜び、信頼して、そんな主が与えて下さる御言葉は良いものと信じて、行うよう、心がけるのです。
序文あっての戒めということを忘れないようにしたいと思います。
<福音を土台として律法を行う恵み、祝福>
さて、そのように神の戒めを、神から与えられた良いものとして、恵みとして受け取って、これを行おうと決心したあと、スンナリそのように歩めればいいのですが、なかなか、そういうわけにはいきません。
十戒なんていう着慣れない着物を着るのは、初めは、窮屈かも知れない。
自分の体には合わない、自分の生活にはあわない、と感じられるかも知れません。
なんで神はこんな無理なことを命じられるのか、と命令のほうが間違っているかのようにも感じられるかもしれません。
人を愛せよと言われても愛せない。
むさぼってはならないと言われても、むさぼってしまう。
ましてや、神を愛することなど、どう逆立ちしても無理。
まじめに神の言葉を行おうとしている人ほど、嫌気がさしてしまうかもしれません。
そういうときに、私たちはもう一度、福音に立ち返ります。
キリストを自分の救い主と信じる者は、戒めを守れる、守れないによって、義と認められたり、罪に定められたりということはない。
そういう原理の下にはない。
ただ信仰によって義と認められるという原理の下にある。
信仰義認の原理。
だから、戒めを守れる、守れないによって、神の子になったり、そうでなくなったり、ということは決してない。
その救いの土台は、私たちの出来・不出来によってブレない。微動だにしない。失敗しても、まったくできなくても、神の子という関係にヒビが入ることはない。
だから安心して、自分のできるところから、御言葉によって生きることを心がければいいのです。
しかももう一つ、キリストを信じる者の恵み、特権は、聖霊が与えられていることです。
聖霊なしには、神の戒めに対して死んだも同然の全く無力ですが、キリストを信じる者には、自分では実感がなかったとしても、聖霊を与えられています。
この聖霊なる神が、私たちの内で働いて下さるのです。
ウェストミンスター信仰告白19章7節より。
…キリストの御霊は、律法に啓示された神の御旨が行うように求めていることを、自由に喜んでなすように、人間の意志を従わせ、またそれをなす力を与えられる。
何という慰め、また励ましでしょうか。
もし、自分の無力さを思わされる時があったとしても、私たちの内に住んでおられる御霊に信頼し、より頼みましょう。
「 御言葉なる 光のうち 主と共に歩まば 行く道筋 照らし給わん 」新聖歌 316番
人は、神の口から出る一つ一つのことばによって生きる、とイエス様は仰いました。
動物はいざ知らず、人は、本能や欲だけで生きるのではなく、神の言葉によって生きる存在。それが人の本質。
人の尊厳、栄光は、そこにある。神は人をそのように造られました。
ところが、最初の人アダムとエバは、そこを踏み外してしまいました。
善悪の知識の木からは、取って食べてはならない、と神は命じていましたが、エバは、神の言葉によって生きることを捨てて、蛇(サタン)の言葉によって行動してしまいました。
アダムもまた(聖書には書かれていませんが)、神の言葉によって生きることを捨てて、「はい、アダムも食べて」というエバの言葉によって行動してしまったのでしょう。
神の口から出る言葉によって生きるという、そこからはずれて、人類は恥辱と悲惨の歴史を歩むことになってしまいました。

16章で見た、天からのパン、マナの食べ方についても、神はイスラエルの民にルールを与えて、神の言葉によって生きる訓練をされました。
パンという命に直結するものも、動物のようにただ本能に従ってではなく、主の言葉に従って食べることを訓練されました。
毎日、その日の分だけ集める。翌日まで残さない。残したものは腐る。
安息日には集めに出かけるな。前日に二日分、与えるから、と。
最初は、彼らはそう言われても、翌日まで取っておく、安息日にも集めに出かける、とまるで反抗期の子どものようなことをしましたが、のちには、神の言葉に従うようになりました。
聖書には、十戒だけでなく、励ましの御言葉、慰めの御言葉もたくさんあります。
私たちの神は、生きておられ、語られる神です。
御言葉を与える神です。
神の御言葉である聖書を読み、親しみ、神の言葉によって生きる幸いにあずからせて頂けますように、そして神の御目に、キリストの似姿をお見せする幸いにあずからせて頂けますように、と願います。
|