<今日の要点>
どんな試練も、主が私たちを支え、乗り越えさせて、最後は栄光に至ると信じる。
<あらすじ>
章が改まって18章。
これまでの試練続きの場面から、いったん、ミデヤンの地へ、かつてモーセが一緒に暮らしていたしゅうとのイテロのもとへと切り替わります。
1節「さて、モーセのしゅうと、ミデヤンの祭司イテロは、神がモーセと御民イスラエルのためになさったすべてのこと、すなわち、どのようにして【主】がイスラエルをエジプトから連れ出されたかを聞いた。」
ミデヤンの地は、モーセたちがいるシナイ半島と、間に紅海をはさんで向こう側にある、広大なアラビア半島の北西部あたりと思われますが、それにシナイ半島の東側の一部を加える人もいます。
このとき、イスラエルがエジプトを出てまだそれほど経ってはいないと思われますが、神がエジプトからイスラエルを救い出されたことは、ミデヤンの地まで届いていました。
何しろエジプトは当時の中近東世界で、誰もが一目置く超大国。
そこで主なる神は、頑強にイスラエルを手放すまいとするエジプトに、次々と十のさばきをもって打った。
そして200万人とも言われるイスラエルの民を、エジプトから解放したというのですから、世界中の耳目を集め、あっちでもこっちでも、このうわさで持ち切りだったでしょう。
そして、その出エジプトを導くために、主がお立てになったのが、自分の義理の息子、40年も一緒に暮らした、あのモーセだと知って、イテロは、いてもたってもいられなくなったのでしょうか。
イテロは、アブラハムの子孫であり、もしかしたら真の神に仕える祭司だったかもしれません。
12節でイテロの持参したいけにえを、モーセが受け入れていることも、そのことを示すようです。
イテロはあらかじめ、どこまで主のご計画を聞いていたのか、わかりませんが、モーセがエジプトにいるとだけは聞いていたでしょうから、毎日、彼のために祈っていたでしょう。そしてこのうわさです。
彼はモーセたちがホレブ山のあたりにいると聞いて、モーセの家族を連れて会いに行きました。
2‐4節「それでモーセのしゅうとイテロは、先に送り返されていたモーセの妻チッポラと、そのふたりの息子を連れて行った。
そのひとりの名はゲルショムであった。
それは『私は外国にいる寄留者だ』もうひとりの名はエリエゼル。
それは『私の父の神は私の助けであり、パロの剣から私を救われた』という意味である。」
最初、モーセがエジプトに向かうとき、途中まで妻チッポラと二人の息子を連れていましたが、例の「血の花婿」事件(4:24-26)のあと、彼女たちを送り返したのだろうと推測されます。
ここで2人の子の名が挙げられています。
ゲルショム「私は、外国にいる寄留者だ」の意。
モーセ40歳のころ、若気の至りで犯した過ちから、パロに命を狙われることとなり、辿り着いた異国の地ミデヤンで暮らす不安、違和感、寂しさと言った心情がうかがわれます。
それが2番目の子のときには、変わっていたようです。
エリエゼル、「神は助け」の意ですが、そのココロは「私の父の神は私の助けであり、パロの剣から私を救われた。」
二人目が与えられたころになって、ようやく安心したのでしょうか。
この頃は信仰を回復して、わが子にも、私の父の神が、私の助けであるとの信仰に立って歩んでほしいと願ったのでしょうか。
彼らは胸を高鳴らせて、ホレブ山で宿営しているモーセのところへ行きました。
そして荒野で、心温まる家族との再会のとき、団欒のときを恵まれました。
5-7節「モーセのしゅうとイテロは、モーセの息子と妻といっしょに、荒野のモーセのところに行った。
彼はそこの神の山(ホレブ山/シナイ山)に宿営していた。
イテロはモーセに伝えた。
『あなたのしゅうとである私イテロは、あなたの妻とそのふたりの息子といっしょに、あなたのところに来ています。』
モーセは、しゅうとを迎えに出て行き、身をかがめ、彼に口づけした。
彼らは互いに安否を問い、天幕に入った。」
あらかじめ、使いを遣わすのは、当時の礼儀作法に則ったものと言われます。
突然行って、驚かせてはいけないという配慮でもあったでしょう。
一年ぶりか、もっとかもしれません。
久しぶりに会う家族。
はやる気持ちを抑えながら、モーセは当時の習慣に従って、イテロの前に身をかがめ、口づけして、その後、久しぶりに会うチッポラと息子たち一人一人の顔を見て、抱擁しあい、再会を喜んだでしょう。
一通り、感動の御対面を終えると、「お元気でしたか、お義父さん」「ああ、わしはこの通り元気じゃ。
お前さんの方こそ、どうだ。
主がなさったことのうわさは聞いておるが。」
「その話は中で。
さあ、天幕にお入り下さい。」
などと安否を問いあって中に入りました。
その後の話は、もっぱら主がイスラエルのためになさったみわざのことだったようです。
口の重いモーセが、饒舌に話しました。
8節「モーセはしゅうとに、【主】がイスラエルのために、パロとエジプトとになさったすべてのこと、途中で彼らに降りかかったすべての困難、また【主】が彼らを救い出された次第を語った。」
伝え聞いただけのうわさと、直接、それを経験した人の言葉は、臨場感、真実味、具体的な細かなことなど、まったく違います。
イテロは身を乗り出して聞き入ったでしょう。

主が、ナイル川をはじめ、エジプト中の水を血に変えたこと、かえるを大量発生させたこと、またそれをモーセの祈りに応えて一夜にして絶やしたこと、ぶよ、あぶの大量発生、それらの災害の中でも、不思議なことに、イスラエルの民は区別されて、災いをこうむらなかったこと、家畜に対する非常に激しい疫病、膿の出る腫物がエジプト中の人にも獣にもついたこと、エジプト史上、未曾有の激しい雹を降らせて、野にある家畜も作物も打たれたこと、それを逃れたわずかばかりの麦の類も、今度はイナゴの大量発生によって食い尽くされたこと、そして三日間、手で触れるかと思うほどの真っ暗闇がエジプト中を覆ったこと、その時もイスラエルの居住地だけは光があったこと、そしてエジプト中の初子が、パロの初子から奴隷の初子に至るまで、さらには家畜の初子に至るまで打たれたこと…。
それでさしもの強情なパロも降参して、イスラエルは、エジプトから出ることができた、しかもそれまでの労賃として金や銀なども与えられたこと。
さらに、エジプトを出た後、追撃してきたパロの軍勢に追い詰められたときにも、絶体絶命のピンチと思われたが、主は目の前の海を左右に分けて乾いた道を造り、そこを通らせて下さったこと、あとを追ってきたエジプト軍は海の中に放り込まれたこと。
語りながら、モーセ自身も感慨深かったでしょう。
思えば、モーセ自身は、主から出エジプトのリーダーとして召されたとき、無理です、誰かほかのふさわしい人を立てて下さい、と何度もしり込みしました。
勇気を振り絞って最初にパロのもとに行ったときも、主の言葉を伝えたらパロは怒ってしまい、かえってイスラエル人の苦役を重くされてしまった。
それで同胞からも、恨まれ、憎まれてしまった。
あのときは、神様、あの約束はどうなっているんですか!話が違うじゃないですか!と食ってかかった。
そんなこともあった。
しかしこうして振り返ってみると、主は確かにそんな不信仰な自分のことも励まし、支えて、出エジプトさせて下さった。
確かに主の言葉通りになった。
エジプトを出てからも、いろんな困難があった。
が、そのすべての困難からも、主は救い出して下さった。
マラで苦い水を甘くして下さったこと、大量のうずらと、天からパンを降らせたこと、岩から水を出して下さったこと、そしてアマレクの急襲に対して、勝利させて下さったこと…。
人の目には、綱渡りのように見えるかもしれない。
しかし実は、どれもこれも、確かな主の御手の内にあって、守られていたことでした。
主がともにおられることは、何よりも確かな安全の保証でした。
これを聞いたイテロも喜びました。
9-11節「イテロは、【主】がイスラエルのためにしてくださったすべての良いこと、エジプトの手から救い出してくださったことを喜んだ。
イテロは言った。
『【主】はほむべきかな。主はあなたがたをエジプトの手と、パロの手から救い出し、この民をエジプトの支配から救い出されました。
今こそ私は【主】があらゆる神々にまさって偉大であることを知りました。
実に彼らがこの民に対して不遜であったということにおいても。』」
主が生きて、実際に働かれたことを聞くと、うれしくなります。
「主はほむべきかな」とイテロの口から思わず賛美の声があがりました。
11節後半は、エジプトがイスラエルに対して、不遜だったと知ったと言います。
たとえエジプトが、この世界ではどれほどあがめられていても、神の愛する民を虐げたのは、不遜であった。
そのことが、このあかしから、よくわかったのでしょう。
私たちも、この世にあっては、今はどういう状況に置かれていたとしても、神の恵みにより、キリストのゆえに、神の愛する子とされた者たちです。
自分がどれほど神に愛されている者なのかを見る霊の目を開かれたいものです
(参考 エペソ1:17−23、新約p. 374)。
そしてこれらのあかしを聞いて、モーセとイテロはいけにえを捧げて、神を礼拝し、そしてアロンと長老たちとともに、祝会を催しました。
12節「モーセのしゅうとイテロは、全焼のいけにえと神へのいけにえを持って来たので、アロンは、モーセのしゅうととともに神の前で食事をするために、イスラエルのすべての長老たちといっしょにやって来た。」
彼らは、ただお祝いしたのではなく、神を礼拝する中でお祝いしました。
このとき、イテロもマナを食べたのでしょうか?おお、これがさっきお前さんが言っていたマナか、と。
「 愛の神は いかなる時にも 頼るなが身 保護し給わん 」新聖歌 311番
イスラエルは、エジプトから救い出され、主の導きに従い、主がともなって下さる旅をしましたが、試練や困難はありました。
しかし、神が私たちを愛しておられるということを土台とするなら、それらの試練は私たちのために益となるはずです。
ローマ8:28、新約p. 302
神を愛する人々、すなわち、神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを、私たちは知っています。
ここの「益」とは、神の目から見た益、つまり本当に益となるもののことです。
宝くじに当たることではありません。
目に見えない、永遠の価値のある益。
神との関係で非常に良いもののことです。
それは私たちに本当の平安を与えてくれるものです(ヘブル12:10-11、新約p. 441)。
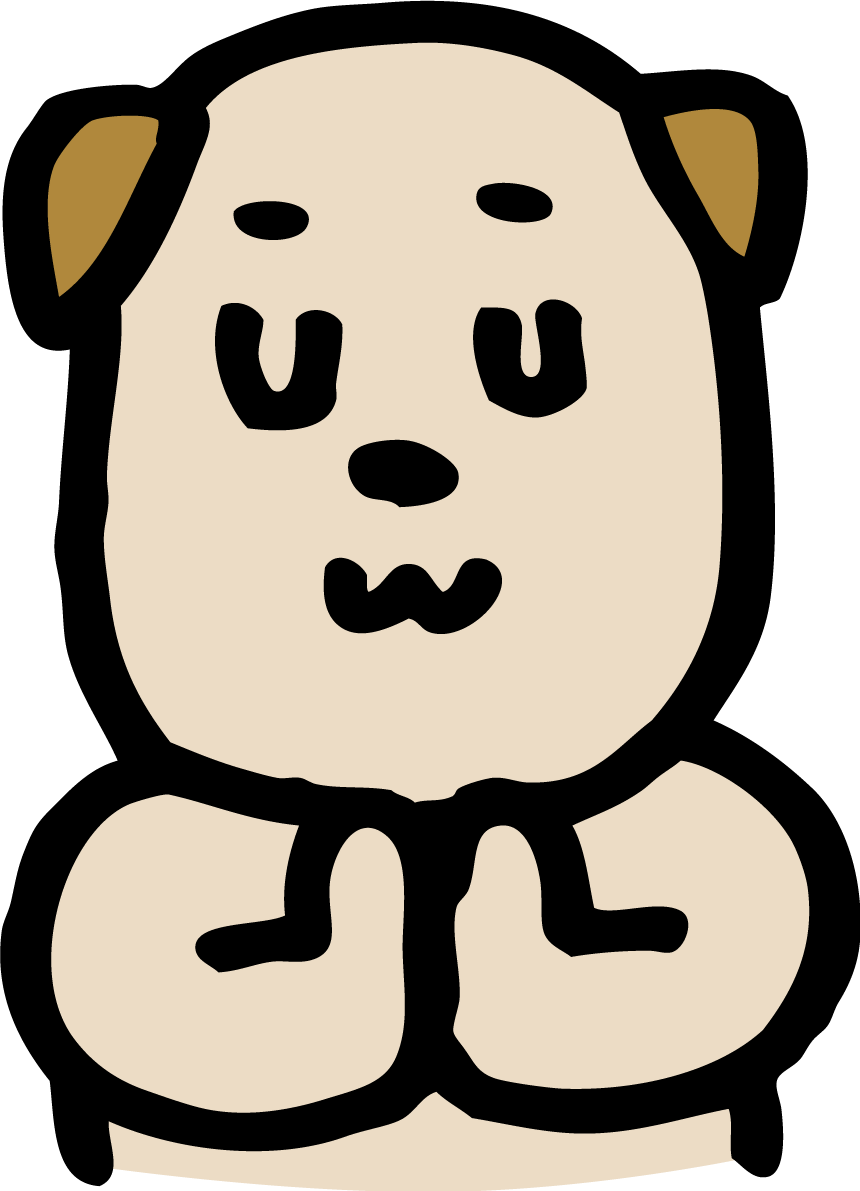
試練の渦中にあるとき、私たちを支えるのは、このような確信ではないでしょうか。
ときには、そう確信できないほどの試練もあるかもしれませんが、神はその間も見えない御手で支えて下さり、やがて聖霊によってこのような確信へと徐々に導いて下さいます。
ですから、今日のような個所を読んで気づかされるのは、試練も困難も、その渦中にあっては苦しみ、大いに揺すぶられるかもしれないけれども、それでもなお、神が恵みによってそれを乗り越えさせて下さったら、それらの試練や困難も最後は、神の恵みをあかしするストーリーになるのだということです。
詩篇119:71、旧約p. 1030。
苦しみに会ったことは、私にとってしあわせでした。
私はそれであなたのおきてを学びました。
この詩人のように告白するときが、主に信頼して従う者には必ず来る。
必ずです。
もしかしたら、この世で経験した苦難も、やがて天の御国の団欒では、主の素晴らしさをあかししあうための材料になるのかな、などと個人的には思ったりします。
人によっては、そんな劇的なあかしはないかもしれません。
しかし、クリスチャンなら誰もが持っているあかしがあります。
このときのモーセ以上のあかしです。
主は力強い御手をもって、イスラエルを救い出して下さいましたが、それは、全宇宙を造った方にとっては、苦もなくできること。
全能の御力を発揮するだけだったら、主ご自身は、かすり傷一つ負いません。
しかし私たちの罪からの救いは、無傷ではできないことでした。
誰か、チリほども罪のない聖い方が、私たちの罪のために、身代わりに神の御怒りを受けなければなりませんでした。
その犠牲を、神が自ら引き受けて下さったのです。
神は最愛の、全宇宙よりもはるかに尊い御子を、罪のためのいけにえとして、私たちに与えられました。
永遠の神の御子は、私たちの身代わりを引き受けて十字架にかかり、神の正しい御怒りを受けて下さいました。
それによって、私たちは御怒りから救われ、神との平和を持ち、永遠に神とともに住む御国を受け継ぐ者とされたのです。
これにまさる救いのみわざのあかしはありません。
御国では、みんな一人残らず、この神のこの上なく尊い救いのみわざを、永遠に喜び、ほめたたえることになるのです。
|