<今日の要点>
イエス・キリストは打たれて、いのちを与えるまことの水を私たちに下さった。
<あらすじ>
前の16章は天からのパン、マナにまつわるエピソードでした。
今度は水です。
パンと同様、水も命の存続に直結する必要不可欠なものです。
しかし、マナは毎日、与えられましたが、水はそうではなかったようです。
飲み水の保証のない荒野の旅は、命がけです。
あたり一面、ゴツゴツした岩と砂が広がり、ジリジリと照りつける日差しに耐えながら、彼らは荒野の旅を続けていました。
そしてようやく次のオアシスに着いたと思ったら、なんと、そこは水が枯れていたのです。
1節「イスラエル人の全会衆は、【主】の命により、シンの荒野から旅立ち、旅を重ねて、レフィディムで宿営した。そこには民の飲む水がなかった。」
レフィディムはシナイ山の北20キロ、ワディ・レファーイドというオアシスではないかと推測されます。
おそらく民は、そこまでいけば水にありつける、と期待していたのでしょう。
ところがそこには水がなかった。
期待していた分、失望も大きく、やがてそれは怒りとなってモーセに向かいました。
2節「それで、民はモーセと争い、『私たちに飲む水を下さい』と言った。モーセは彼らに、『あなたがたはなぜ私と争うのですか。
なぜ【主】を試みるのですか』と言った。」
「下さい」とおとなしく訳していますが、前後を読むと、彼らは相当殺気立っていました。
「水はどうしたんだ、水は。これじゃみんな死んでしまう。
主がともにおられると言うのなら、今すぐ、水をよこせ!」とモーセの胸ぐらをつかみかねない剣幕だったでしょう。
これに対してモーセは「なぜ、主を試みるのか」と言いました。
何か困難があったとき、主がともにおられるというのなら、これこれこうしてみろ、というのは、主を試みることです。
それができたら認める。できないなら認めないと主を試しています。
人が試験官になって、神を試験する側になっています。不遜です。心得違いもはなはだしいことです。
困難にあったとき、人がなすべきは、神を試すのでなく、神に祈ること、信頼することです。
あるいは、主に信頼しきれない不信仰を悔い改め、主の憐れみを乞い求めることです。
神がいるなら、こうしてみろ、という挑発には、神は決して乗りません。
そんな不遜な態度が砕かれて、主の憐れみを乞い求めるようになるまで、沈黙を守られるでしょう。

彼らはまたモーセに文句を言いました。
こんなことなら、エジプトにいた方がよかったと。
3節「民はその所で水に渇いた。それで民はモーセにつぶやいて言った。
『いったい、なぜ私たちをエジプトから連れ上ったのですか。
私や、子どもたちや、家畜を、渇きで死なせるためですか。』」
何かというと、すぐにエジプトにいた方がよかった、と言い出す民。
彼らをエジプトから連れ出し、約束の地に連れ上ると約束して下さった、目に見えないお方に目を留めていない。信頼しない。
確かにこの過酷な状況は、この場面だけを切り取れば、彼らの態度もわからなくはない。
しかし主は、いきなりこの試練を与えたわけではなく、これまで何度も、主が彼らをいかに愛しておられるか、大切にして、守って下さったか、経験していました。
エジプトで奴隷として虐げられていた時、主は大いなる十のさばきをもってエジプトを打ち、彼らを解放しました。
イスラエルの民はその主の超自然的な大いなるみわざを見ました。十回も。
またエジプトを出た彼らをパロの軍勢が追撃してきたときに、袋小路に追い詰められた彼らのために、主が、目の前の海を左右に分けて、海の中に乾いた道を造って彼らを助け出し、その後、追いかけて来たパロの軍勢を海に沈めたのも目の当たりにしました。
さらに以前にも、ようやく見つけた水が苦くて飲めなかったときに、主が示された一本の木をそこに投げ入れると、水が甘くなって飲むことができたこともありました。
そしてついこの間は、エジプトでごちそうを食べていた時の方がよかったと言い出した彼らのために、主は天からのパンとうずらを全員分、供給して下さったことを経験したばかりでした。
パンはその後も、毎日、与えられていました。
これら数々の主の救いのみわざ、大いなるみわざ、恵みのみわざを体験していたのです。
これでもか、というほど。
それなのに、です。主に信頼しないというのは、どういうことなのか。
鬼のような形相で、今にも飛びかかってきそうな群衆に詰め寄られて、モーセも命の危険を感じました。
そして主に叫びました。
4節「そこでモーセは【主】に叫んで言った。
『私はこの民をどうすればよいのでしょう。
もう少しで私を石で打ち殺そうとしています。』」
もう自分の手には負えません。お手上げです。
どうしていいのか、わかりません…。
人生の荒野にも、こういうときがあるかもしれません。
そういう時は、主に叫ぶことです。
聖書を読んでも、キリストに助けを求めないなら、意味がありません。
主は生きておられ、聞いておられるお方です。
心があるお方です。
モーセは叫びました。
叫ばざるを得ない状況でした。
「叫ぶ」とは、必死ということです。
そのような叫びに、主は答えて下さいます。
5-6節「【主】はモーセに仰せられた。
『民の前を通り、イスラエルの長老たちを幾人か連れ、あなたがナイルを打ったあの杖を手に取って出て行け。
さあ、わたしはあそこのホレブの岩の上で、あなたの前に立とう。
あなたがその岩を打つと、岩から水が出る。
民はそれを飲もう。』
そこでモーセはイスラエルの長老たちの目の前で、そのとおりにした。」
ホレブは、主が最初にモーセに現れた場所です。
彼らはその地点まで来ていました。そこにある岩の上で、主がモーセの前に立つと言います。
そしてモーセがその岩を、例の杖で打つと、その岩から水が出る。
それもちょっとやそっとではない。
イスラエルの民全員分の渇きを癒すだけの水が流れ出るというのです。普通なら、信じられないと思います。
しかしモーセは、これまで何度も、主のみわざを経験してきたからでしょう。彼は迷うことなく、主の言われたとおりにしました。
「そのとおりにした」とサラッと書いていますが、これもなかなか、勇気のいることだったと思います。
殺気立っている民の前を通って、長老たちを連れて、と言いますが、モーセが「来なさい」と言って、果たしてついてきてくれるか。
ヘタをしたら「やだよ」と言われて、民の前で恥をかくことになりかねない。
そしてその長老たちの前で岩を打つ。主はその岩を打つと、岩から水が出ると言われたが、果たして岩から水が出るのだろうか…。
もし水が出てこなかったら、恥をかく。信頼を失う。
迷い出したら足がすくみます。
しかしモーセはすべて主が命じられた通りにしました。
そして主の言われた通りにすると、主のみわざが現れます。
主の言葉通り、岩から水が流れ出たのでした。
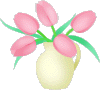
最後にこの場所は、マサ(試み)、またメリバ(争い)と名付けられたと言います。
7節「それで、彼はその所をマサ、またはメリバと名づけた。
それは、イスラエル人が争ったからであり、また彼らが、『【主】は私たちの中におられるのか、おられないのか』と言って、【主】を試みたからである。」
先に書いたように、彼らはこれまで何度も主のみわざを見てきました。
それだけでなく、主は雲の柱、火の柱となって、見える形で彼らとともにいて下さいました。
主が彼らとともにいて、彼らを約束の地に導き入れて下さると約束を頂いていました。
それなのに、主が私たちの中におられるのか、おられないのか、おられるなら、水を出してみろ、と主を試みた民。これはあってはならないことでした。
申命記6:16、旧約p.316
あなたがたがマサで試みたように、あなたがたの神、【主】を試みてはならない。
また詩篇95:7-11、旧約p.1002
95:7 主は、私たちの神。
私たちは、その牧場の民、その御手の羊である。
きょう、もし御声を聞くなら、
95:8 メリバでのときのように、荒野のマサでの日のように、あなたがたの心をかたくなにしてはならない。
95:9 あのとき、あなたがたの先祖たちはすでにわたしのわざを見ておりながら、わたしを試み、わたしをためした。
95:10 わたしは四十年の間、その世代の者たちを忌みきらい、そして言った。
「彼らは、心の迷っている民だ。
彼らは、わたしの道を知ってはいない」と。
95:11 それゆえ、わたしは怒って誓った。
「確かに彼らは、わたしの安息に、入れない」と。
主を試みることが、いかに主を怒らせることか。
肝に銘じておきたいと思います。
困難のときには、主を試みるのでなく、心を尽くして主に信頼し、モーセのように、主に助けを求めて叫ぶ者でありたいものです。
「天つ真清水 流れ来て あまねく世をぞ 潤せる」新聖歌433番
今日は、死に瀕した民の渇きを癒した岩、いのちの水を流れ出させた、あの岩に注目したいと思います。
主はわざわざ岩の上に立たれたということ、何か意味がありそうです。
主と関係ない岩でなく、主がそこにおられる岩です。
また、モーセが手にした杖は、エジプトに裁きをもたらした杖です。
神の裁きの杖です。
主のおられる岩を、神の裁きの杖で打つ。
すると、打たれた岩から、民を滅びから救う水が流れ出た…。
象徴的ではないでしょうか。
使徒パウロはこの岩をキリストと解釈しました(第一コリント10:4、新約p. 331)。
キリストは、私たちの罪のために、鞭打たれ、十字架に釘で打ちつけられて下さいました。
打たれて傷を負って下さいました。痛み、苦しみを受け、血を流されました。それによって、神と私たちの間を隔てていた罪という壁が取り除かれて、いのちの源である神のもとから、私たちを生かす御霊が流れ出たのでした。キリストを信じる者は、誰でもこのいのちの水である御霊を頂くことができます。
永遠のいのち、まことのいのちを与える水です。
私たちにいのちを与える水は、ただ単に井戸かなにかのありかを教えて済むようなものではなく、主ご自身が打たれなければなりませんでした。
私たちの罪のために、主ご自身が血を注ぎ出さなければなりませんでした。
万物の造り主にして、万物の上におられるお方の十字架の苦しみがあって、はじめていのちの水が与えられるのです。
主は、私たちにまことのいのちを与えるために、そのことをして下さいました。
ご自分のいのちを注ぎ出して、主は私たちを招いて言われます。
ヨハネ7:37-39、新約p. 190
7:37 …「だれでも渇いているなら、わたしのもとに来て飲みなさい。
7:38 わたしを信じる者は、聖書が言っているとおりに、その人の心の奥底から、生ける水の川が流れ出るようになる。」
7:39 これはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのである。
…
肉体の渇きは気が付きやすいですが、魂の渇きは気が付きにくいかもしれません。
お金、名誉、成功、人の好意、等々、神ならぬもので、渇きを癒そうとします。
一時的に渇きが癒されたように感じるものはあるかもしれません。
しかし真に永続的に人の魂の渇きを癒すのは、神ご自身をおいてほかに、ありません。
人はそのように造られているからです。
人は、神とともにいることによって、永遠のいのちにあずかり、無条件の、聖い神の愛を限りなく注がれ、喜びと賛美が泉のように心から湧き出ます。
イザヤ書12:2-3、旧約p. 1144
12:2 見よ。神は私の救い。
私は信頼して恐れることはない。
ヤハ、【主】は、私の力、私のほめ歌。
私のために救いとなられた。
12:3 あなたがたは喜びながら救いの泉から水を汲む。

旧約聖書にエゼキエルという預言者の書があります。
彼はあるとき、幻の中で、神殿から水が川のように流れ出るのを見ました。
その水はどんどん増えて泳げるほどの川になり、ついには渡ることのできない川となりました。
そしてこの水について御使いは言いました。
エゼキエル書47:9、旧約p. 1443
この川が流れて行く所はどこででも、そこに群がるあらゆる生物は生き、非常に多くの魚がいるようになる。
この水が入ると、そこの水が良くなるからである。
この川が入る所では、すべてのものが生きる。
いのちを与える御霊が、十字架で打たれたキリストから流れ出て、今や世界中を潤し、信じる者たちを生かしています。
私たちも日々、キリストのもとに行って、救いの御業を思い巡らし、いのちの水を十分に頂くことができますように!
|