<今日の要点>
福音は、私たちの心に歌をもたらす。
<あらすじ>
前回、前々回と見た14章は、出エジプト記中、最も絵になる場面でした。
モーセが手を海に差し伸べると、海が両側に大きく割れて高い壁となり、イスラエルのために乾いた道を造る。
後を追ってきたエジプト軍は、鵜の真似をするカラスよろしく、その道を通ろうとしたが、海の中に沈んだ。
私たちはこうして読んでいるだけなので、どうしても他人事で、なかなかこの時のイスラエル人の感動がわからないのですが、この神の救いを実際に体験した当のイスラエル人にしたら、ものすごい感激、感動だったに違いありません。
抑えきれない感動は、歌となって表現されます。
1節。
「そこで、モーセとイスラエル人は、【主】に向かって、この歌を歌った。
彼らは言った。
「【主】に向かって私は歌おう。
主は輝かしくも勝利を収められ、馬と乗り手とを海の中に投げ込まれたゆえに。」
「主に向かって私は歌おう」と、この賛美をどなたに向けて歌うのか、明確にします。
私たちも賛美のとき、ただ歌っているのではありません。
どなたに向けて歌っているのか、明確に主を意識して、主に向かって、賛美したいものです。
続いて、賛美する理由が続きます。
何の故に、主を賛美するのか。
主が敵であるエジプト軍に対して圧倒的な勝利を収められたから、です。
主は無条件にほめたたえられるべきお方ですし、創造のみわざの素晴らしさに感動して造り主をほめたたえるということも、もちろんよいことですが、私たちは実際に主が自分を窮地から救い出して下さった経験をしたときに、いっそう強い賛美の思いが沸き起こります。
賛美の源泉は、感動です。また感謝です。そこが賛美のいのちです。
うまいへたは気にせず、賛美しましょう。主は心をご覧になります。
続く2節は、その、主への賛美の思いが、湧き水のようにあふれ出ます。
短い言葉の羅列が、感動の強さをうかがわせます。
人は強く感動すると、冗長な表現は出てこず、短い言葉を次々と発するのでしょう。
「主は、私の力であり、ほめ歌である。
主は、私の救いとなられた。
この方こそ、わが神。
私はこの方をほめたたえる。
私の父の神。
この方を私はあがめる。」
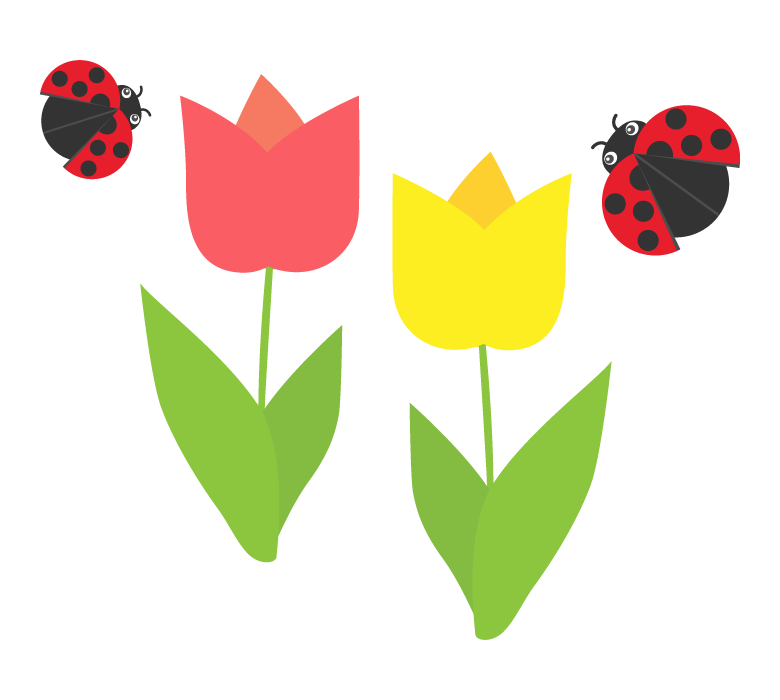
真っ先に出て来たのは、主はわが力ということでした。
詩篇でも「主は私の力」という表現が出てきます。
さて、私たちが力としているものは、実際のところ、何だったかな、と問われるようです。
神を、私の力とすることができたら、どんなに心強いことでしょう!神は天と地を造られた方なのですから!あれもこれも、心配なことがいっぱいあって、重荷に押しつぶされそうに感じることも、長い人生にはあるかもしれませんが、天地を造られた神がわが力!とこの信仰一本でスッキリと立ちたいものと、あこがれさせられます。
神をわが力とするなら、どんな状況にも希望を失うことはないでしょう。
そして「主はほめ歌」です。
歌です!しかもこの「歌」の原語は、元々「指でたたく」の意から来ている言葉で、歌詞よりも楽器で奏でる曲を意味していたらしいのです。
モーセの時代だと弦楽器、打楽器でしょうか。
言葉だけでは足りず、メロディーにのせて賛美を捧げずには、いられない。
ここにも喜び、感動の強さがうかがわれます。
確かに、ただ助かったというよりも、神が自分を窮地から救って下さった体験をすると、神に覚えられていることを実感して、うれしくなります。
主の救いは喜びなのです。
賛美は、キリスト教に特徴的なものとよく言われるのは、この救いの喜び、感動があることのあかしです。
2節後半は、似た表現を並べて繰り返す並行法になっています。
「この方こそ、わが神。
私はこの方をほめたたえる。
/私の父の神。
この方を私はあがめる。」
これも単なる表現上の技巧というよりも、感動の強さの表れなのでしょう。
感動が強いと、一回言っただけでは気が済まず、何回も繰り返したくなるものです。
炭酸水を良く振ってふたを開けると、その後いくら手で抑えようとしても抑えられずに、中から噴き出してくるように、感動が強いと一度の賛美では収まらないのです。
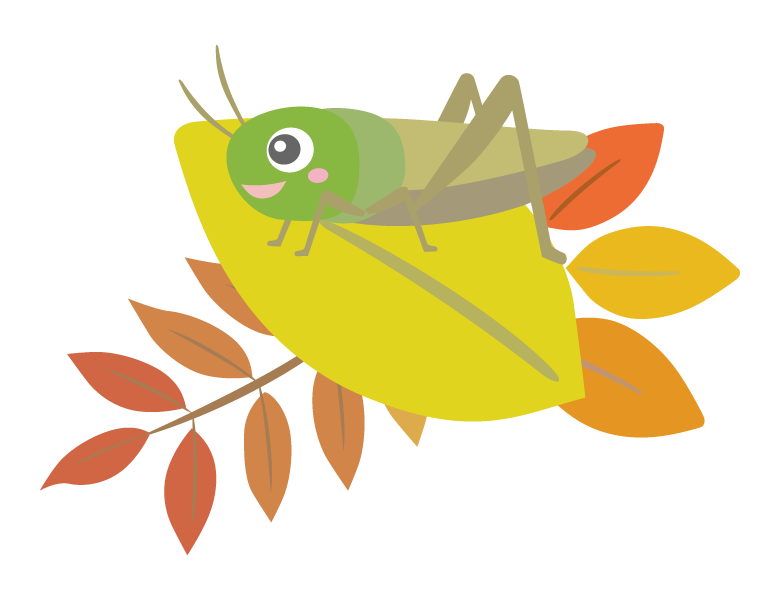
以下、彼らが体験した主のみわざを描写します。
彼らの救いは、彼らを滅ぼそうとする者の滅びです。
それゆえ、3節では「主はいくさびと」と表現され、以下、彼らを守るために戦って下さる主のみわざ、エジプト軍の滅びの様子を生々しく描写します。
こうして具体的に歌うことで、後代の人々へ印象深く伝え、主への信仰を励ますのでしょう。
6節「【主】よ。
あなたの右の手は力に輝く。
【主】よ。
あなたの右の手は敵を打ち砕く。」
聖書では「右」は力や権威を表します。
ここでは力を表すのでしょう。
ここで、この歌の構造について一言。
この歌は、形式の上では1番から3番までの3つの連節から成り、各連節の終わりには繰り返しがなされ、その直前には「〜のように」という直喩が置かれるという形式になっています。
たとえば1番は1-6節で、最後に
「主よ。あなたの右の手は…」という句が繰り返され、その直前には「石のように」となっています。
2番は7-11節、ここも終わりに「だれか(が)あなたのような(に)」という句が繰り返され、直前は「鉛のように」です。
3番は12-16節、「民が通り過ぎるまで」という句が繰り返され、その直前は「石のように」。
そして17-18節は結びとなります。
他方、内容的には、大きく二つに分かれていて、1-12節が今、彼らが体験した主の救いのみわざの賛美、13-18節はこれから主が彼らを約束の地へ導いて下さることを、すでに成就したかのように確信に満ちて歌っています。
エジプトからの救いと、約束の地に導かれることは、出エジプト記の二つの大きな主題です。
これは現代の信仰者にとって、キリストによるサタンの支配からの救いと、約束の御国を受け継ぐまでの主の導き、地上の歩みに対応します。
それで、形式的には7節から2番に入りますが、ここも1番に続いて、主がエジプトになさったさばきのみわざが、さらに具体的に生々しく、かつ比喩が多用されて、歌われます。
歌い出し7節「威力」は、原語では1節の「輝かしくも勝利を収めた」と訳された語からの派生語で、並行関係にあるようです。
8節「鼻の息」の「息」はヘブル語「ルーアハ」で、これは「風」も表します。
前回見た「東風」は「ルーアハ・カーディーム」ですから、この主の鼻の息という表現は、あの東風を連想させます。
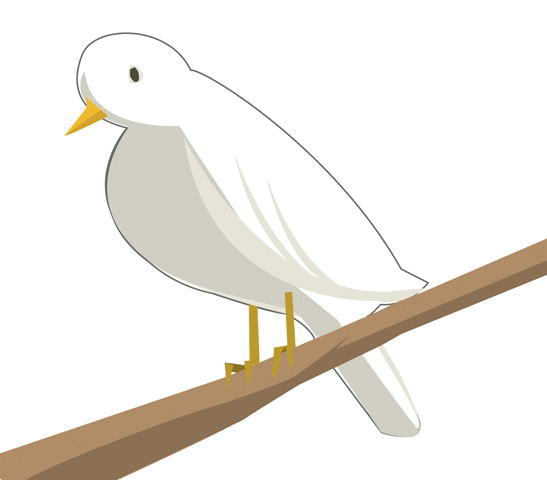
私たちからすると、神の鼻息という表現は変な感じがするのですが、イスラエル人の間では好まれたか、しばしば出て来る表現です。
特に神のさばき、怒りを表すときに使われるようです。
9節には敵エジプト人のセリフが記されます。
自分の欲望を剣によってかなえよう、と。
自分の欲望を満たすために、人を人とも思わない、人の命を奪うことを何とも思わない、このような悪人が、残念ながら罪の世には存在するようです。
しかしそんな悪の軍勢も、10節「あなたが風を吹かせられると、海は彼らを包んでしまった。
彼らは大いなる水の中に鉛のように沈んだ。」
と、彼らに対する主の大いなるさばきのみわざを誇らしく歌います。
悪に対するさばきは、正義が行われるということです。
それゆえ、正義を待ち望む者にとって、主がさばきを行われるのは、主への賛美のときとなります。
世の終わりにも、同じことが起こります。
こうして2番の結び
「【主】よ。
神々のうち、だれかあなたのような方があるでしょうか。
だれがあなたのように、聖であって力強く、たたえられつつ恐れられ、奇しいわざを行うことができましょうか。」
と力強く正義を行われる主の唯一性を繰り返してほめたたえます。
3番は、12節で主がエジプト人をおさばきになったことに触れて(「地」が飲み込んだとは、よみに下ったの意か)、その力あるお方が、以下、これから約束の地カナンに私たちを守り導いて下さることを確信と喜びをもって歌います。
13節「あなたが贖われたこの民を、あなたは恵みをもって導き、御力をもって、聖なる御住まいに伴われた。」
と、これからのことなのにすでに実現したことのように語られるのは、これが預言的に語っていることで、必ずそうなるとモーセが確信して言ったからと説明されます。
ヘブル語では預言的に語られたことは、未来のことであっても確実にそうなることなので、完了形が使われることがあるのです(ヘブル語には基本的に完了形と未完了形の二つしかない)。
ともかく、モーセは、この主の大いなる御救いを体験して、主はこれからも、信仰的とは言えない民をも恵みをもって導き、荒野にあっても偉大な御力をもってあらゆるわざわいから、また敵から守り、必要を満たして、必ず約束の地に伴って下さると確信して、すでに与えられたかのように、喜びをもって歌ったのでしょう。
私たちも、将来の神の救いを確信をもって、すでに与えられたかのように喜び、賛美したいものです。
14-16節は、彼らがカナンの地に入るまでに通らなければならない周辺の国々と、カナンの先住民のこと。
彼らが、エジプトに対してなされた主のみわざを聞いて、恐れおののくという預言です
そして最後17-18節は結び。
これから彼らが向かうゴールをもう一度指さして歌います。
「ご自身の山」はエルサレム。
「御住まいのためにあなたがお造りになった場所」は「あなたの御手が堅く建てた聖所」と言い換えられます。
これは神殿のことです。
つまり、彼らの生活の中心に神礼拝があり、神が彼らとともにおられ、とこしえに主が彼らを治められる、という幻をモーセは思い描いたのでしょう。
この17-18節は、出エジプトの目的、ゴールを示します。
神とともに住む神の都が、私たちのゴール、望みでもあります。
それをすでに与えられたものとして思うことは喜びであり、心が元気づけられることです。
19節はもう一度、主のみわざを簡潔に記して、20-21節はモーセの姉ミリヤムが音頭を取って、女性たちが歌と踊りで花を添えた様子が記されます。
歌だけでなく踊りもあり。
楽器はタンバリン。
主の救いの喜びを表現する方法は多彩です。
ちなみにこの時、ミリヤムは90歳前後か、それ以上と思われます。
「感謝なき日はなく 賛美なき夜はなし」新聖歌 266番
主の救いを経験したモーセは、喜び、感動して、歌を歌いました。
喜び、感動から歌が生まれます。
ほかの人が歌った賛美を聞いて励まされる、ということもありますが、最初に歌ができるのは感動があるからです。
そして福音は、私たちの心に歌を生み出すのです。
私は以前、牧師として四六時中、教会の働きをし、長い時間祈り、説教の準備のために週に二度くらい徹夜し、ときに断食祈祷、徹夜祈祷をしていた時期がありました。
が、あるとき、そこに喜びがないことに気づかされ、愕然としました。
一生懸命、主に仕えているつもりだけれども、喜びがなく、心は乾ききっていました。
憐れみ深い主は、そんな私に福音の再発見の機会を与えて下さいました。
もちろんそれまでにも、福音を知識としては知っていましたし、神学校で訓練を受けましたから、講壇から間違ったことは語らなかったと思います。
しかし、心の深いところは福音に対して閉ざされていたのだと思います。
福音をもっと深く掘り下げよう!決心して、私はむさぼるように福音について学びました。
福音を妨げているのは、心の中にある偶像です。
偶像が明らかにされるのは、痛いことでもありましたが、それらを悔い改めると、自由が与えられました。
そして少しずつ、神の愛が頭でなく心に沁み込んできました。
そしていつしか、福音から湧いてくる喜びが、魂を静かに潤し始めていました。
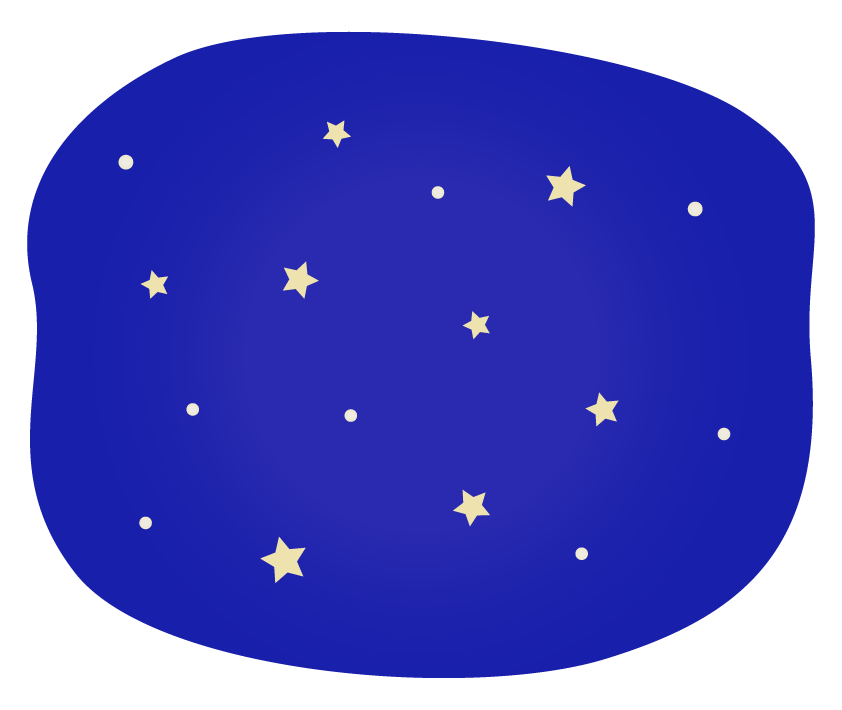
そしてあるとき、ふと気が付くと、歌を口ずさんでいたのです。
以前の私には、なかったことでした。
福音を深く学んで、偶像が取り除かれ、神の愛が少しずつ心に沁み込むようになって、自然と歌が心から湧いて、口から出ていたのです。
福音は、私たちの生活に歌をもたらします。
それが、主の喜ばれる霊の捧げものだと思います。
そして驚くべきことに、福音は、神ご自身にも喜びの歌をもたらすのです!
ゼパニヤ 3:17、旧約p1542。
これは救いが完成した時のことと思われますが。
…主は喜びをもってあなたのことを楽しみ、その愛によって安らぎを与える。
主は高らかに歌ってあなたのことを喜ばれる。
みなさんは、神の喜びの子なのです。
ぜひ、神が自分を喜んでおられるということを、心に思い巡らしてみて下さい。
神は尊い御子を十字架に渡して、私たちの罪を赦し、ご自身の子として下さいました。
それほどの犠牲を払ってまで、手に入れたいと思って下さった私たちです。
神は私たちを喜んでおられるのです。
歌まで歌われて!その喜びの大きさ!
|