主は、私たちにとって、さばく方ではなく、癒す方であることを確信する。
<あらすじ>
直前の20-21節。
「アロンの姉、女預言者ミリヤムはタンバリンを手に取り、女たちもみなタンバリンを持って、踊りながら彼女について出て来た。
ミリヤムは人々に応えて歌った。
『【主】に向かって歌え。
主は輝かしくも勝利を収められ、馬と乗り手とを海の中に投げ込まれた。』」
主が自分たちを守るために、強力なエジプト軍と戦って下さり、輝かしい勝利を収められたことを、イスラエル人たちは誇らしげに歌いました。
これで彼らを脅かすエジプトの脅威は完全に消え去りました。
彼らは喜ばしい心持ちで、主の鮮やかなみわざを口々にほめたたえながら、約束の地に向かって旅を続けたことでしょう。
しかしその感動は、残念ながらいつまでもは続きません。
やがて厳しい現実を前に、主のみわざを忘れてしまいます。
彼らが歩いているのは、荒野でした。
22節「モーセはイスラエルを葦の海から旅立たせた。
彼らはシュルの荒野へ出て行き、三日間、荒野を歩いた。
彼らには水が見つからなかった。」
エジプト北東部の「葦の海」から、シナイ半島北西部にあった「シュルの荒野」へ彼らは出ましたが、三日間、歩いても歩いても、水がなかったと言います。
持ってきた水は底を尽き、喉はカラカラ。
このまま、干からびて死んでしまうのではないか、そんな恐れもよぎるでしょう。
そんなときに、さらに追い打ちをかけたのは、マラでの出来事でした。
23節「彼らはマラに来たが、マラの水は苦くて飲むことができなかった。それで、そこはマラと呼ばれた。」
「マラ」は「苦い」の意。
三日歩いて、ようやく見つかったと思った水。
主よ、感謝します!一瞬、喜んで口にしてみたら、苦くて飲めなかった…。ぬか喜びだった。一瞬、喜んだだけに、落胆も大きい。
腹も立つ。こういうとき、要注意です。
24節「民はモーセにつぶやいて、『私たちは何を飲んだらよいのですか』と言った。」
聖書の「つぶやく」は文句・不平を言うという意味です。
彼らがこうなってしまうのも無理はないかな、と不信仰な私なんかは、思ってしまいますが、注解書には「つぶやきは基本的には神への不信であって、彼らは神の大勝利を経験していながら、困難に直面して三日目で神への不信に陥った」と書いていました。
確かに彼らが、神の救いのわざを実際に体験していたというのは、大きなことです。
彼らは、三日前に体験した主の大いなる救いを、目の前にある困難に関連付けることができなかったのです。

三日前の奇跡が、神が自分たちに備え、守って下さる真実な方だということと、結びついていなかったのです。
私たちも、神が御子を下さるほどに、私たちを愛しておられるという、あの十字架にあらわされた神の真実なご愛を、目の前の困難に関連付けることが、できなくなっているときが、あるかもしれません。
解決した!と思ったら、ぬか喜びで、いったんはガッカリしても、そこで御子をさえ下さった神の御愛にまたしっかりと立って、なお、主に信頼し続ける二枚腰の強さ、良い意味のしぶとさを身に着けたいものです。
モーセはこの問題を主に持っていきます。
25節「モーセは【主】に叫んだ。
すると、【主】は彼に一本の木を示されたので、モーセはそれを水に投げ入れた。
すると、水は甘くなった。
その所で主は彼に、おきてと定めを授け、その所で彼を試みられた。」
モーセはしょっちゅう、主に叫んでいます。
実際、モーセの力でどうにかなるものではない問題なので、主に叫ぶしかない。
みなさん、自分の手ではどうにもならない問題、もしあったら、主に叫んで下さい。それが主の御心です。
主は時に私たちを主に叫ぶしかない、というところに置かれます。
そのときに、素直に主に叫ぶことができることが、大切です。
このとき、主はモーセの叫びに答えられました。
しかしいきなり、苦い水を甘くしたのでなく、まず一本の木をモーセに示し、そしてモーセがその木を水に投げ入れると、水が甘くなりました。
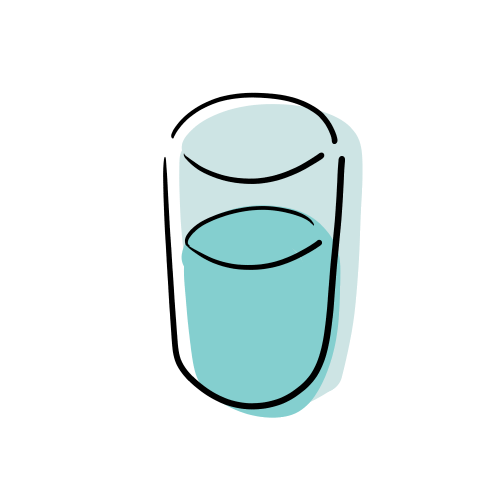
モーセが持っていた杖でなく、突然、示された一本の木によって、苦い水が甘くなった。
これは古来、キリストの十字架を表すとされます。
私たちの苦い罪の心を、甘い御霊の実を生らせる心に造り変えるキリストの十字架です。
また主の十字架は、試練を恵みに変え、わざわいを祝福に変え、死さえも、いのちに変えます。
キリストの十字架は、あらゆる苦みを甘みに変える、魔訶不思議な奇跡の木です。
ところで、ここで苦い水を甘くして終わり、ではありませんでした。
主はここでモーセにおきてと定めを与え、また彼を試みたとあります。
おきて、定めの内容は26節と思われますが、主はここでモーセの何を試したのか。
おきて、定めを与えたこととセットで記されていることを考えると、モーセが心を尽くして主を愛するかどうかを試した、ということかもしれません。
主の救いを体験して、主がどれほど自分を愛して下さったかを知り、そして主を愛する者となったなら、その戒めは重荷とはならず、むしろその愛する方の戒めを守りたくなるものだからです。
Ⅰヨハネ5:3、新約p470。
神を愛するとは、神の命令を守ることです。
その命令は重荷とはなりません。
またヨハネ14:15、新約p210。
もしあなたがたがわたしを愛するなら、あなたがたはわたしの戒めを守るはずです。
主のことば、主が与える戒めを守るかどうかは、主を愛するかどうかが試されているのです。
もちろん、完全に守れる人は誰もいません。
しかし最初から、「そんなもの!」と守る気もない、気にも留めないというのでは、主を愛しているとは言えないでしょう。
そんなことを踏まえると、続く26節前半は、心を尽くして主を愛するか、が問われている言葉のようにも見えてきます。
「そして、仰せられた。『もし、あなたがあなたの神、【主】の声に確かに聞き従い、主が正しいと見られることを行い、またその命令に耳を傾け、そのおきてをことごとく守るなら、…』
これらはただ戒めを守れ、というのでなく、心を尽くして主を愛することが求められているのではないでしょうか。
「あなたの神、主の御声に確かに聞き従い」と強調されています。
「聞き従い」と訳された語は「聞く」が本来の意味の語。
まず聞くことから。
週の初めに礼拝を捧げることは、まず主の声を聞くというライフスタイルです。
主の御声の中心は、「あなたはわたしの目には高価で尊い」ということです。
「あなたはわたしの愛する子。
わたしは、わたしのひとり子を与えたほどにあなたを愛している」ということです。
まず、この主の御声を、毎週というより毎朝、心の耳でしっかりと聞きましょう。また主の御声を求めて、日曜日、水曜日だけでなく、自分で聖書を読む、学ぶことも有益です。
また良質の信仰書や教理の本を読むのもよいでしょう。
信徒向けに書かれた神学書も出ています。
体系的に学ぶことは、正しく聖書を理解するために必要です。
そして「主の目に正しいことを行い」主の目に正しいか、どうか、ということを基準にして行動するということです。
自己中心になって、自分が基準になってしまいがちな私たちには、必要な戒めです。
「その命令に耳を傾け、主のおきてをことごとく守る」そもそも、従うべき命令や守るべきおきてが、あるという意識もなかったかもしれません。
現代の私たちにも、たとえば十戒は有効です。
命令も、おきても、私たちが幸せに生きるために、主が与え、定めておられるものです。
また私たちの魂を罪から癒すために必要なものでもあります。
このように心を尽くして主の言われる通りにするなら、26節後半「わたしはエジプトに下したような病気を何一つあなたの上に下さない。…」
と仰います。イスラエルは集団生活をしていましたから、伝染性の疫病が流行ったら、ひとたまりもありません。
しかしそんなわざわいを下さないと、約束を与えて彼らを励まします。
そして最後に「わたしは【主】、あなたをいやす者である。」
と言われました。
エジプトに十のわざわいを下したり、追撃してきたパロの軍勢を海の中に放り込んだり、すべてはイスラエルを救うために主がしたことですが、その場面を見て、何か主をこわい方、わざわいを下す方という印象が、イスラエル人のうちにあったかもしれません。
またモーセは、イスラエルの民も、罪のゆえにさばかれるのでは、と心配したかもしれません。
しかし、主はエジプトに対しては、さばきを行う方ですが、イスラエルに対しては癒す方と言われるのです。
モーセはこのことばを聞いて、大いに励まされて、次なる宿営地へと出発したでしょう。すると次に導かれたのはオアシスでした。
27節「こうして彼らはエリムに着いた。
そこには、十二の水の泉と七十本のなつめやしの木があった。
そこで、彼らはその水のほとりに宿営した。」
ちょうど一部族に一つずつ、12の泉が備えられていました。
「なつめやし」の木は、比較的乾燥した地にも強く、果実は日本でも「デーツ」として売られています。
乾燥したものは保存食になり、可食部100g(約7粒)あたり270kcalになります。
これが一本の木から大量にとれます。

ここで水と食糧を補給できて、一息つけました。
私たちの人生にもマラがあるかもしれませんが、主はそのあとにエリムを用意しておられるのかもしれません。
マラで止まってしまったら、エリムはありません。
私たちもマラで止まることなく、エリムまで進みましょう。
ヘブル書12:11、新約p.441。
すべての懲らしめは、そのときは喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になると、これによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。
「妙なる御恵み 日に日に受けつつ」新聖歌300番
主はご自身を「いやす者」と示されました。
病院へ行くと、医師、看護師が、患者を癒すために、忙しくしています。
病院の目的は、癒すことです。癒すために最善を尽くしています。
たとえもし仮に、その病気なりケガなりが、自業自得でなったものだったとしても、そのことをさばくことが医師の仕事ではありません。
患者を良くするために厳しいことを言うかもしれませんが、それはさばくことが目的ではありません。
あくまでも癒すこと、健康にするためにすべてのことをします。
私が小学生の頃、左足のスネを骨折しました。
石膏のギプスでひざまでガチガチに固めて、骨折した部位が動かないようにしました。
3か月後、ギプスを取ったときには、ひざの関節が固まってしまって、そこを動かすためのマッサージは、大の大人でも逃げ出すほどの激痛でした。
しかしそれも癒すためにすることです。

同様に、私たちにとって苦しいことでも、主は、私たちに対して、ただ癒すことだけを願って与えます。
主は私たちにとって、さばく方でなく、癒す方です。
なぜなら、キリストが私たちの罪に対するさばきをすべて、引き受けて下さったからです。
キリストのゆえに、主は私たちに対して、ただただ恵み深い方であられ、私たちを癒すことだけを考えておられます。
ここを確信しましょう。
神が世界を創造されたとき、世界は祝福に満ちていました。
神は祝福することを喜ばれる方、祝福することが神の本性と言ってもいいでしょう。
人の罪のゆえに世に病が入り、死がすべての人を支配するようになっても、神は病を癒し、死からよみがえらせて下さるお方です。
神はご自身の子らを祝福し、御国を祝福で満たすことをこそ、願っておられるお方です。
神を何か、わざわいを下す恐ろしい方と思っていたら、大間違い。
人の罪のゆえに、世には悲惨があふれるようになってしまいましたが、神はそれを喜んでおられるのでは決してない。
神の本心は祝福したいのです。
たとえ私たちが罪ある者となっても、神はさばくことではなく、赦し、癒すことを望んでいるのです。
エゼキエル18:23、旧約p.1387 。
わたしは悪者の死を喜ぶだろうか。
──神である主の御告げ──彼がその態度を悔い改めて、生きることを喜ばないだろうか。
そのために、神は最愛の御子をさえ、十字架に渡されました。
私たちが神の愛を知って悔い改め、いのちを得るようにと。
御子イエス様は言われました。
ルカ5:31-32、新約p.118。
そこで、イエスは答えて言われた。
「医者を必要とするのは丈夫な者ではなく、病人です。
わたしは正しい人を招くためではなく、罪人を招いて、悔い改めさせるために来たのです。」
私たちが地上の旅路で、どれほど積み上げているかしれない罪の数々。
それに対しても、無尽蔵の赦しの恵みを用意して、私たちを悔い改めへと招き、私たちの魂を癒し、あらゆる良きもので満たそうとして下さる主に導かれて歩む幸いを感謝したいと思います。