主は、ご自身を愛する人のところに来て、ともに住み、主を愛する歩みを応援して下さる。
<はじめに>
「神が私たちとともにおられる」ことは、神の祝福(あるいは契約)の中心、本質です。
これに勝る祝福は、天にも地にもありません。
イエス・キリストはインマヌエルとも呼ばれました。
それは「神が私たちとともにおられる」という意味です。
そのためにキリストは人となって世に来られ、十字架にまでかかられました。
天地を造られた神ご自身が、私たちとともにおられるとは、なんと心強いことでしょうか。
神が、私たちの味方であるなら、何を恐れることがあろうか、と思います
(ローマ8:31、新約p302)。
しかし他方で、現実の世界に目を向けると、コロナ、戦争、自然災害、それらから生じる様々な影響を考えて、不安を覚えるかもしれません。
こういう時に、神がともにおられるとの約束を信じる信仰が、揺さぶられるのもまた、偽らざる事実ではないでしょうか。
そのような現実に少しでもよりよく対処できることを願って、さらには神が望んでおられるところに従って、私たちの信仰のあり方が成長・成熟に向けて、ある意味、脱皮することを願って、この御言葉を選びました。

神がともにおられるから大丈夫だと、この約束を支えとすることも良いことです。
神はその信仰も喜ばれます。
しかし、ただ単に「神が私たちとともにおられる」と覚えるだけだと、どこか受け身な感じがしないでしょうか。
主体的に私たちが神を愛するという姿勢に転じた方が、より私たちの安全につながると思いますし、神に喜ばれるでしょう。
またこの約束を、ただ私たちを守って下さるという意味においてだけ、信じるとするなら、それは、その人自身の態度としては、ご利益宗教信者と変わらないとも言えます。
私たちにとって、イエス様は単なる「守り神」なのでしょうか。
そうではないと思います。
もちろん、より頼む対象が、天地を造られた神なので、他のご利益宗教信者とは決定的に違います。
真の神により頼む信仰は、良しとされます。
ですが、主体的に、こちらから愛するという姿勢に転じることで、新しい段階へと進むことができます。
「守り神的信仰」から、「主を愛する信仰」へと、ちょっとした意識改革というと大げさかもしれませんが、でもこれは大きな方向転換の一歩です。
この方向に踏み出す時に、さらに神の愛を、体験を通して知り(これが聖書的な意味の「知る」です)、神がそばにいて下さっているという確信が、強められるのではないかと思います。
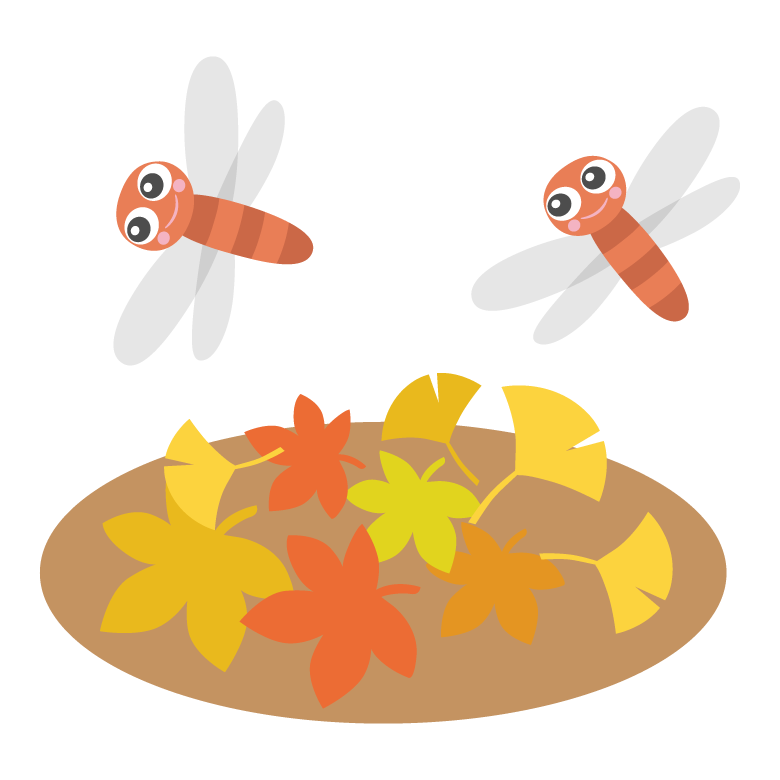
愛とは本来、相互的なもので、交流を通して深められるものだからです。
神との愛による人格的な関係が豊かに従って、神は決して私をお見捨てにならないとの確信が強固になる。
そしてそこから、この世のものではない、神だけが与えることのできる平安が恵まれ、かつは喜びが生まれるのだと思います。
生ける主との人格的な交わりが深められることによって、荒野のような状況にあっても、生活の中に御霊の川の流れる、豊かな信仰生活へ、また確信に満ちた信仰生活へ導かれるようにと願います。
<前半:主を愛して、その主への愛を、みことばを守るという形で表す>
ここの「わたし」はイエス・キリストです。
誰でも、イエス様を愛する人は、イエス様のことばを守ると言います。
愛する相手のことばは、自然と気になるものですし、心にとどまるものです。
もちろん、完璧にイエス様のことばを守ることのできる人は、一人もいません。
ただ、イエス様のご愛を知って、私たちの方でもイエス様を愛する意志を持つことでよいのだと思います。
理想は、イエス様のご愛を知って、私たちの心のうちに自然とイエス様への愛が生まれ、成長し、実を結ぶことです。
しかし、なかなか、そううまくはいかないものです。
まずはイエス様のご愛を受けて、それに対する応答として、イエス様を愛する意志を持つことから、始めればいいのです。
そしてイエス様を愛するから、イエス様のことばを守る、と自分に言い聞かせます。
そしてイエス様への愛を、イエス様のことばを守るという形で表します、と主に申し上げます。
イエス様が最も喜ばれる贈り物は、どんな金銀財宝よりも、御言葉を行う従順です。
それがイエス様への霊の捧げものです。
イエス様のことばを行うという形で、イエス様への愛を表現しましょう。
もちろん、生身の人間ですから、難しいこともあります。
気持ちがついて行かないこともあるでしょう。
しかし、旧約聖書の中に、面白い律法があります。
「あなたを憎んでいる者のろばが、荷物の下敷きになっているのを見たら、それを起こしてやりたくなくても、必ずいっしょに起こしてやらなければならない」という律法です
(出エジプト23:5、旧約p136)。
気持ちが伴わなくても、形から入るということも、アリなのです。
「それは偽善だ!」などとサタンの屁理屈に惑わされてはいけません。
助けたくない感情を抑えて、善を行うことは、立派なことなのです。
神はそれをよしとされるのです。
主を愛するという部分が抜けて、主のことばを守るという行いだけに心が奪われると、律法主義の罠に陥ります。
窮屈になります。
主を愛するという、根っこの部分があって、主のことばを守るという実を結ぶのです。
十字架に表された主の愛を思い巡らすことによって、私たちの主への愛も、少しずつ深められ、根を張っていくのでしょう。
主の愛を思い、主を愛して、主のことばを守るという形で主への愛を表す。
あるいは主への霊の捧げものを捧げる。
その意識を忘れないようにしたいと思います。
それでも、現実はスンナリとはいかないでしょう。
そのように生きようとするときに、自分の罪を思い知らされるかもしれません。
しかし、たとえつまずいても、転んでも、主を愛して、主のことばを守ろうと努力しているご自身の子たちを、神は決して冷たく突き放したりは、なさいません。
むしろ、そばに来て、励まして下さる。応援して下さる。
近くに来て、伴走して下さる。目に見えない霊的祝福で取り囲んで、主が近くにおられる喜びを与えて下さる。
それが、この御言葉の後半で言われていることだと思います。
<後半:主も、私たちへの愛を、来て、ともに住むという形で表して下さる>
ここで、そうすれば、父はその人を愛するとあります。
ここは教理をよく学んでいる方には、引っ掛かるところです。
ここの「愛する」は、神の愛を、こういう形で、私たちにわかるように、表して下さる、という意味に取ると良いと思います。
神は、キリストを信じるすべての人を、この上ない、永遠の、絶対の愛をもって愛しておられます。
私たちの行いに一切よらず、ただただ100%、神の一方的に注がれている、無条件の愛です。
私たちの救いは、この神の絶対の愛から出ています。
だから揺るがない。だから安心なのです。
ただ、そのご愛をどう表すかは、機械的に一律ではありません。
その人にとって、―その人の霊的成長にとってー最も益となる形で表されるのだと思います。
その原則に従って、神は、イエス様を愛して、そのことばを守ろうと、けなげに努力している人のところに来て、その人ともに住んで、その人を応援するという形で、ご自身の愛を表して下さるということです。
信じるすべての人に対する最高の愛は変わらないけれども、私たちの成長の段階に応じて、状態に応じて、ふさわしい表し方をされるのだと思います。
本当は、神の方ではすべての人に、このような形でご自身の愛を表したいと願っておられるのです。
けれども、私たちの方が主を愛していないのであれば、主はご自身のことを愛してもいない人のところに押しかけて、ともに住むなどということは、できません。
相手の人格を尊重するのが、本当の愛というものでしょう。
主は、私たちの心が主の方に向いて、主を愛したいという意志を持つようになるまで、じっと待っておられるのだと思います。
「わたしたち(御父とイエス様)はその人のところに来て、その人とともに住みます。」
とあるのは、目に見える姿で私たちのところに来るというのではありません。
目に見えない形で、つまり聖霊において、私たちのそばに来て下さるということです。これも、教理を学んでいる人には引っ掛かるところです。
イエス・キリストを信じたときに、すでに聖霊がその人のうちに与えられ、その人のうちに住んでおられます。
内住の御霊などと言われます。
この御霊は、私たちの救いの保証として与えられています(エペソ1:13-14、新約p373)。
救いにかかわることー真のいのちにかかわることーは、有無を言わさず、与えられます。
私たちが求めるようになるまで、待つのではありません。
この保証としての御霊は、私たちの側では全然、実感がなくても、私たちの内におられます。
このお方は、私たちの救いを確証し、御国に入るまで守って下さる方なので、いついかなるときにも、取り去られることはありません。
イエス様を愛するどころか、自分では信仰の火が消えてしまったかのように思っても、御霊はその人の中心におられます。
例えて言えば、バーベキューで燃やした炭が、炎が出なくなって、外から見たらもう表面が白くなって、まったく赤いところが見られず、すっかり冷めたように見えることがあります。
でも、中の方にはまだ火があるのです。
そして風を送ると、パーッとまた燃え上がります。
そのように、すっかり信仰の火が消えて、冷めきったように見えても、その人の核の部分というか、中心には御霊がおられて、その人を守っておられます。
私たちの救いを保証するために与えられている御霊だからです。
このヨハネ14:23で、御父とイエス様が来て、ともに住んで下さると言われているのは、それとは別のことです。
「その人とともに住みます。」
の「ともに」と訳された言葉は、「そばに(beside)」の意味です。
救いの保証としての御霊は「内に(in)」おられます。
こちらはそばにです。
私たちは、神が遠く離れているように感じることが、あるのではないでしょうか?それに対して、神がそばにおられると感じることもあります。
もちろん、感覚と信仰は別です。
保証としての御霊は、私たちが全然、感じなくても信じるべきことです。他方、信仰生活において、神の臨在の祝福は、遠く感じることと、近くに感じることがあります(参考:ウェストミンスター信仰告白18章「恵みと救いの確信について」4節)。
そして、神の愛、キリストの愛を知って、私たちもキリストを愛するという目標に向けて歩むときに、神はそのことを大いに喜ばれて、私たちのところに来て、ともに住んで、目には見えませんけれども、生活を共にして、応援して下さる。
そういう形で、私たちへの愛を表して下さるというのです。
これは、すばらしい励ましではないでしょうか!何のためにイエス様がこう仰ったかというと、私たちのイエス様を愛する歩みを励ますためです。
それほど、イエス様は、私たちのような者の愛をも、望んでおられるのです。
結び 「心に主の愛 溢れて歌う」新聖歌 352番
パスカルという人は「神を信じることから愛することまでは、いかに遠いことか。」
と言いました。
パスカルほどの人でも、こうだったのか、です。
神を愛することは、一生かけて目指すべき高き嶺です。
短距離走でなく、長距離走のつもりで、息長く、根気よく、継続しましょう。
途中転んでも、疲れて休んでも、いいのです。
やめないことが大事です。
伴走しておられる主に励まされて、完走を目指しましょう。
「誰でも」とイエス様は言いました。
金持ち、貧乏、社会的な立場、関係ありません。
イエス様を愛する者は、誰でもです。
この約束は公平に誰にでも与えられています。
一方的に注がれている神の愛を受けて、キリストを信じたときに、内住の御霊は与えられ、救いは保証されました。
それはスタート地点です。
そこから、神を愛し、神との交わりを豊かにする歩みへと成長・成熟していくことが、神の御心です。
神は、私たちの主を愛する歩みを応援するために、来て下さって、ともに住んで下さいます。
主がともに住んで、ともに生活を営むとは、それこそ、神の国に生活するということです。
この醍醐味を味わう経験を恵まれますように。
いや、願うなら、必ず恵まれます。
イエス様は仰いました。
ルカ12:32、新約p140
小さな群れよ。恐れることはない。
あなたがたの父は、喜んであなたがたに御国をお与えになるからです。